この記事にはプロモーション・広告が含まれています
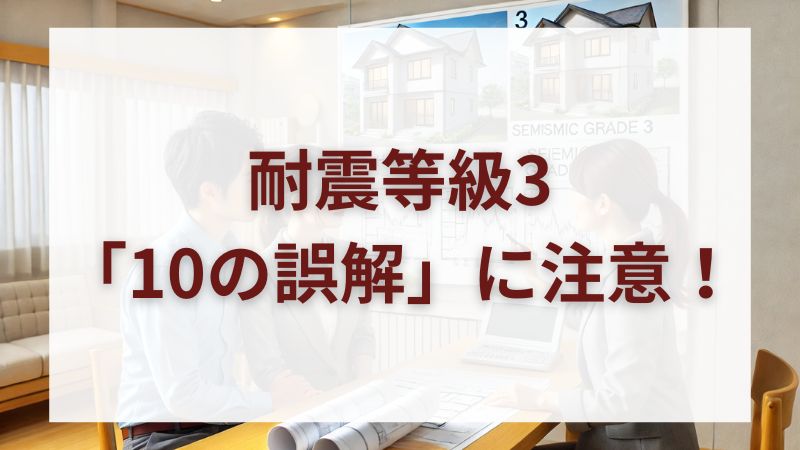
家族を守る住まいを建てるとき、「耐震等級3」という言葉を耳にする方は多いでしょう。耐震性能の最高等級であることから、強い地震にも安心だと期待する人が少なくありません。
しかし実際には、耐震等級3に関する情報は断片的で、営業トークやネット記事の一部が誤解を生みやすい状況にあります。「耐震等級3なら無傷で済む」「どの家も同じ耐震性能」といった誤解が、重大な見落としにつながることもあるのです。
>>「耐震等級3は過剰」という声の真実|住宅選びに失敗しない知識と判断方法
>>【耐震等級比較ガイド】等級1・2・3の違いと、あなたに合った選び方
本記事では、耐震等級3に関するよくある誤解を10のポイントに整理し、それぞれについて「誤解の背景」「正しい事実」「理解しておくべき重要性」を専門的に解説します。情報を正しく理解することで、安心できる家づくりの第一歩を踏み出しましょう。
耐震等級3とは何か?その本質を理解する

「耐震等級3」とは、住宅の耐震性能を評価する「住宅性能表示制度」において最も高い等級であり、建築基準法で定められた耐震基準の1.5倍の地震力に耐えることを示しています。消防署や警察署など防災拠点に求められる基準と同等の耐震性能であり、「震度6強から7程度の地震でも倒壊しない強度」が求められます。
>>【保存版】耐震等級3の実力とは?震度5〜7での性能を徹底検証
この等級は、単に強い家という意味だけでなく、「命を守る最低限のラインを、さらに強化した基準」として位置づけられています。つまり、倒壊を防ぐことを目的とした性能であり、「無傷を保証するものではない」という点を理解することが重要です。
耐震等級3の取得には、構造計算による耐震性の裏付けや、第三者機関による審査を経る必要があります。設計の信頼性や安全性が客観的に確認される仕組みとなっています。一方で、同じ耐震等級3でも設計内容や施工精度により実際の耐震性能に差が出ることもあります。
耐震等級の基本的な区分とその意味
住宅性能表示制度における耐震等級は、次の3段階に区分されます。
- 耐震等級1
- 耐震等級2
- 耐震等級3
耐震等級1
建築基準法で定める耐震基準を満たすレベルで、震度6強から7程度の地震で倒壊しない性能。
耐震等級2
耐震等級1の1.25倍の耐震性能を持つ。学校や病院など災害時に避難場所となる施設で求められる基準。
耐震等級3
耐震等級1の1.5倍の耐震性能を持つ。消防署や警察署と同等の防災拠点とされる建物に求められる基準。
このように、耐震等級は「耐えられる地震の大きさ」に比例する階層構造となっており、等級が上がるほど求められる強度が高くなります。ただし、建物が「壊れない」ではなく「倒壊しない」ことを目的としている点は共通です。
「耐震等級3=無敵」という誤解の背景
「耐震等級3」と聞くと、「どんな地震でも壊れない」と誤解してしまう人が少なくありません。この誤解は、等級の定義が「建物が倒壊しない強度」であるにもかかわらず、「建物が無傷で済む」と受け取られやすい表現に起因しています。
実際には、耐震等級3の住宅でも大きな地震で内装材の剥落やひび割れ、設備の破損が発生する可能性があります。建物は倒壊しなくても、生活再建には修繕が必要になる場合があるのです。耐震等級3はあくまで「構造体」の強度を示すもので、家具や設備の安全性、火災リスクなどは別途対策が必要です。
この誤解を放置すると、必要な備えやリスク管理を怠り、結果的に「安全だと思っていたのに被害が大きかった」という事態につながりかねません。耐震等級3は非常に高い性能基準である一方で、「絶対の安全を保証するものではない」という冷静な理解が不可欠です。
誤解されがちな10のポイントとその真実

「耐震等級3」と聞くと、最高ランクの耐震性能として「絶対に安全」と信じてしまう方が少なくありません。しかし実際には、その意味や限界を正しく理解していないと、大切な家づくりで見落としや誤算につながるリスクがあります。
ここでは、耐震等級3に関して多くの方が誤解しやすい10のポイントを取り上げ、事実と正しい理解をわかりやすく解説します。
1. 耐震等級3なら地震で絶対に倒壊しない?
「耐震等級3」とは、建築基準法で定める耐震基準の1.5倍の地震力に耐える性能を持つ等級です。しかし、これは「建物が倒壊しないこと」を目的としており、「無傷で済むこと」を保証するものではありません。
- 構造体の倒壊を防ぐ性能
- 内装材や設備の損傷は防げない可能性
- 命を守る性能と無被害は同義ではない
「耐震等級3なら無傷」と信じ込むと、防災意識が低下し、必要な備えが欠けるリスクにつながります。
被害を最小限に抑えるには、家具の固定や備蓄品の準備など、追加の防災対策が不可欠です。
2. 耐震等級3を取得すれば、どんな地盤でも安心?
耐震等級3は「建物の構造体」に関する評価であり、地盤の強さを保証するものではありません。軟弱地盤や液状化リスクのある土地では、耐震等級3でも被害を受ける可能性があります。
| 誤解 | 実際の内容 |
| どの土地でも安全 | 地盤によって安全性は異なる |
| 等級3なら地盤調査不要 | 地盤調査と基礎対策は別途必要 |
| 地盤補強不要 | 必要なら補強工事が求められる |
「耐震等級3だからどこでも大丈夫」という誤解は、見えないリスクを見落とす原因になります。
家づくりの際は、必ず地盤調査を実施し、必要に応じて補強や改良工事を検討しましょう。
>>【耐震等級3は完璧じゃない?】ハザードマップで見抜く「本当に安全な土地」の選び方
3. 「耐震等級3相当」は正式な認定と同じ?
「耐震等級3相当」とは、設計段階で耐震等級3と同等の性能を目指したものであり、正式な認定ではありません。認定を受けるには、第三者機関による審査と確認が必要です。
>>【耐震等級3の中古住宅】相当とは違う?正しい見極め方と必ず確認すべき書類
- 「相当」は正式認定ではない
- 住宅性能評価書がなければ法的証明にならない
- 認定取得済は書類で確認できる
「相当」と「正式認定済」は法的にも内容的にも異なります。契約時には認定書類の有無を必ず確認しましょう。
正式認定があれば、地震保険料の割引や将来の売却時に有利になるなどの利点もあります。
4. 耐震等級3の取得には構造計算が不要?
木造2階建て以下の住宅では、壁量計算だけで建築確認申請が可能な場合がありますが、耐震等級3の認定には「許容応力度計算」などの詳細な構造計算が必要です。
>>「耐震等級3」が家族の未来を守る。地震後も“暮らせる家”の選び方とは
| 計算方法 | 内容 |
| 壁量計算 | 簡易計算。許容応力度計算には不十分 |
| 許容応力度計算 | 詳細計算。耐震等級3取得には必須 |
「簡易計算で耐震等級3が取れる」という認識は誤りです。
構造計算は設計の信頼性を裏付けるものであり、必ず実施する必要があります。設計者にどの計算方法を用いるのか確認しましょう。
5. 耐震等級3の家はすべて同じ性能?
耐震等級3の認定を受けた家であっても、設計内容や施工精度によって実際の耐震性能に差が出ます。認定は「設計図面通りに施工されること」が前提であり、現場での施工ミスがあれば性能は低下します。
>>【平屋でも耐震等級3は必要?】知らないと危険な間取りと構造リスク
- 設計が同じでも施工精度で性能に差が出る
- 第三者検査の有無で品質に差が出る
- 工事記録や検査履歴の確認が重要
「認定があるから絶対安全」とは限りません。信頼できる施工体制を選ぶことも不可欠です。
工事中の写真記録や構造見学会への参加、第三者監理の活用など、品質を確保するための工夫をしましょう。
6. 耐震等級3の取得はコストが高すぎる?
耐震等級3の取得には構造計算や追加の耐力壁、補強材の使用が必要になるため、耐震等級1や2よりも初期コストが上がる傾向にあります。ただし長期的には修繕費や地震被害のリスク低減により、トータルコストで有利になる可能性があります。
| 費用項目 | 内容 |
| 設計費 | 構造計算・設計変更費用が発生 |
| 材料費 | 耐力壁・金物・補強材の追加費用 |
| 施工費 | 工期延長や施工難易度によるコスト増 |
- 初期費用は耐震等級1より高い
- 長期的な補修・地震被害リスクは低下
- 保険料割引や資産価値維持に貢献
「高いだけ」と捉えず、長期の費用対効果で判断することが重要です。
7. 耐震等級3の家ならメンテナンスは不要?
耐震等級3を取得した住宅でも、経年劣化や自然災害による微細な損傷は避けられません。基礎や接合部の緩み、外壁のひび割れなど、小さな劣化が積み重なると耐震性能が低下します。
- 10年ごとの点検・補修が推奨される
- 基礎部分の防水・防蟻処理の再施工が必要
- 地震後には外観・内部の点検が必要
「取得したら終わり」ではなく、定期点検・補修を行うことで、性能を維持できます。
8. 耐震等級3の家なら地震保険は不要?
耐震等級3の家でも、地震被害により損傷や補修が必要になる可能性はあります。保険の対象は「建物の損害」であり、耐震等級3であっても無被害は保証されません。地震による火災や津波被害は耐震性能とは無関係です。
| 誤解 | 実際の内容 |
| 耐震等級3なら保険不要 | 損害補償は保険加入が必要 |
| 全損しなければ保険無意味 | 部分損害でも保険金が出る場合がある |
| 地震による火災もカバー済み | 火災保険では補償外、地震保険が必要 |
- 地震保険料の割引が適用される
- 建物・家財どちらも加入できる
- 保険金額上限は評価額の50%まで
「耐震等級3だから保険不要」と誤解せず、地震リスクに備えて保険も検討しましょう。
>>あなたの家、本当に大丈夫?“耐震等級3”が必要な現実とは
9. 耐震等級3の家は資産価値が常に高い?
耐震等級3は高い耐震性能を示す指標ですが、それだけで将来的な資産価値が保証されるわけではありません。立地条件、周辺環境、築年数、メンテナンス履歴なども評価に影響します。
>>耐震等級3の家は資産価値が落ちない?売却・賃貸で有利になる理由を徹底解説
| 誤解 | 実際の内容 |
| 耐震等級3なら資産価値は安泰 | 立地や維持管理状況も大きく影響する |
| どこでも同じ評価 | 地域や市場動向に左右される |
| 取得時点で将来の価値が決まる | 長期の維持管理で価値維持が左右される |
- 定期的な補修・メンテナンスが重要
- 売却時には性能評価書の提示が有利
- 立地・インフラ整備状況も資産価値に影響
「耐震等級3だから高く売れる」は保証されません。価値を維持するための行動が必要です。
10. 耐震等級3の取得は誰でも簡単にできる?
耐震等級3の取得には、構造計算・審査・設計調整など多くの工程が必要です。設計士や構造設計者との協議、確認申請、第三者機関の審査を経るため、一般的な耐震等級1の住宅より手間と時間がかかります。
- 設計段階で耐力壁や補強の検討が必要
- 許容応力度計算や審査費用が発生
- 認定取得には第三者審査の合格が必要
「誰でも簡単に取れる」わけではなく、専門家の関与と適切な設計が不可欠です。
耐震等級3を目指すなら、経験豊富な建築士や工務店に相談し、十分な計画期間を確保することが成功のカギとなります。
誤解を生む背景とそのリスク

耐震等級3に関する誤解は、単に情報不足だけではなく、情報の伝わり方や営業トークの影響によっても生まれています。誤った前提で家づくりを進めると、必要な備えを欠いたり、過度な期待で判断を誤るリスクが高まります。
情報の断片化と営業トークの影響
住宅の耐震性能についての情報は、インターネット記事、広告、営業担当者の説明など、さまざまな経路で入手されます。しかし、これらの情報の多くは一部分のみを切り取っており、背景や制約条件まで詳しく説明されていないことが多いのです。
| 情報源 | 特徴 |
| 営業トーク | 自社の強みを強調する傾向 |
| ネット記事 | 誤解を招く表現や誇張が含まれる場合がある |
| SNS | 体験談や主観的意見が中心 |
- 一部情報が強調され誤解を生む
- 全体像や条件が伝わりにくい
- 情報の正確性が確認しづらい
「断片的な情報の積み重ね」が誤解を助長します。信頼できる情報源と専門家の意見が不可欠です。
誤解を放置することのリスク
誤解を抱いたまま住宅購入や建築を進めると、「期待していた安全性と違う」「想定外の追加費用が発生した」といった問題が後から表面化します。耐震等級3に対する過信は、命を守るために必要な備えや判断を遅らせるリスクにもつながります。
- 家具固定や避難経路確保が後回しになる
- 地盤調査や補強工事の重要性を軽視する
- 建物完成後に不満や不安が残る
「知らなかった」「聞いていなかった」では済まされない課題が、安全性や暮らしに直結します。
>>【南海トラフ・首都直下地震に備える】高リスク地域にこそ「耐震等級3」の家を建てる理由
正確で総合的な理解を持つことが、家族の安全を守る第一歩です。情報を受け取る際には、「誰が」「どの立場で」「何を目的に伝えているか」を意識する習慣をつけましょう。
正しい情報を見極めるためのチェックリスト

耐震等級3に関する情報を正しく理解するには、入手した情報の信頼性を確認し、自分自身で裏付けを取る意識が重要です。以下のチェックリストを活用し、誤解や勘違いを防ぎましょう。
- 情報の出典が公的機関・公式機関である
- 担当者が資格を持つ建築士または構造設計者である
- 数字や用語に具体的な根拠が示されている
- 設計図書や評価書など公式書類で裏付けされている
- 営業トークだけでなく複数の資料で確認している
このチェックリストを意識することで、「聞いただけ」「ネットで見ただけ」の情報から一歩踏み出し、自分で正しい判断ができるようになります。
公式な認定書類の確認方法
耐震等級3が正式に認定されているかどうかは、「住宅性能評価書」で確認できます。評価書には評価機関名、等級、評価内容が明記され、設計図面に基づいた第三者評価の結果として発行されます。
- 評価書の発行日と有効期限を確認
- 評価機関が国土交通大臣登録の機関であるか確認
- 評価対象の建物住所・物件名が一致しているか確認
評価書がなければ「相当」と記載されていても正式認定ではありません。契約時に必ず確認しましょう。
専門家への相談のポイント
耐震等級3を正しく理解するには、資格を持つ専門家への相談が不可欠です。相談時には、以下のポイントを意識しましょう。
- 設計者が構造計算の知識を持っている
- 説明内容が根拠に基づいている
- 質問に対して明確な回答がある
- 曖昧な表現やごまかしがない
- 書類や計算資料を提示してくれる
「わからないまま進めない」「疑問はその場で解決する」姿勢が、後悔しない家づくりにつながります。
相談先の選び方とポイント

耐震等級3の取得や正しい理解のためには、信頼できる相談先を選ぶことが重要です。選ぶ相談先によって得られる情報や対応が大きく異なるため、特徴を把握して比較することが求められます。
ハウスメーカーと工務店の違い
耐震等級3を取得する際、相談先としてハウスメーカーと工務店のどちらを選ぶかによって、設計の自由度やコスト、対応内容に違いがあります。
>>【間取り制限は誤解?】耐震等級3でも叶う“自由設計”の家づくり完全ガイド
| 項目 | ハウスメーカー | 工務店 |
| 設計の自由度 | 標準仕様が多く自由度はやや低め | 柔軟に対応しやすい |
| 価格帯 | 一定の価格設定で追加費用が出やすい | 仕様次第で調整可能 |
| 保証・対応 | 長期保証・アフターサービスが充実 | 保証内容は会社ごとに異なる |
| 耐震等級対応 | 自社標準で耐震等級3仕様を用意 | 工務店によって対応力に差がある |
- 標準仕様重視ならハウスメーカーが選択肢
- 個別対応や地域密着型なら工務店が適する
- 相談内容や優先事項に応じて選ぶことが大切
「耐震等級3を取得できるか」だけでなく、対応実績や施工精度も比較ポイントに加えましょう。
>>耐震等級3の家は“信頼できる施工会社”で!悪質業者に騙されない見極め術
第三者機関の活用方法
相談先の選定や情報の妥当性を確認するために、第三者機関の利用も有効です。中立的な立場からアドバイスや検査を行ってくれるため、営業トークや偏った情報に左右されない判断ができます。
- 住宅性能評価機関に事前相談する
- 独立系の建築士事務所にセカンドオピニオンを求める
- 工事中に第三者検査を依頼する
「自分だけでは判断が難しい」と感じたら、第三者の視点を取り入れることで安心感が高まります。
信頼できる相談先を選び、複数の意見を取り入れることが、耐震等級3を正しく理解し、最適な家づくりにつながります。
誤解に惑わされない「耐震等級3」の正しい選び方

耐震等級3は、家族を守るための非常に高い耐震基準ですが、その意味や限界を正しく理解することが欠かせません。誤った情報や過信に基づいて家づくりを進めると、安全性や費用面で後悔につながるリスクがあります。
>>耐震等級3でも倒壊リスク?見落としがちな落とし穴と安全に守る対策
本記事では、耐震等級3に関する「よくある誤解」と「実際の事実」を10のポイントに分けて解説しました。これらを正しく知ることで、「知らなかった」では済まされない後悔を防ぎ、冷静で客観的な判断力が身につきます。
>>【命を守る家】子どもも高齢者も安心「耐震等級3」という最強の備え
家族の命と暮らしを守る家づくりには、「正しい情報を知り、自ら選ぶ力」が必要です。
ぜひ、ここで得た知識を活かし、信頼できる専門家や相談先と共に、納得できる家づくりを進めてください。そして不安や疑問があれば、迷わず第三者の専門家に相談し、確かな裏付けのある選択を重ねていきましょう。家族の未来を守る一歩は、正しい理解から始まります。
憧れの大手メーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれる

住宅展示場や完成見学会にいくのは時間もかかるし大変…
そんなときに便利なのが「タウンライフ家づくり」です。
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
気になるメーカーや工務店を選び、希望の間取りや予算を入力するだけ。「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる!
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。

「タウンライフ家づくり」はこんな方におすすめ
- あなただけの間取りと見積もりを無料で手に入れ比較したい
- 営業されるのが嫌、苦手
- 自宅でじっくり信頼できるハウスメーカーを選びたい
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ




