この記事にはプロモーション・広告が含まれています
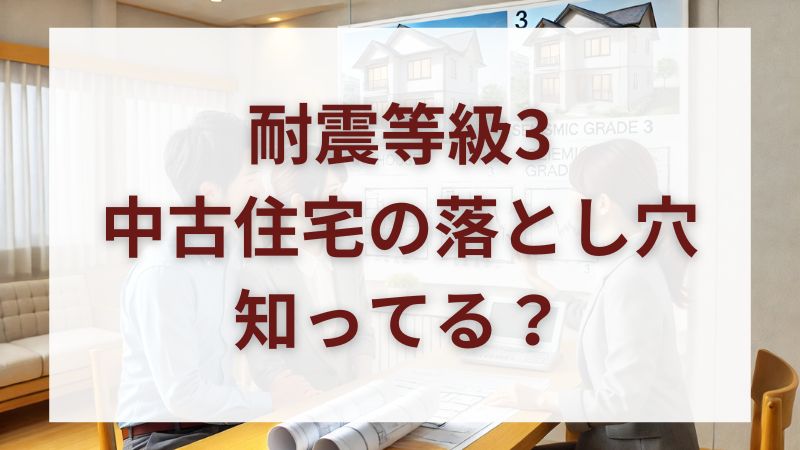
中古住宅を購入する際、多くの方が「家族の安全を守れるか」を重視します。地震大国である日本では、住宅の耐震性が大きな関心事となっています。その中でも最も高い耐震性能を示す「耐震等級3」の住宅は、強い揺れにも倒壊しにくいとされ、注目を集めています。
>>【南海トラフ・首都直下地震に備える】高リスク地域にこそ「耐震等級3」の家を建てる理由
しかし実際に中古住宅市場で「耐震等級3」の物件を探すと、数が少なく情報も限定的で、どこに気を付ければ良いのか迷う方が少なくありません。耐震等級3相当」といったあいまいな表現や、証明書の有無など、見落としやすいポイントも多いのが現実です。
>>耐震等級3でも倒壊リスク?見落としがちな落とし穴と安全に守る対策
この記事では、中古住宅で耐震等級3を選ぶ際に知っておくべき確認ポイントを詳しく解説します。誤解を避け、後悔のない住宅選びができるよう、探し方から確認方法、注意点まで実践的な情報をお届けします。
>>耐震等級3は完璧じゃない?誤解しがちな10の落とし穴と正しい対策
中古住宅における耐震等級3の見つけ方

「耐震等級3」の中古住宅は、新築住宅に比べて圧倒的に供給数が少なく、物件探しに苦戦する方が多いのが現状です。そもそも中古市場では、耐震等級の情報自体が十分に公開されていないケースもあります。耐震等級3の中古住宅を見つけるには、供給数が少ないという前提を理解し、的確なアプローチを取る必要があります。
多くの中古住宅は、建築当時の耐震基準や住宅性能評価制度の有無に左右されます。2000年の建築基準法改正以降に建てられた住宅であっても、必ずしも耐震等級3を取得しているわけではなく、評価書が発行されていない物件も少なくありません。そのため、単に築年数や立地だけで選ぶのではなく、証明書や性能評価の有無を確かめる視点が不可欠です。
耐震等級3の中古住宅が少ない理由
耐震等級3の中古住宅が市場に少ない背景には、いくつかの要因があります。まず、耐震等級3が制度化された2000年以降でも、実際にこの等級を取得して建築された住宅の割合は限定的です。多くの住宅が耐震等級1や2で建築されており、最高等級を目指す動きが一般的ではありませんでした。
中古住宅の売却時に耐震等級を証明する書類が整っていないケースも多いです。性能評価書は新築時に取得しても、保管されていない、または売主側が把握していないことが少なくありません。耐震等級3の証明書類が残っている中古住宅は、そもそも流通数が極めて限られているのです。
このように、耐震等級3の中古住宅は、制度上取得のハードルが高いだけでなく、書類の保存や情報開示という流通上の課題によって、さらに希少性が高まっています。
中古住宅で耐震等級3を見つけるための条件
耐震等級3の中古住宅を見つけるには、物件タイプや建築背景に注目することが重要です。特定の条件に該当する住宅は、耐震等級3を取得している可能性が比較的高い傾向があります。
ハウスメーカーによる注文住宅
大手ハウスメーカーでは、標準仕様で耐震等級3を採用しているケースがあります。新築時に等級3で建てられた住宅は、性能評価書が発行されている可能性が高いです。
分譲住宅で販売時に性能評価書付き
分譲住宅でも、性能評価書付きで販売された物件は、等級3を取得していることがあります。ただし、必ずしも全棟が対象ではないため、個別の確認が必要です。
長期優良住宅の認定を受けた住宅
長期優良住宅の認定には、耐震等級2以上が求められますが、等級3で認定を受けている住宅も存在します。この認定住宅は書類の保存が義務付けられており、確認がしやすい傾向にあります。
これらの条件を満たす物件は、耐震等級3である可能性が高く、購入時に証明書類を入手できる確率も上がります。
中古住宅における「耐震等級3相当」という表現に注意
物件情報の中には「耐震等級3相当」と記載されていることがあります。一見「耐震等級3と同じ性能」と誤解しがちですが、この表現には注意が必要です。耐震等級3相当」という表現には、正式な住宅性能評価書の裏付けがない場合が多いのです。
正式な耐震等級3は、国土交通省の定める「住宅性能表示制度」に基づき第三者機関による評価を受けたものです。しかし「相当」という表現は、設計段階や工務店の自主評価によるもので、証明力が限定されることがあります。実際に性能評価書が発行されていない場合、住宅ローンや地震保険の割引適用にも影響を及ぼす可能性があります。
このため、「相当」の記載を見かけた場合は、必ず「正式な住宅性能評価書があるか」を確認する必要があります。証明書がない場合、その物件の耐震性能は自己責任での判断となり、購入後に想定外の補強工事が必要になるリスクもあります。
購入時には以下の資料があるかを確認しましょう。
- 住宅性能評価書(新築時)
- 設計住宅性能評価書
- 建築確認申請書の副本
- 構造計算書(該当する場合)
これらの書類を確認することで、「相当」という表現の裏付けを探り、リスクを最小限に抑えることができます。中古住宅では、情報のあいまいさを放置せず、必ず証明書類の有無を確認する姿勢が大切です。
「耐震等級3相当」と「耐震等級3」の違い

中古住宅を検討する際、「耐震等級3相当」という文言に出会うことがあります。一見すると正式な耐震等級3と同等の性能があるように見えますが、実際には大きな違いが存在します。耐震等級3」と「耐震等級3相当」は、証明方法と法的な裏付けにおいて明確な差があるのです。
耐震等級3は、住宅性能表示制度に基づき、第三者機関による正式な評価を受けた証です。評価の過程では、建築確認申請や設計審査、施工中の検査が行われ、性能評価書として発行されます。この評価書は、金融機関の住宅ローン優遇や地震保険の割引適用などの裏付けとして機能します。
一方、耐震等級3相当という表現は、設計士や施工業者が自社の設計基準や構造計算に基づいて「等級3相当の性能がある」と判断しただけの場合があります。正式な評価書が伴わないことが多く、法的効力や第三者認定がないことが一般的です。そのため、金融機関や保険会社で優遇措置が受けられない可能性もあります。
>>耐震等級3の家は“信頼できる施工会社”で!悪質業者に騙されない見極め術
「耐震等級3相当」の物件を購入するリスク
「耐震等級3相当」と記載された物件を購入する際には、いくつかのリスクが伴います。正式な評価書がない場合、建物の性能を裏付ける書類が存在せず、購入後に実際の耐震性能が期待以下だったと判明する可能性があるのです。
注意が必要なのは、耐震等級3相当が設計図面上の計算結果に基づくもので、施工時の検査や実地確認が省略されているケースです。設計段階での性能と、完成後の実際の性能には差が生じる可能性があります。評価書がない物件は、性能を保証されていないのと同じと理解するべきです。
耐震等級3相当を信じて購入した後、増改築やリフォームをする際に「実は正式な評価を受けていない」と気づくケースもあります。この場合、将来的に性能評価書の取得や耐震診断が必要となり、追加費用が発生する恐れがあります。
正式な耐震等級3を確認する方法
中古住宅で正式な耐震等級3を確認するには、以下の書類が揃っているかを必ずチェックする必要があります。これらの書類は、耐震等級3の裏付けとして重要な役割を果たします。
住宅性能評価書(新築時)
住宅性能表示制度に基づき、第三者機関が発行した正式な評価書です。評価の有効性や対象となる住宅名義の確認も重要です。
設計住宅性能評価書
設計段階での評価結果を示す書類です。施工中に別途「建設住宅性能評価書」が発行されているかも確認しましょう。
建築確認済証および確認申請図書
建物が適法に建築された証明として重要です。設計時の耐震基準もこの書類から確認できます。
構造計算書(必要な場合)
構造計算によって耐震等級3を証明している場合、この書類も裏付け資料として役立ちます。
これらの書類がすべて揃い、内容が適切であることを確認することで、正式な耐震等級3であるかを判断できます。書類が一部でも不足している場合は、不動産仲介会社や売主、専門家に補完を依頼し、曖昧な状態で契約を進めないようにしましょう。
耐震等級3の確認は、書類の有無だけでなく中身を精査する姿勢が求められます。正しい情報を手に入れることで、家族の安全と資産価値を守る住まい選びが実現します。
>>「耐震等級3は過剰」という声の真実|住宅選びに失敗しない知識と判断方法
>>耐震等級3の家は資産価値が落ちない?売却・賃貸で有利になる理由を徹底解説
中古住宅購入時に必ず確認すべき証明書と書類

中古住宅で「耐震等級3」の物件を選ぶ際には、書類確認が非常に重要です。耐震等級3を名乗る住宅であっても、証明書類がなければその性能を裏付けることはできません。耐震等級3の裏付けは、書類の有無と内容確認がすべての基本です。
書類の確認を怠ると、後から「思っていた性能と違った」と気づいても取り返しがつきません。ここでは、購入時に必ず確認すべき耐震関連の書類を解説します。
住宅性能評価書の有効性と確認方法
住宅性能評価書は、住宅性能表示制度に基づき第三者機関が発行する公的な証明書です。新築時に取得されることが一般的ですが、中古住宅の場合、この評価書がそのまま有効であるとは限りません。
住宅性能評価書には「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」の2種類が存在します。中古住宅で耐震等級3を確認する際には、両方が揃っているか、または建設住宅性能評価書があるかを必ず確認しましょう。設計段階だけの評価では、実際の施工状況が評価されていない可能性があります。
評価書が残っていても名義変更されていない、紛失しているなどのケースも見られます。その場合、再発行は原則としてできないため、評価書の有無を最初の段階で確認することが重要です。
設計住宅性能評価書
設計図面の段階での性能評価を証明する書類です。耐震等級3で設計された証拠として使えますが、施工中の検査を証明するものではありません。
建設住宅性能評価書
実際の施工を含めた性能評価を証明する書類です。中古住宅で耐震等級3を証明する際には、こちらの有無が重要となります。
これらの書類が揃っているか、内容に不備がないかを確認することが、耐震等級3を保証する最も確実な方法です。書類がない場合は、他の方法で耐震性を確認する必要があります。
耐震診断書の重要性
中古住宅では、耐震診断書を取得しているケースもあります。耐震診断書は、既存住宅の耐震性を調査・評価した結果をまとめた書類です。ただし、耐震診断書と耐震等級3の評価は別物であることに注意が必要です。
耐震診断は、建築基準法に基づく現行基準を満たしているかを確認するための調査ですが、耐震等級の評価を行う制度とは異なります。そのため、診断書に「耐震性に問題なし」と記載されていても、正式な耐震等級3の証明とはなりません。
簡易耐震診断書
診断項目が限られた簡易な診断結果をまとめた書類です。基本的な耐震性の確認には役立ちますが、詳細な性能評価には不十分です。
精密耐震診断書
建物の詳細な構造データを基にした診断結果をまとめた書類です。補強の必要性や耐震改修の方向性を具体的に知る際に役立ちます。
耐震診断書は、あくまで現状の耐震性を把握するための書類であり、評価書の代替にはなりません。購入時には、診断内容や診断方法の詳細も含めて確認し、必要に応じて専門家の意見を求めることが大切です。
診断書は性能を保証する証明ではなく、状態を把握するための資料であることを理解しましょう。
購入判断の材料として活用しつつ、正式な評価書との違いをしっかり認識しておくことが安全な物件選びにつながります。
中古住宅の耐震基準の違い:新基準と旧基準の影響

中古住宅を購入する際、建物が建てられた時期によって耐震性能に大きな差が生じます。これは日本の建築基準法が複数回にわたり改正され、耐震基準が強化されてきたからです。建築年=適用される耐震基準」と理解し、基準の違いを把握することが購入の第一歩です。
住宅の耐震性は、建築時の基準に従って決まります。築年数だけではなく、建築確認申請がいつ行われたかも重要であり、購入前に必ず確認すべき項目です。
新耐震基準、旧耐震基準、現行基準の違い
日本の耐震基準は1981年に大きな改正が行われ、それ以前の「旧耐震基準」と区別されます。新耐震基準では、震度6強程度の大地震でも倒壊しない強度が求められました。一方、旧耐震基準では震度5程度までの地震に耐えられる設計とされ、現在では十分とは言えません。
さらに2000年には、構造計算方法や耐力壁の配置など、設計の細部にわたる基準強化が行われました。2000年以降の建物は、よりバランスの取れた耐震性能が確保されやすくなっています。
旧耐震基準(1981年以前)
震度5程度の地震に耐える設計。現行基準に比べ耐震性が低い。
新耐震基準(1981年以降)
震度6強の地震に耐える設計。大地震でも倒壊しない性能が目標。
現行基準(2000年改正以降)
構造計算や壁配置の基準が強化され、より安全性が高い設計。
このように、1981年と2000年が耐震基準の大きな分岐点となっています。購入検討中の住宅がどの基準で建てられているかを知ることで、実際の耐震性を見極める重要な判断材料となります。
旧耐震基準で建てられた住宅は、耐震診断や補強工事が必要となる場合があります。購入後の改修コストを含めた資金計画が必要になるため、基準の違いを知った上で物件を選ぶことが重要です。
基準の違いは住宅の安全性だけでなく、将来的な補強コストにも影響します。
購入後の不安や追加負担を防ぐためにも、建築年だけで判断せず、適用基準まで確認しましょう。
中古住宅の耐震等級3を見つけやすい物件の傾向

耐震等級3の中古住宅を探すには、どのような物件が該当しやすいのかを知ることが大切です。供給数が限られている市場の中で、効率的に探すためには、物件のタイプや建築背景に着目することが重要です。耐震等級3の取得実績がある物件の特徴を理解することが、理想の物件探しの近道です。
以下の物件タイプは、耐震等級3を取得している可能性が比較的高い傾向があります。
分譲住宅と注文住宅、ハウスメーカー物件の違い
分譲住宅、注文住宅、ハウスメーカー物件では、耐震等級3の取得状況に違いがあります。それぞれの特徴を理解することで、どの物件が狙い目なのかを見極めることができます。
分譲住宅
一定の基準で一括開発されるため、全棟で耐震等級3を取得している場合があります。ただし、評価書の有無や等級の違いは棟ごとに異なることがあるため、個別確認が必要です。
注文住宅
建築主の要望により仕様が異なるため、耐震等級3の取得は設計時の判断に左右されます。評価書付きの場合は取得済みであることが多いですが、書類の確認は必須です。
ハウスメーカー物件
大手ハウスメーカーでは、標準仕様で耐震等級3を採用しているケースがあります。長期優良住宅仕様の場合は、耐震等級3が条件となっている場合が多く、信頼性が高い傾向があります。
このように、ハウスメーカー物件や性能評価書付きの分譲住宅は、耐震等級3の中古住宅を見つけやすい選択肢といえます。一方、個人設計の注文住宅は、評価書の有無や等級が不明確な場合があるため、書類確認が重要となります。
購入を検討する際には、物件種別だけでなく「評価書の有無」「建築時の基準」「ハウスメーカーの仕様」をセットで確認する意識が求められます。物件の見極めは、書類確認と背景理解の両方が必要です。
このポイントを押さえることで、限られた市場の中でも安全性と安心を備えた住宅選びが実現します。
>>【耐震等級3は完璧じゃない?】ハザードマップで見抜く「本当に安全な土地」の選び方
購入前に依頼可能な専門家の活用方法

中古住宅で「耐震等級3」の物件を選ぶ際、専門家の力を借りることは非常に有効です。売主や仲介会社からの情報だけでは確認しきれない部分も、専門家による第三者視点でチェックしてもらうことで、購入後の不安を減らせます。購入前の専門家活用が、見落としを防ぎ後悔しない選択を支えます。
>>【耐震等級比較ガイド】等級1・2・3の違いと、あなたに合った選び方
ここでは、中古住宅購入時に依頼可能な専門家と、その活用方法について解説します。
ホームインスペクターを活用する理由
ホームインスペクター(住宅診断士)は、住宅の現況を診断する専門家です。耐震性、雨漏り、基礎の劣化など、目に見えない部分も含めて住宅の状態を評価し、購入判断に役立つ情報を提供します。
見た目では分からない劣化の指摘
専門機器や知識を用いて、内部構造や設備の状態を確認し、素人では気づきにくい問題点を報告します。
診断報告書を基にリフォーム費用を試算可能
診断結果をもとに、必要な補修や耐震補強の費用感を把握でき、予算計画に活かせます。
ホームインスペクターの診断は、中古住宅購入時のリスク回避に直結します。耐震性のチェックについても、目視調査の範囲で指摘可能な項目をカバーしてくれるため、評価書や診断書が不十分な物件でも一助となります。
建築士による耐震性のチェック
詳しい耐震性の確認を希望する場合、建築士に依頼する方法があります。建築士による耐震診断は、構造計算や設計図面の確認、建物の構造的な弱点を見つけ出すことに優れています。
構造図面を基に耐震性を評価
建築士は構造図面や施工記録をもとに、建物の耐震性能を理論的に評価します。図面が残っていない場合も現地調査による補足が可能です。
必要に応じて精密耐震診断も依頼可能
精密診断では、壁の配置や接合部、基礎の状態まで詳細に調査し、補強が必要な箇所を特定できます。
建築士への依頼は、ホームインスペクターより費用が高くなる傾向にありますが、精密な耐震診断や補強計画まで見据える場合には有効です。旧耐震基準や書類の不備がある物件では、建築士の診断が安心材料となります。
専門家の活用は、見た目や表面的な情報だけでは判断できないリスクを減らす鍵です。購入前に必要な調査を終えておくことで、将来のトラブルや追加費用を避け、安心して暮らせる住宅選びが実現します。
>>「耐震等級3」が家族の未来を守る。地震後も“暮らせる家”の選び方とは
中古住宅で後悔しない!耐震等級3を見極める購入術

中古住宅で「耐震等級3」の物件を選ぶには、単に物件情報を確認するだけでは不十分です。評価書の有無、耐震基準の違い、さらには「耐震等級3相当」という表現の意味まで正しく理解することが求められます。正しい知識と確認が、安全な住まい選びにつながります。
耐震等級3の中古住宅は供給数が限られており、探すこと自体が難しい場合もあります。しかし、評価書付きの分譲住宅や大手ハウスメーカーの物件など、比較的見つけやすい傾向のある物件タイプを狙うことで、効率的に探せます。
購入前には、住宅性能評価書や耐震診断書など、必要な書類を必ず確認しましょう。評価書がない物件の場合、耐震診断を依頼したり、専門家の意見を取り入れたりするなど、追加の確認手段を講じることが大切です。
ホームインスペクターや建築士など、専門家の力を借りることで、見落としや情報不足によるリスクを減らせます。専門家の診断は費用がかかるものの、将来的な補強費用や修繕リスクを回避できる大きな価値があります。
書類確認」「基準理解」「専門家活用」の3つを意識することで、後悔のない中古住宅選びが実現します。
>>【命を守る家】子どもも高齢者も安心「耐震等級3」という最強の備え
大切な家族と資産を守るために、確実で納得できる選択を行いましょう。耐震等級3の中古住宅は、情報と行動力を持つことで、必ず見つけ出せる住宅です。
憧れの大手メーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれる

住宅展示場や完成見学会にいくのは時間もかかるし大変…
そんなときに便利なのが「タウンライフ家づくり」です。
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
気になるメーカーや工務店を選び、希望の間取りや予算を入力するだけ。「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる!
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。

「タウンライフ家づくり」はこんな方におすすめ
- あなただけの間取りと見積もりを無料で手に入れ比較したい
- 営業されるのが嫌、苦手
- 自宅でじっくり信頼できるハウスメーカーを選びたい
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ




