この記事にはプロモーション・広告が含まれています
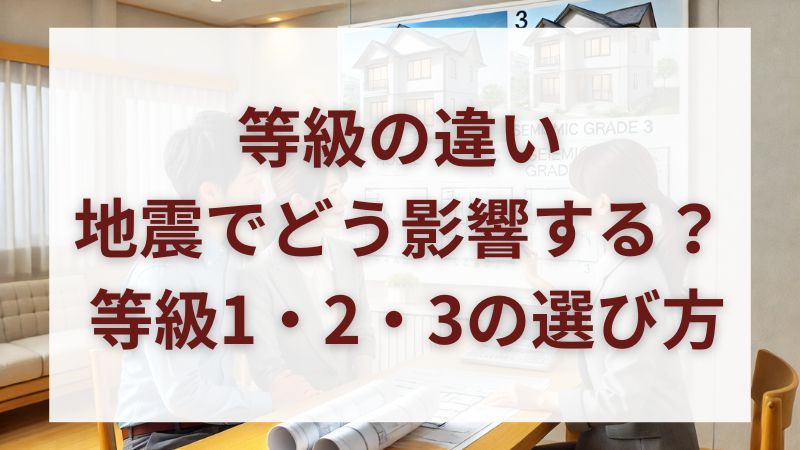
日本は世界有数の地震大国であり、住宅の耐震性能は暮らしの安心に直結する重要な要素です。新築住宅やリフォームを検討する際、「耐震等級」という言葉を目にする機会が増えてきました。
しかし、耐震等級1・2・3といった区分は、数字の大小だけでは判断が難しく、実際にどれが自分にとって最適なのか判断に迷う人も多いのが現状です。
耐震等級は単なる「強さの違い」ではなく、住まいの安全性・将来設計・経済性に深く関わる選択です。
この記事では、耐震等級1・2・3の違いを明確に比較し、数値や制度に基づいた根拠ある情報を提供します。住宅購入やリフォームの検討段階で「後悔しない選択」をするために、等級選びの判断基準を整理していきましょう。
耐震等級とは?基礎から理解する

耐震等級を正しく理解することは、安心・安全な住まいを選ぶうえで欠かせない第一歩です。このセクションでは、耐震等級の意味や制度上の位置づけ、1・2・3という等級の具体的な違いについて、基礎からわかりやすく解説します。
「等級の数字が何を示しているのか」「なぜ等級が必要なのか」を明確にすることで、家づくりの判断力がぐっと高まります。
耐震等級の定義と位置づけ
耐震等級とは、建物がどれだけの地震に耐えられるかを示す指標であり、「住宅の耐震性能」を数値化したものです。これは、国が定めた「住宅性能表示制度」の中で明確に基準化されており、建築基準法と連動して設計・評価されます。
建築基準法では「震度6強〜7程度の大地震でも倒壊しない」水準が定められており、この最低ラインが「耐震等級1」に相当します。
耐震等級は、以下の3段階に分類されます。
| 等級 | 耐震性能の概要 |
| 耐震等級1 | 建築基準法の最低基準。震度6強〜7でも倒壊しないレベル。 |
| 耐震等級2 | 等級1の1.25倍の耐震性。学校・病院などの避難施設に推奨。 |
| 耐震等級3 | 等級1の1.5倍の耐震性。消防署・警察署など重要施設と同等。 |
等級が1段階上がるごとに、建物の強度は「25%ずつ」増します。
この数値差は一見わずかに思えるかもしれませんが、地震の破壊力は指数的に増幅するため、わずかな違いが生死を分けることもあります。
耐震等級と構造設計の関係
耐震等級は「どのように建物を設計するか」にも大きな影響を与えます。ここでは、主に使われる2つの構造計算方法を整理しておきます。
壁量計算(簡易的な方法)
主に木造住宅で用いられる計算手法。耐震等級1〜2を取得する際に使われることが多く、設計の自由度が高い一方で、構造の安全性確認には限界がある。
許容応力度計算(詳細な構造解析)
耐震等級3を取得するために必要な方法。各部材にかかる力を詳細に計算し、建物の耐久性・剛性を数値で検証する。設計の精度が高まる一方、設計費用や作業工程が増える。
| 耐震等級 | 主な計算方法 | 設計の自由度 | 審査の厳しさ |
| 等級1 | 壁量計算 | 高い | 緩やか |
| 等級2 | 壁量計算(場合により構造計算) | 中程度 | 中程度 |
| 等級3 | 許容応力度計算 | 低い | 厳格 |
等級が上がるほど、建物の安全性に対する検証精度が高まり、信頼性の高い住宅となります。
しかしその分、設計・建築コストが増えるため、家づくりの目的や優先事項に応じて等級を選ぶ視点が重要となるのです。
耐震等級1・2・3を徹底比較:強度・コスト・暮らしへの影響

耐震等級の数字だけを見て「強いから安心」と判断するのは危険です。各等級は構造の強度だけでなく、地震後の生活継続性、保険・税制への影響、そして建築コストや資産価値にまで波及する重要な指標です。ここでは、等級ごとの実質的な違いを整理し、どの視点で比較・判断すべきかを具体的に解説します。
>>耐震等級3の家は資産価値が落ちない?売却・賃貸で有利になる理由を徹底解説
地震時の安全性と居住継続性
耐震等級ごとの「倒壊リスク」や「住み続けられるかどうか」は、単に構造体の強さだけでなく、耐震設計の方針や使われる素材・施工精度にも左右されます。
>>耐震等級3でも倒壊リスク?見落としがちな落とし穴と安全に守る対策
>>耐震等級3の家は“信頼できる施工会社”で!悪質業者に騙されない見極め術
| 耐震等級 | 地震発生時の安全性 | 地震後の居住継続性 |
| 等級1 | 倒壊は免れるが、修繕が必要になる可能性が高い | 一時的な避難や補修が前提になることが多い |
| 等級2 | 中程度の損傷を想定。ある程度の修繕で再居住可能 | 軽微な修繕で生活可能なケースが多い |
| 等級3 | 構造被害が最小限に抑えられる可能性が高い | ライフラインが機能していれば継続的な居住が可能なことも |
耐震等級3は「命を守る」だけでなく「生活を守る」性能でもある点が大きな特長です。
共働き家庭や子育て世帯では、地震後も住み続けられるかどうかは重要な判断材料となります。高等級ほど修繕費の抑制や避難リスクの軽減にもつながるため、長期的な視点でのコストパフォーマンスも見逃せません。
>>【命を守る家】子どもも高齢者も安心「耐震等級3」という最強の備え
保険料・住宅ローン減税・税制優遇の違い
耐震等級が高いほど、住宅の「安全性」だけでなく、「経済的なメリット」も大きくなります。以下は主要な制度と耐震等級との関係をまとめた一覧表です。
| 制度名 | 耐震等級1 | 耐震等級2 | 耐震等級3 |
| 地震保険料の割引 | なし | 最大30%割引 | 最大50%割引 |
| 住宅ローン減税 | 条件付き可 | 優遇あり | 最大優遇あり |
| 固定資産税の軽減 | 原則対象外 | 条件付き対象 | 条件付き対象 |
地震保険の割引率は等級によって大きく異なり、保険料の節約だけでなく、地震リスクに対する備えとしての「制度的な信頼」も得られます。
住宅ローン減税や固定資産税の軽減措置も、耐震等級を取得しているかどうかで明暗が分かれるため、住宅性能評価書の取得が非常に重要です。
取得手続きや審査にコストはかかりますが、長期的に見れば制度の恩恵による経済効果は無視できません。耐震等級3は、多くの制度において「最も優遇される基準」となっています。
建築コストと資産価値への影響
耐震等級が高くなるほど、構造部材の強化や設計・審査手続きが必要となり、建築コストが上昇する傾向があります。しかし、それは単なる出費ではなく、将来的な資産価値や売却時の評価にも影響する投資的要素でもあります。
| 耐震等級 | 建築コストの傾向 | 資産価値への影響 |
| 等級1 | 最も低コスト。最低限の耐震基準を満たす | 資産価値としての評価は限定的 |
| 等級2 | 中程度のコスト増加。構造部材が強化される | 一般的な住宅よりも耐震性が評価されやすい |
| 等級3 | 最大15〜20%のコスト増が見込まれることも | 高耐震性が売却時の大きなアピールポイントに |
等級3の住宅は、資産としての信頼性が高く、買い手に安心感を与える武器になります。
耐震性能が明確に等級として示されていれば、中古住宅市場においても価格競争力を持ちやすくなります。地震に対する意識が高い都市部では、「耐震等級3の住宅」であることが物件選びの決め手になるケースも多くあります。
>>【耐震等級3の中古住宅】相当とは違う?正しい見極め方と必ず確認すべき書類
耐震補強の追加工事が不要であることは、中長期的なリフォームコストの抑制にもつながり、住宅のトータルコストを下げる効果もあります。目先の建築費だけでなく、将来的な資産価値・維持コストを総合的に考える視点が重要です。
ライフスタイルで変わる“最適な耐震等級”の選び方

耐震等級の選択は「数値が高ければ安心」という単純な話ではありません。家族構成や働き方、老後の住まい方など、ライフスタイルによって最適な等級は変わります。自分たちの生活に合った等級を選ぶことで、日常の安心感と地震後の生活継続性の両方を高めることができます。
ライフスタイル別・等級選びの判断基準を整理しよう
耐震等級の選び方に迷ったら、以下のような判断基準で整理すると、自分に合った等級が見えてきます。
家族構成
小さな子どもがいる、または高齢の家族が同居しているかどうかで安全性の基準が変わる。
共働きか専業世帯か
共働き世帯は地震後の生活インフラや通勤への影響も考慮する必要がある。
住宅の立地
活断層の近くや沿岸部など、地震リスクが高い地域では等級3が推奨されるケースが多い。
長期居住か将来的に売却か
長く住む家なら耐震性能を重視すべきだが、売却を想定するなら資産価値の観点も重要。
将来のライフステージの変化
子どもが独立した後や老後を見据えた住まいとしての耐震性の確保も忘れてはならない。
等級選びは「今の自分たち」に加えて「10年後、20年後の暮らし」も見越して考えることが大切です。
>>【南海トラフ・首都直下地震に備える】高リスク地域にこそ「耐震等級3」の家を建てる理由
【比較表】ライフステージごとの耐震等級の優先ポイント
| ライフステージ | 推奨等級 | 理由・ポイント |
| 子育て世帯 | 等級2〜3 | 子どもの安全確保、地震後も住み続けられる安心感 |
| 共働き家庭 | 等級3 | 地震後も通勤・保育を継続できる住まいが必要 |
| シニア世代 | 等級2〜3 | 避難困難リスクを減らし、住宅内での安全性を確保 |
| 多世帯住宅 | 等級3 | 各世帯の安心感と共有スペースの安全確保が求められる |
表の内容は一例ですが、どの等級が最適かは「暮らしの中で何を優先したいか」によって変わります。 安全性だけでなく、コストや設計の自由度とのバランスをとるためにも、自分たちにとっての「優先事項」を明確にしておくことが賢明です。
>>【間取り制限は誤解?】耐震等級3でも叶う“自由設計”の家づくり完全ガイド
子育て世帯にとっての安心とは?守りたい暮らしの視点で考える
子育て世帯にとって住まいとは、家族の「日常」と「将来」の両方を支える存在です。小さな子どもがいる家庭では、地震の際に安全を確保しつつ、混乱の中でもなるべく普段の生活を維持できる環境が求められます。
子どもは自分で身を守れないからこそ、住まいが確実に命を守る必要があります。
耐震等級3を選ぶことにより、地震発生時の倒壊リスクを最小限に抑えることができるだけでなく、建物内部の被害を軽減することで、避難所ではなく「自宅での生活継続」を目指す選択が可能になります。
次のような点も子育て世帯には重要な判断基準となります。
避難不要な暮らし
自宅が安全であれば、子どもを連れての避難のストレスや健康リスクを減らせる。
物理的な安全確保
建物の倒壊だけでなく、家具の転倒リスクを抑えるための構造補強がしやすくなる。
精神的な安定
親が安心して暮らせることが、子どもにも大きな安心感を与える。
子育ては長期戦であり、成長とともに生活スタイルも変化していきます。そのため、住宅選びは「一時的な安さ」よりも「長く安心できる環境」であることが何よりも重要です。
家族を守るという視点から見ると、耐震等級3の住宅は最も信頼できる選択肢といえます。 家づくりの段階で将来を見据えた耐震性を確保しておくことは、後悔しない家選びの大きな一歩です。
>>【命を守る家】子どもも高齢者も安心「耐震等級3」という最強の備え
共働き夫婦のリスクマネジメント:地震後も通勤・生活を止めない工夫
共働き世帯にとって、災害時の最大のリスクは「生活の停止」です。地震で家が使えなくなれば、仕事も育児も一時中断せざるを得ず、家族全体の生活に大きな支障が出ます。だからこそ、日常の継続を守るために耐震性の高い住宅を選ぶことが必要です。
耐震等級3の住宅は、地震後も「職場に通う」「保育園に預ける」「日常生活を維持する」可能性を広げます。
共働き世帯が住宅の耐震性を高めるメリットには、以下のような具体的な視点があります。
インフラの停止に備える
上下水道や電気の途絶が想定される中、建物自体が機能すれば、仮設住宅や避難所に頼る必要が減る。
通勤・通学ルートの確保
建物の安全が確保されていれば、自家用車や自転車での移動も可能となり、復旧までの生活維持が現実的に。
家事・育児の継続性
家が使えることは、食事・入浴・育児といった日常業務を自宅で完結できる環境を保つことにつながる。
共働き家庭は平日は家に不在がちです。そのため、地震が起きた際に家に誰もいない時間帯に被災する可能性もあります。誰もいない時間帯でも住宅が倒壊しない耐震性を確保することは、家族の命と財産を守る最後の砦になります。
リモートワークの普及が進む中で、自宅が「職場」となる人も増えています。そうした働き方においては、地震後でも「安全に働ける住まい」であることが新しい選択基準になっています。 家だけでなく仕事や子どもの生活リズムを守るためにも、耐震等級の選択は重要な意思決定です。
シニア世代や老後を見据える選択肢:建て替えか、住み継ぐか
シニア世代にとって、住まいの耐震性は「今」の安心と「これから」の備えを同時に支える重要なテーマです。高齢になるほど、避難の難しさや医療的なケアの必要性が増し、災害時の移動や避難所生活は現実的ではなくなります。
地震が起きても「その場で安全に過ごせる家」が老後の住まいにとって最大の安心材料です。
築年数が経過した住宅に住んでいる場合、耐震補強で耐震等級を向上させることも可能ですが、基礎や構造体の劣化によっては建て替えを検討した方が安全性と将来性を確保しやすいケースもあります。
以下は、老後の住まいにおける耐震等級選びの比較ポイントです。
| 視点 | 耐震等級1 | 耐震等級2 | 耐震等級3 |
| 安全性 | 最低限の倒壊防止。補修前提の居住 | 中程度の安心感。災害時に不安が残る | 最も高い安全性と居住継続性 |
| バリアフリー対応 | 改修次第で対応可 | 比較的柔軟に設計可能 | 設計制限ありも高性能と両立可能 |
| 建て替えの判断 | 補強で対応可能な場合もある | 状況により選択肢 | 新築時に計画的に取得がおすすめ |
老後の安心を考える際は、建物の性能だけでなく、以下のような要素も含めて判断するのが理想的です。
階段の段差や出入り口の安全性
耐震性だけでなく、転倒リスクを減らす住環境の整備が求められる。
介護を見据えた設計
将来的に介護が必要になった場合にも、自宅で過ごせる設計が望ましい。
地域とのつながり
地震発生後の孤立を避けるため、地域コミュニティや医療機関へのアクセスも重要。
高齢期の住まいにおける耐震性の確保は、「命を守る」ことに加えて「住み慣れた場所で最期まで過ごすための準備」でもあります。建て替えか補強かという選択は、耐震等級という基準をベースに、将来のライフスタイルや健康状態を踏まえて慎重に検討することが重要です。
二世帯・三世代住宅で考える耐震性の落とし穴
二世帯・三世代住宅では、世帯ごとの生活スタイルやニーズが異なるため、住宅に求められる性能も多様化します。耐震性についても、一世帯住宅と同じ基準で考えるのでは不十分であり、共有スペースや接続部分の安全性が「家族全体の命を守る鍵」となります。
注意すべきなのは、構造が複雑化しやすい点です。上下階の居住空間が分かれていたり、玄関や水回りが2セットあるなど、通常よりも建物の荷重バランスが不均衡になりやすく、耐震設計には高度な技術と検証が求められます。
以下は、多世帯住宅における耐震設計での主な注意点です。
構造の一体性の確保
増築部分や間取りの違いで強度のムラが生じると、地震時に建物がねじれて損傷するリスクがある。
生活空間の分離と避難経路
各世帯が独立していても、緊急時に安全に避難できる動線が設計されているかが重要。
共有スペースの強度確保
リビングや廊下など複数世帯が集まる場所ほど、最も高い耐震性能を持たせる必要がある。
| 項目 | 一世帯住宅 | 二世帯・三世代住宅 |
| 間取りの複雑性 | 単純 | 複雑(増改築が多い) |
| 強度バランス | 保ちやすい | 崩れやすい(接続部に注意) |
| 設計・施工難易度 | 一般的 | 高い(構造計算必須) |
家族の人数が多いほど、「誰かが家にいる確率」も高くなり、地震発生時に在宅しているリスクも上昇します。
そのため、単純に「等級2で十分」とせず、構造上のリスクや共有部分の安全性を重視し、耐震等級3の取得を前提に設計することが望ましいケースも多く見られます。多世帯住宅こそ、「家全体の構造をどう守るか」が等級以上に問われるのです。
地震リスクを地域特性から読み解く:立地で変わる等級の考え方

耐震等級を考える際、建物そのものの性能だけでなく「どの地域に建てるか」という立地条件も重要な判断要素となります。地盤の強さや地震の発生リスクは地域によって大きく異なり、同じ等級でも効果の感じ方が変わることがあります。地形や災害履歴、ハザードマップの活用など、地域特性を読み解いたうえで耐震等級をどう選ぶかが、安全で賢い住宅選びに直結します。
>>【耐震等級3は完璧じゃない?】ハザードマップで見抜く「本当に安全な土地」の選び方
立地条件別・耐震等級の選び方を整理しておこう
活断層が多い地域や液状化の可能性がある地盤では、耐震性だけでなく地盤補強も含めた対策が必要です。逆に地盤が安定していても、近年では都市部特有の「共振」による揺れの増幅も懸念されます。
| 立地条件 | リスク要素 | 推奨される耐震等級 |
| 活断層付近 | 強い地震が発生しやすい | 等級3推奨 |
| 沿岸部 | 津波・液状化のリスク | 等級3+地盤補強 |
| 山間部 | 土砂災害・孤立リスク | 等級2〜3+避難計画 |
| 都市部 | 共振による揺れの増幅 | 等級3(高層住宅含む) |
| 郊外・内陸 | 地盤による差が大きい | 地盤調査を前提に判断 |
地震は「どこでも起きる」災害ですが、被害の出方は立地で大きく異なります。
地域のリスク特性に応じて、耐震等級とあわせて地盤調査や地形特性への理解を深めることが、安全な家づくりの出発点となります。等級だけに目を向けず、「どこに建てるか」を意識することで、住宅の防災力は飛躍的に高まります。
活断層が近い地域での住まい選びに必要なこと
活断層の近くに位置する地域では、大規模地震の発生リスクが他地域より高くなります。プレート型ではなく直下型地震が発生する可能性があるため、震源が近く、揺れの強さや被害の規模も甚大になりやすいのが特徴です。
このような地域では、耐震等級の選び方が住宅の生死を分ける要因になり得ます。
等級1や等級2では「倒壊を免れるレベル」だが、居住継続は難しいケースが多くなります。
活断層リスクがあるエリアに家を建てる場合、以下のような対策が有効です。
耐震等級3の取得
地震の揺れが強くなることを前提とした構造設計が必要。等級3であれば震度7クラスにも耐えうる設計が基本となる。
許容応力度計算による設計
構造の強度だけでなく、各部材への応力を数値で検証。地震の瞬間的な負荷にも対応できる。
基礎構造の強化
ベタ基礎や杭基礎を用いて地盤との一体性を高め、建物の沈下や崩壊を防止する。
| 検討項目 | 推奨内容 |
| 耐震等級 | 等級3必須 |
| 設計方法 | 許容応力度計算 |
| 地盤対策 | 地盤調査+補強工事 |
| 建築素材 | 高耐力壁、制震ダンパーなど |
活断層地帯においては、行政の地震防災マップや地震履歴データの活用も重要です。建物の性能だけでなく、土地そのものの特性を理解することが、地震に強い家づくりの第一歩です。
住まいの安全性は、建物と立地の“二重構造”で守るべきもの。どれだけ堅牢な家を建てても、地盤や断層の脆弱さを無視しては本末転倒です。活断層の近くに暮らすならば、等級3を「当たり前」として考える姿勢が、真に安心できる選択と言えるでしょう。
沿岸部・山間部の住まいは“耐震”だけで足りるのか
津波や土砂災害といった複合災害が想定される地域では、耐震性だけでは住宅の安全を完全には担保できません。建物が無事でも、周囲の地形や地盤の影響で住環境自体が機能不全になる可能性があるため、総合的なリスク対策が不可欠です。
沿岸部では、地震直後に津波の危険があるため、耐震性の確保に加えて「高台への避難動線」や「建物のかさ上げ」などが必要です。一方、山間部では急傾斜地からの土砂崩れ、落石、地滑りといった地盤災害のリスクが存在し、崖条例など地域ごとの規制も住宅設計に大きく影響します。
それぞれのエリアで必要となる対策を表に整理します。
| 地域 | 主なリスク | 耐震以外に必要な対策 |
| 沿岸部 | 津波、液状化 | 高床建築、避難ルートの確保、防潮堤との位置関係の確認 |
| 山間部 | 土砂崩れ、孤立 | 盛土・擁壁の整備、退避路確保、土砂災害特別警戒区域の確認 |
これらの地域で求められるのは、「耐震等級をベースに、地域固有のリスクに対応した設計方針を加える」姿勢です。等級3の家であっても津波浸水エリアに建っていれば、命を守るのは難しくなります。
立地特性と災害リスクを的確に読み解き、必要ならば防災・減災のハード・ソフトを組み合わせることで、初めて「本当に強い家」が完成します。
災害の種類が多様化する今、耐震性能だけに安心を預けるのではなく、地域の特性を読み取った「災害対応力のある住まい」が求められています。設計段階から「地震+α」の視点を持つことが、後悔しない家づくりにつながります。
都市部と郊外で異なる「揺れやすさ」
都市部と郊外では、同じ震度の地震が発生しても揺れ方や建物への影響が大きく異なることがあります。その主な要因は「地盤の特性」と「建物密集度」です。
都市部は地盤が軟弱な低地に開発されたケースが多く、地震の揺れが増幅されやすい傾向にあります。
一方で、郊外や山裾に広がる住宅地は固い地盤に立地していることが多いため、揺れの影響を受けにくい場合もあります。ただし、造成地や盛土エリアなどでは別のリスクが存在します。
以下は都市部・郊外の比較をまとめた表です。
| 地域分類 | 地盤特性 | 揺れの傾向 | 建物密度 | 耐震等級の推奨 |
| 都市部 | 軟弱地盤(埋立地など) | 揺れが増幅しやすい | 高密集。倒壊連鎖の懸念あり | 等級3推奨 |
| 郊外 | 固い地盤が多いが造成地も存在 | 局所的に揺れに強い | 比較的ゆとりあり | 等級2〜3(造成地は要検討) |
都市部では、高層マンションや密集した住宅が隣接しているケースが多く、建物同士の「共振」や「接触倒壊」など二次被害のリスクも無視できません。
郊外の住宅では、ゆとりのある敷地と構造上の自由度を活かし、耐震+制震・免震といった複合的な構造を取り入れやすいメリットがあります。とはいえ、近年は郊外の宅地開発も盛んで、造成地や谷底低地など地盤が不安定な場所も増えています。
立地の安全性を過信せず、「自分の敷地がどういう地盤の上にあるか」を知ることが、耐震等級の判断材料として欠かせません。
ハウスメーカーや建築士の説明に任せきりにせず、自ら地盤調査やハザードマップを確認することが、安心の住まいづくりへの第一歩です。等級だけでなく、地盤の「揺れやすさ」に応じた対応を選ぶことが、家族を守る備えになります。
ハザードマップを使いこなす:地震以外のリスクも要チェック
耐震等級は建物の「地震に対する強さ」を示すものですが、実際の災害リスクはそれだけでは語れません。洪水・土砂災害・液状化といった“複合災害”の可能性を見落とすと、安全な家づくりは成立しません。
そこで活用したいのが自治体が公開している「ハザードマップ」です。これは地震や津波に限らず、浸水・崖崩れ・火山活動など、地域特有の災害リスクを視覚的に確認できるツールです。
ハザードマップで確認すべき主な項目は以下の通りです。
浸水想定区域
河川の氾濫によって水がどこまで及ぶかを予測した範囲。低地や旧河川流域は要注意。
土砂災害警戒区域
崖や斜面に面した地域で、土砂崩れや地すべりのリスクがあるエリア。
液状化の可能性
海沿いや埋立地で、地震時に地盤が液体状になり建物が傾く恐れがある地帯。
活断層・地震断層帯
大地震の震源となる可能性がある断層が通っている場所。
| リスク種別 | チェックポイント | 推奨対応策 |
| 洪水 | 浸水想定区域内か | 建物のかさ上げ、排水計画の強化 |
| 土砂災害 | 警戒区域内か | 擁壁・斜面保護、避難計画の策定 |
| 液状化 | 旧河川・埋立地か | 地盤改良、杭基礎などの地盤対策 |
| 地震断層 | 活断層の近接 | 耐震等級3、構造補強を強化 |
ハザードマップは各自治体のホームページや「重ねるハザードマップ」(国土交通省)で簡単に確認できます。土地購入や建築計画の初期段階で調査しておくと、後から「想定外」を防ぐことができます。
耐震等級を選ぶだけで安心してしまうのではなく、地域の災害リスクを“俯瞰”して住宅性能と組み合わせることで、真に強い住まいが実現します。
家の安全は「等級×立地×災害対策」の三位一体で考える必要があるのです。ハザードマップは、そのための最も手軽で信頼できるツールとして活用すべき必須情報といえるでしょう。
耐震等級の取得と確認方法

耐震等級は建物の地震に対する強さを数値で示す指標ですが、ただ設計通りに建てるだけでは等級の「認定」は得られません。正式な等級の取得には、設計段階から明確な計算と申請、第三者による評価が必要です。既存住宅についても、後から診断や補強によって等級相当の性能を把握・向上させることができます。
耐震等級の取得は等級によって難易度が異なる
耐震等級1:最低基準だが、正式な認定には申請が必要
建築基準法に適合すれば耐震等級1相当の性能は確保できますが、性能表示制度に基づく「正式な等級1の認定」を得るには、住宅性能評価機関に申請し、評価書を取得する必要があります。
- 計算方法:壁量計算
- 設計の自由度:高め
- 主な対象:一般住宅、建売住宅など
等級1はコストや設計自由度を優先した住宅に多く採用されますが、地震後の居住継続性はあまり高くないため、災害への備えという点では物足りなさがあります。
耐震等級2:公共施設並みの強度、審査のハードルも中程度
等級1に比べて1.25倍の耐震強度が求められ、学校や病院などの避難施設にも採用される水準です。木造住宅の場合、壁量計算でも取得できますが、建物の規模や複雑性によっては構造計算が必要になることもあります。
- 計算方法:壁量計算または構造計算
- 対象:小中学校、介護施設、福祉住宅など
- 注意点:認定を受けないと税制優遇が受けられない
耐震等級3:最高等級、許容応力度計算と第三者審査が必須
最も高い等級で、消防署・警察署など防災拠点に採用されるレベルの耐震性です。取得には緻密な「許容応力度計算」と、認定機関による書面審査・現場検査が必要です。
- 計算方法:許容応力度計算(構造解析ソフトを使用)
- メリット:地震保険料の割引、住宅ローン減税の最大優遇など
- デメリット:設計・施工費用が高くなりがち
「耐震等級3相当」との違いに注意:制度的メリットを得るには正式取得が必要
住宅会社の中には「等級3相当」と表示する場合がありますが、これはあくまで「等級3レベルの設計です」という意味にすぎません。実際には第三者機関の認定を受けておらず、評価書がない限り、以下の制度上のメリットが受けられません。
| 項目 | 等級3相当 | 等級3(認定取得済) |
| 地震保険料の割引 | 原則なし | 最大50%割引あり |
| 住宅ローン減税 | 非対象 | 対象 |
| 性能評価書の発行 | なし | あり(等級記載) |
| 固定資産税の優遇 | 非対象 | 条件付きで対象 |
安心・安全だけでなく、保険・税制など経済的メリットを得るには「認定等級3」であることが絶対条件です。 購入・建築の際には「等級相当」なのか「正式取得済」なのかを必ず確認しましょう。
既存住宅の耐震等級の確認と向上方法
新築住宅では設計段階で耐震等級を選択できますが、既存住宅に住んでいる場合、今の家がどの程度の耐震性能を備えているかを把握することが第一歩です。そして必要に応じて補強工事を行えば、耐震性能を引き上げることも可能です。
現状の耐震性能を知るには?診断の流れとポイント
耐震性能の確認には、専門家による「耐震診断」が欠かせません。これは家の構造や劣化状態を調べ、倒壊リスクや補強の必要性を評価するものです。
診断対象
主に1981年(新耐震基準)以前に建てられた住宅が優先対象。ただし、それ以降の建物でも劣化や設計不備があれば診断すべき。
診断項目
壁の配置・量、接合部の強度、基礎の状態、屋根の重量、劣化状況など。
評価の基準
評点1.0以上が「倒壊しない目安」とされ、1.0未満は補強が推奨される。
実施者と費用
建築士や耐震診断士が担当。費用は数万円〜十数万円が一般的で、自治体の補助がある場合も。
自宅の耐震性を数値で「見える化」することが、補強や建て替えの判断を明確にします。
診断結果をもとに、必要な補強箇所や優先順位を把握し、効率的に対応できるのが利点です。
耐震補強による等級向上の選択肢と注意点
診断結果で等級が不足していた場合、建物の部分的な補強によって性能を引き上げることが可能です。主な補強手法は以下の通りです。
壁の増設・筋交いの追加
耐力壁を増やすことで、横揺れへの強さを向上。
接合部の補強金物設置
柱と梁、土台などの結合部分に金物を追加し、崩壊を防ぐ。
基礎の補修・増設
無筋コンクリートや布基礎を、鉄筋入りのベタ基礎などに改修。
屋根材の軽量化
重い瓦から軽量金属屋根への変更で、揺れによる負荷を減少。
| 補強箇所 | 工法例 | 期待される効果 |
| 壁 | 面材張り、筋交い追加 | 横揺れ耐性が向上 |
| 接合部 | 金物補強 | 構造体の崩壊防止 |
| 基礎 | 鉄筋入りベタ基礎補修 | 建物の沈下・傾き防止 |
| 屋根 | 瓦からガルバリウムへ | 重心低下で揺れ軽減 |
補強工事は一度で完了させなくても、予算や時間に応じて段階的に進めることも可能です。
自治体によっては診断費用や補強工事に対する補助金制度も用意されています。事前に相談し、適用条件や申請方法を確認することが成功のカギとなります。既存住宅であっても、計画的な対応によって「安心できる住まい」へとアップデートできるのです。
耐震等級を活用した安心・安全な住まいづくり

耐震等級は、ただの数字や制度ではありません。家族を守る「暮らしの盾」として、住宅の本質的な価値を形にする手段です。 等級の高低に一喜一憂するのではなく、「どんな暮らしを実現したいか」に応じて上手に活用することが、理想の住まいをつくる第一歩となります。
耐震等級を活かした住宅設計のポイント
高い耐震性を確保するには、建物全体のバランス設計が鍵を握ります。ただし、耐震性を優先するあまり、デザインや住み心地が犠牲になるようでは意味がありません。
以下は耐震性と他の要素を両立させるための設計のポイントです。
重心と剛心のバランスを意識
建物が揺れたときにねじれが生じないよう、構造体の配置を均等にする。
過度な吹き抜けや大開口は慎重に
開放感と引き換えに耐力壁が減るため、補強設計が必要。
基礎・構造材の選定にも配慮
地盤に応じた基礎形式と、耐力の高い構造材を組み合わせることで総合力を高める。
住宅性能との複合設計
耐震だけでなく、省エネ性、断熱性、劣化対策などと合わせて設計することで、長寿命な住宅が実現。
高い耐震性を担保しながらも、美しく快適に暮らせる住まいは、設計の工夫次第で実現可能です。
建築士との対話を大切にし、要望を一方通行で終わらせないことが成功のポイントとなります。
地震に強い家づくりのためのアドバイス
耐震等級を最大限に活かすためには、建てる前の「選び方」だけでなく、建てた後の「守り方」も重要です。
信頼できる建築士や施工業者の選び方
構造計算の実績や、住宅性能評価書の取得経験が豊富な事業者を選ぶ。
定期的な点検とメンテナンスの実施
経年劣化によって構造材が弱くなることも。5〜10年ごとに点検を依頼し、必要に応じて補修する。
住まい方の見直し
重たい家具の固定、ガラス飛散防止フィルムの活用など、日常の中でもできる耐震対策は多く存在する。
家族での防災計画の共有
避難経路や緊急連絡手段の確認など、ハードだけでなくソフト面での備えも重要。
| 実施項目 | 内容 | 効果 |
| 構造計算の確認 | 設計段階での強度把握 | 揺れへの耐性を科学的に検証 |
| 性能評価書の取得 | 第三者による評価 | 等級に基づく制度的優遇を享受 |
| 定期メンテナンス | 基礎・柱・接合部など | 劣化による性能低下を防ぐ |
| 家具の固定 | 家具転倒・避難障害防止 | 二次被害の軽減 |
| 防災訓練 | 家族の避難ルート確認 | 緊急時の混乱回避 |
耐震等級は「一度決めたら終わり」ではなく、住まい手が活用し続けてこそ真価を発揮します。
性能を引き出すのは住まい手の姿勢です。正しく理解し、定期的に見直しながら、住まいを長く、強く、安全に育てていきましょう。
最適な耐震等級を選ぶために

地震が頻発する日本において、住まい選びの基準として「耐震等級」を無視することはできません。しかし重要なのは、単に「等級が高いから安心」という思考にとどまらず、自分のライフスタイルや地域特性に合った選択をすることです。
耐震等級1・2・3には、それぞれ異なる設計意図と強度があり、家族構成、立地、予算、将来設計に応じて最適な選択肢は変わります。等級3は確かに高性能ですが、すべての家庭に必要とは限りません。
最適な選択を行うために、以下の視点を持ちましょう。
- 生活の安心と安全をどこまで重視するか
- 建築コストや将来の資産価値への影響
- 地域の災害リスクや地盤の特性
- 制度的なメリット(保険料・減税など)の活用余地
- 信頼できる専門家のアドバイスを得ているか
それぞれの家族にとっての「ちょうどよい耐震性能」は異なります。共働き家庭では「地震後も住み続けられること」が最優先かもしれませんし、高齢世帯では「命を守る最低限の強度+避難のしやすさ」が重視されるでしょう。
重要なのは、自分たちの価値観と暮らしに合った耐震等級を「納得して選ぶ」ことです。
そのためには、感覚だけに頼らず、制度や数値、専門家の知見をバランスよく取り入れる姿勢が欠かせません。
家づくりは人生の中でも最も大きな投資のひとつです。耐震等級を正しく理解し、自分たちの暮らしに合った選択をすることが大切です。
憧れの大手メーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれる

住宅展示場や完成見学会にいくのは時間もかかるし大変…
そんなときに便利なのが「タウンライフ家づくり」です。
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
気になるメーカーや工務店を選び、希望の間取りや予算を入力するだけ。「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる!
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。

「タウンライフ家づくり」はこんな方におすすめ
- あなただけの間取りと見積もりを無料で手に入れ比較したい
- 営業されるのが嫌、苦手
- 自宅でじっくり信頼できるハウスメーカーを選びたい
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ




