この記事にはプロモーション・広告が含まれています
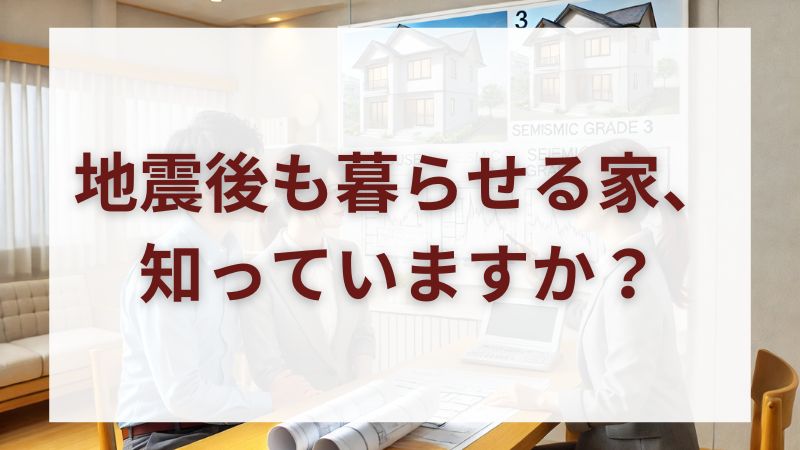
日本は世界でも有数の地震大国として知られています。地震の発生は避けられず、その被害を最小限に抑えるための備えが不可欠です。
これまで多くの人が「建物が倒壊しないこと」に重きを置いてきました。しかし、地震の脅威は一瞬の揺れだけではありません。
>>耐震等級3でも倒壊リスク?見落としがちな落とし穴と安全に守る対策
大切なのは、地震後も安心して生活を続けられる住宅かどうかという点です。一見同じように見える住宅でも、地震に対する備えには大きな違いがあります。
特に注目すべきなのが「耐震等級3」という基準です。これは建築基準法の1.5倍の耐震性能を持つ最上級ランクであり、地震後の生活を左右する鍵となります。
本記事では、耐震等級3の重要性について、具体的な事例や比較を交えながら詳しく解説していきます。「命を守る」だけでなく、「生活を守る」ための新しい視点を提供します。
本当に大切なのは「倒壊しない家」ではなく「住み続けられる家」

地震大国・日本において、「倒壊しない家」を建てることは当然の前提となっています。しかし、本当に求められているのは、揺れに耐えただけでなく、その後も安心して暮らし続けられる家です。
震災後、避難所での生活を余儀なくされる家庭が多いなか、自宅での生活を維持できた家庭は、心身ともに大きな安定を得ています。この違いは、単なる構造強度だけではなく、設計段階でどれだけ「地震後の暮らし」を見据えていたかにかかっています。
避難生活が長期化すれば、家族の健康や仕事、学業にも悪影響が及びます。自宅に住み続けられるという選択は、地震後の生活再建を大きく前進させる力を持っています。
耐震等級3の住宅は、そんな生活の継続性を支える「強さと備え」を兼ね備えた選択肢です。命を守る家から、暮らしを守る家へ住宅選びの基準を見直す時がきています。
「耐震等級3」ってどこが違うの?数字以上に大きい安心の差
「耐震等級」とは、住宅の耐震性能を3段階で評価する制度です。中でも等級3は、警察署や消防署などの災害拠点施設と同等の耐震性能を持つとされています。
これは単なる「数字の違い」ではありません。等級3の住宅は、地震後も家族が普段通りに暮らせる可能性を飛躍的に高めます。
等級の違いによって何が変わるのかを、以下の表にまとめました。
| 耐震等級 | 耐震性能の基準 | 想定される被害と生活影響 |
| 等級1 | 建築基準法の最低基準(震度6強で倒壊しない) | 建物に損傷あり。居住継続は困難な場合も |
| 等級2 | 等級1の1.25倍の耐震性能 | 建物の損傷は軽減されるが、生活への影響は残る可能性あり |
| 等級3 | 等級1の1.5倍の耐震性能 | 構造躯体の損傷が少なく、そのまま住み続けられる可能性が高い |
この差は、家の構造だけでなく、家族の心の安定や生活の継続に直結します。耐震等級3の家なら、避難生活のリスクを大幅に軽減できるのです。
とりわけ、小さな子どもや高齢者がいる家庭にとっては、日常を守れることが何よりの安心材料になります。「万が一」が現実になったとき、数字では見えない差が、命と暮らしを分けるのです。
>>【命を守る家】子どもも高齢者も安心「耐震等級3」という最強の備え
等級1と3の差は1.5倍。でも実際の被害の差はそれ以上
耐震等級の数値差は、単に「1.5倍」という表現だけでは測れません。実際の地震被害では、この1.5倍の差が「住み続けられる家」と「住めなくなる家」を分ける決定的な違いとなって現れます。
代表的な例が、2016年の熊本地震です。この地震では震度7が2度発生し、多くの住宅が被害を受けました。ところが、耐震等級3で建てられた住宅の多くが「無被害」または「軽微な損傷」で済んだことが確認されています。
被災地域での調査結果を、以下の表にまとめました。
| 耐震等級 | 被害状況 | 備考 |
| 等級1 | 全壊・半壊の割合が高い | 倒壊や大きな損傷により住み続けるのは困難 |
| 等級2 | 被害は軽減されるが修繕を要する場合もあり | 損傷の程度によっては一時的に居住困難になる可能性あり |
| 等級3 | 無被害・軽微な損傷が大多数 | 継続居住可能な状態を多くの住宅で維持 |
このように、等級の差は数字以上の生活の質の違いを生み出します。特に二次災害や余震が続く中で、家にとどまれるかどうかは、心理的にも経済的にも極めて重要です。
熊本地震を契機に、耐震等級3の住宅を選ぶ人が急増したのも、実際の効果が証明されたからです。見えないところに投資する価値が、命と生活を守る力になるという現実が、今も語り継がれています。
避難所生活を前提にしていませんか?「住み続けられる」選択がある
地震後、多くの家庭が避難所生活を余儀なくされます。しかし、そこには多くの課題があります。
プライバシーの欠如
カーテン一枚で仕切られる空間での生活は、精神的な疲労を引き起こしやすくなります。
衛生環境の不安定さ
トイレや入浴施設の不足、感染症リスクの高さが、長期生活には不向きな環境となっています。
生活の再建が遅れる
日常生活への復帰が遅れ、家族の健康・教育・仕事にも深刻な影響を及ぼします。
これに対し、耐震等級3の住宅で「自宅にとどまれる」ことは、生活の再開を早め、心身の安定を確保するという大きなメリットをもたらします。
特に子育て世代や高齢者のいる家庭では、慣れ親しんだ自宅で過ごすことが健康維持やストレスの軽減につながります。避難所に頼らずに済むという選択は、防災を「自助」だけで終わらせない社会的価値も持っています。
>>【命を守る家】子どもも高齢者も安心「耐震等級3」という最強の備え
防災とは、ただ「命を守る」だけでなく、「どこで、どう生活を守るか」まで考えること。その選択肢として、耐震等級3の住宅はますます重要性を増しています。
精神的ショックは家の損傷だけじゃない
大きな地震の後、人々が受ける衝撃は物理的な損傷にとどまりません。見慣れた我が家が壊れたり、避難所での不自由な生活が続いたりすること自体が、大きな精神的ストレスとなります。
特に子どもや高齢者は、環境の変化に敏感であり、不安定な暮らしは心身の健康に深刻な影響を及ぼします。「自宅で生活を続けられる」という選択が、家族の心の安定と回復の早さに大きく貢献するのです。
また、住宅の損傷を目の当たりにすること自体が、被災者に強いショックを与えます。「家に帰れない」「修理が必要」「いつ再建できるかわからない」といった不安は、被災後の生活再建に暗い影を落とします。
一方、耐震等級3の家に住んでいた人々の中には、「家が無事だったから落ち着いて対処できた」「日常生活を守れたことが支えになった」と語る声も少なくありません。
家が被害を受けなかったという安心感は、想像以上に大きな支えとなり、被災後の心の回復を助けるのです。精神的被害を最小限に抑えるという意味でも、「住み続けられる強さ」は重要な要素といえるでしょう。
避難しないという選択が、出費や生活の混乱を防ぐ
地震で自宅が損傷し、避難所や仮設住宅に移らざるを得ない場合、直接的な出費だけでなく、生活全体に多大な影響が生じます。その一方で、住み続けられる家を持つことは、被災後の経済的・社会的負担を劇的に軽減する選択肢となります。
避難が必要になると、次のような出費や不安定要素が発生します。
仮住まいの家賃・引越し費用
一時的な住居の確保には予想以上のコストがかかるケースも多く、家計への打撃は避けられません。
家具・家電など生活用品の再購入
壊れた家具の買い直しや日用品の補充には、数十万円規模の費用が必要になることもあります。
就労・学業の中断
家族全体の生活リズムが崩れ、働けない・通学できないなどの事態に直面する可能性も高まります。
これに対して、耐震等級3の住宅で「避難せずに済む」ことは、上記すべての出費や混乱を回避できる可能性を持っています。生活の場を失わないという事実は、経済的損失を抑える最も確実な防災策でもあるのです。
また、保険申請や公的支援の手続きなど、地震後の事務作業も、自宅で落ち着いて行えることで大きく効率が上がります。耐震等級3は、単なる安全基準ではなく、「暮らしの継続コスト」を抑える合理的な選択でもあります。
「命が助かる」その先まで考えた住まいが、家族を守る

地震から命を守るだけでは、本当の意味での「安心」は得られません。災害発生後の暮らしにまで視野を広げたとき、住宅に求められる性能は一段と高いものになります。
「家に住み続けられるかどうか」が、家族の未来に大きな影響を与えるのです。
震災を経験した多くの人が語るのは、「地震そのものよりも、その後の生活が一番大変だった」という現実です。住む場所を失い、生活の基盤が揺らぐことが、どれほど大きな負担となるかは計り知れません。
耐震等級3の住宅は、こうした「その後」に対応できる設計思想の象徴です。被災直後から普段の生活をできる限り維持し、家族の暮らしを守るための備えとして機能します。
表面的な安全性だけではなく、災害後の暮らしの持続性までを含めた防災性能を持つ住宅こそが、これからの新しい“安心の基準”になるべきです。その考え方が、家づくりに求められているのです。
“最低限”では足りない?建築基準法に頼りすぎないという選択
建築基準法は、すべての建物が守るべき最低限のルールを定めた法律です。しかし、「基準法を満たしていれば安全」と考えるのは大きな誤解です。
>>耐震等級3は完璧じゃない?誤解しがちな10の落とし穴と正しい対策
実際には、基準法で定められている耐震性能(耐震等級1)は、震度6強〜7程度の地震でも「倒壊しないこと」を目的とした最低限の設計に過ぎません。つまり、「壊れない」ことは担保されても、「住み続けられるか」は保証されていないのです。
以下は、基準法と耐震等級の関係を示した比較表です。
| 評価基準 | 建築基準法(等級1) | 耐震等級2 | 耐震等級3 |
| 耐震性の基準 | 最低限の耐震性能 | 基準法の1.25倍 | 基準法の1.5倍(最上位等級) |
| 想定される目的 | 倒壊を防ぐ | 被害を軽減し居住継続の可能性もある | 生活を守り、継続的に住める水準 |
| 災害時のリスク対応 | 避難の必要が高い可能性あり | 状況次第で避難または居住可 | 避難不要で居住継続の可能性が高い |
法律は「最低限の安全」でしかない以上、本当に家族の命と暮らしを守るなら、自主的に“その先”を選ぶ必要があるのです。その選択が、耐震等級3という防災意識の新しいスタンダードにつながります。
命だけでなく生活全体を守るためには、基準を超えた備えが不可欠です。法律の範囲にとどまらない「本当の安心」を、住宅選びの軸に据える時代が来ています。
「命を守るだけ」では、その後の生活は守れない
建築基準法で守られるのは、あくまで「生命の安全」です。しかし、震災を経験した人たちが口を揃えて語るのは、「助かった後の生活こそが本当の試練だった」という現実です。
地震によって自宅が損傷すれば、たとえ命は助かっても、生活の土台が失われます。仮設住宅や親戚宅への一時避難、家財の損壊、日常の喪失……それらすべてが、家族の生活に長く影を落とします。
また、住宅再建には時間とコストがかかり、精神的・経済的な負担も非常に大きなものになります。いったん住まいを失えば、家計だけでなく働き方や子どもの教育環境までが一変します。
一方、耐震等級3の住宅であれば、構造的損傷を受けにくく、被災後もそのままの暮らしを維持できる可能性が高まります。この「生活が続く」という安心感こそが、家族にとって最も価値のある備えです。
命を守るだけでは十分ではありません。「暮らしを守れる家を選ぶ」という判断が、未来の安心と直結しているのです。
数字で選べる安心。「住宅性能表示制度」で失敗しない家選びを
住宅の性能は、見た目では判断できません。しかし、購入者や建築主が「安心して選べる仕組み」が存在します。
それが「住宅性能表示制度」です。これは国が定めた統一基準に基づき、住宅の性能を数値化・可視化する仕組みで、耐震性だけでなく、断熱性や劣化対策なども含まれます。
この制度を利用することで、以下のようなメリットがあります。
第三者機関による評価で信頼性が高い
独立した評価機関が厳密にチェックするため、設計段階から信頼性のある住宅選びが可能になります。
性能の比較がしやすくなる
カタログだけでは見えにくい「耐震等級」や「劣化対策等級」が明確に表示されるため、家選びで迷いにくくなります。
将来の資産価値を守れる
高性能住宅は長期的に見て資産価値が下がりにくく、リセール時にも有利になる傾向があります。
表にまとめると、次のようになります。
| 比較項目 | 性能表示制度を活用しない場合 | 性能表示制度を活用した場合 |
| 性能の信頼性 | 設計者の説明に依存 | 第三者評価で客観的に確認可能 |
| 耐震等級の把握 | 明記されない・曖昧 | 等級1〜3で明確に確認可能 |
| 将来の資産価値維持 | ばらつきあり | 高性能表示で安定した評価が可能 |
>>耐震等級3の家は資産価値が落ちない?売却・賃貸で有利になる理由を徹底解説
>>【耐震等級比較ガイド】等級1・2・3の違いと、あなたに合った選び方
「知らなかった」では済まされないのが住宅選び。住宅性能表示制度は、後悔しない家づくりをサポートする強力な味方です。数値化されたデータを根拠に、冷静に「安心」を選び取る時代が来ています。
「防災=備蓄」だけで終わっていませんか?“暮らしの継続”が本当の備え
多くの人が「防災」と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、水や食料、電池といった備蓄品です。もちろん、それらは災害直後を乗り切るために不可欠な準備です。
しかし、本当に備えるべきは「その後の生活」まで含めた視点です。日常生活をいかに早く、いかに安定して再開できるかが、防災の真価を問われるポイントといえるでしょう。
備蓄は「その場しのぎ」になりがちですが、耐震等級3の住宅は、被災直後からの「生活の継続性」そのものを守ってくれる存在です。
住み慣れた家にとどまれる
精神的安定と生活のスピード回復に直結します。
避難所に依存しない生活が可能
感染症リスクやストレスの軽減にもつながります。
仕事や学校をすぐに再開できる
社会復帰が早く、経済的・教育的損失も最小限で済みます。
防災とは単なる「準備」ではなく、「未来を止めない力」を整えること。暮らしを守るための備えが、真の意味での“災害に強い家”を形づくるのです。
生活の再開が早い人には理由がある
地震の被害を受けた地域では、多くの家庭が生活の再建に長い時間を要します。しかし一部には、驚くほど早く元の生活に戻れる家庭も存在します。
その違いを生む大きな要因の一つが、「家の耐震性能」です。耐震等級3の住宅に住んでいた人々は、被災直後から自宅で生活を継続できるケースが多く見られます。
これは単に家が壊れなかったから、という理由にとどまりません。以下のような要素が、生活再開のスピードを支えているのです。
自宅の片付けだけで日常生活に戻れる
大きな補修が不要なため、短時間で元の生活に復帰できる。
仕事や学校の再開が早い
家族全員の生活サイクルが乱れず、社会復帰もスムーズに進む。
精神的ダメージが最小限で済む
家が無事という事実が、家族に安心と冷静な判断力をもたらす。
熊本地震や東日本大震災の被災者の証言からも、こうした違いは明確に表れています。生活再建の早さは、住宅の性能と直結しているという現実を無視することはできません。
今後の災害に備え、「何を選ぶか」ではなく「どう備えるか」が、暮らしの持続力を左右する時代になっています。
地域全体が強くなる。耐震住宅は“個人の安心”を超える
地震への備えは、個人や家族単位の話にとどまりません。地域社会全体がどれだけ災害に強いかも、私たちの暮らしを大きく左右します。
耐震等級3の住宅が増えることには、個人の生活を守るだけでなく、地域全体の防災力を底上げする効果があります。
その理由は以下の通りです。
避難所の負担を軽減できる
多くの住民が自宅にとどまれることで、避難所の混雑や支援物資の不足が起きにくくなります。
地域インフラの早期復旧に寄与
地元住民が現地にとどまって協力できれば、インフラ整備や支援体制の構築が円滑に進みます。
復興のスピードが上がる
商店や企業も営業再開しやすくなり、経済活動の回復が早まります。
以下の表に、耐震住宅が地域にもたらす影響を整理しました。
| 耐震住宅の効果 | 地域社会への影響 |
| 自宅にとどまれる家庭の増加 | 避難所混雑の回避、行政支援の負担軽減 |
| 家族単位の生活継続が可能 | 子育てや介護を地域内で完結しやすくなる |
| 地元経済の早期復旧 | 地元商店やサービス業の営業再開がスムーズに進む |
一人ひとりの「備える」という行動が、地域の安全と復興力を形づくる土台になります。災害は個人では避けられませんが、備えによってその被害を最小限に抑えることはできます。
「自分だけが助かればいい」という時代から、「地域全体で守り合う」時代へと、防災意識も進化しているのです。
「被災しても暮らしを失わない」という家のあり方

地震大国・日本では、多くの震災を経験してきた中で、住まいのあり方も大きく見直されてきました。そのなかでも、耐震等級3の住宅に住む人たちの“被災後の証言”には、大きな意味があります。
「命を守る」にとどまらず、「生活を守る」性能を証明した家々が実際に存在するのです。
こうした住宅は、震災直後から生活の継続が可能だったという点で、従来の家づくりと明確に一線を画します。耐震性能の高さは、単なる構造強度ではなく、居住者の心理的安定や、地域の支援負担の軽減にも寄与しているのです。
事実、耐震等級3を採用していた多くの家は、震災後も住み続けられたという報告が各地から寄せられています。その実体験に耳を傾ければ、どのような備えが生活の継続性を左右するのかが、よりはっきりと見えてくるでしょう。
今後の家づくりにおいて、災害に「耐える」だけでなく、「乗り越えられる」住まいを選ぶこと。それが、本当の意味での安心を手に入れる第一歩となります。
熊本地震でわかった“等級3の底力”
2016年の熊本地震では、2度の震度7という未曾有の揺れが観測され、多くの住宅が全壊や半壊の被害を受けました。しかしその中で、耐震等級3の住宅が極めて高い耐震性能を発揮し、注目を集めました。
>>【保存版】耐震等級3の実力とは?震度5〜7での性能を徹底検証
熊本県益城町をはじめとする被災地での調査では、耐震等級3の住宅が無被害または軽微な損傷にとどまり、住み続けられた事例が多数確認されています。
以下の表に、熊本地震での住宅の損傷状況を整理しました。
| 耐震等級 | 被害状況の傾向 | 継続居住の可否 |
| 等級1 | 倒壊・半壊が多数 | 多くが避難生活に移行 |
| 等級2 | 一部で損傷や外壁の亀裂など | 状況によっては居住継続困難 |
| 等級3 | 無被害または軽微な被害が中心 | そのまま居住可能な住宅が多数確認された |
この差は、数値では語りきれない大きな安心の差であり、災害時の対応力の違いとしても如実に表れました。
また、等級3の住宅に住んでいた住民の多くが「家に被害がなかったことが心の支えになった」「他の人を助ける側に回れた」と語っています。自宅が安全であれば、自分だけでなく周囲を支える行動にもつながるという社会的な価値も持ち合わせているのです。
熊本地震は、耐震等級3という基準が「数字のため」ではなく、「命と生活を守るため」にあることを証明した出来事でした。
他の震災でも見られた、住み続けられた家の共通点
熊本地震に限らず、東日本大震災や能登半島地震といった過去の大地震でも、「地震後も自宅で生活を続けられた家」には共通点が見られます。それが、構造的に優れた設計と、数値に裏付けられた耐震性能(とりわけ耐震等級3)です。
例えば、東日本大震災では津波被害のなかった内陸部で、耐震等級3の住宅が構造的な損傷を免れ、多くの世帯がそのまま居住を継続できました。また、2024年の能登半島地震でも、等級3を取得した住宅の多くが倒壊を免れ、「そのまま生活が続けられた」という報告が各所から寄せられています。
このような事例から分かるのは、次のようなポイントです。
耐震等級3の住宅は、震度7レベルでも倒壊を防ぎうる実績を持つ
多重構造・許容応力度計算により、地震エネルギーの受け流し方が根本的に異なります。
設計段階から「揺れに耐える家」として考えられている
壁の配置や構造用金物の選定など、耐震構造を最大限に活かす設計がされているケースが多くあります。
実際に住み続けられた事実が、設計思想の正しさを証明している
住民の証言に基づく「自宅避難の実現」は、性能の信頼性を物語ります。
以下の表は、各地の震災後に「住み続けられた家」の傾向をまとめたものです。
| 地震名 | 耐震等級3住宅の被害状況 | 継続居住の可否 |
| 熊本地震 | 無被害または軽微な損傷が多数 | 多くが自宅での生活継続が可能だった |
| 東日本大震災 | 内陸部で被害軽微な事例が目立つ | 自宅避難を選択する家庭が多く確認された |
| 能登半島地震 | 構造健全な等級3住宅が健在 | 被災直後から通常生活を再開できた事例多数 |
過去の震災が教えてくれるのは、耐震性能は「備えるべき知識」ではなく「実際に効く防災手段」だという事実です。未来の安心を得るために、これらの実例は極めて重要な示唆を与えてくれます。
“性能”だけではない、失敗しない耐震住宅の見分け方

住宅の耐震性を考えるとき、単に「等級3だから安心」と思い込んでしまうのは危険です。本当に安心できる耐震住宅を見極めるには、設計や施工の“中身”にまで目を向ける必要があります。
>>耐震等級3の家は“信頼できる施工会社”で!悪質業者に騙されない見極め術
見た目やパンフレットだけでは判断できない、失敗しないための視点をいくつか紹介します。
構造計算の方法が明示されているか
特に「許容応力度計算」を採用しているかどうかは、構造的信頼性を測るうえで重要な指標です。
設計者や施工会社が“構造の見える化”に積極的か
図面の内容説明や、構造体を施工中に見せる対応など、透明性のある対応が信頼性に直結します。
「等級3相当」と記載された住宅に注意する
等級3の仕様で設計していても、正式な認証を受けていないものは、実際の性能が担保されていない可能性があります。
以下の表は、表面的な表示だけでなく「本当に安心できる家」を見分けるポイントを比較したものです。
| 見分けポイント | 注意すべき表記例 | 信頼できる状態 |
| 耐震等級の明記 | 等級3“相当” | 等級3の認定済・性能評価書あり |
| 構造計算の方法 | 簡易な壁量計算のみ | 許容応力度計算を用いた設計 |
| 設計・施工の説明姿勢 | 質問に対して曖昧な回答 | 図面・仕様の根拠を明確に説明できる |
| 完成前の確認方法 | 完成品だけを見せる | 工事中の構造見学や写真記録がある |
本当の安心は、「見えない部分」にこそ宿る。数字だけにとらわれず、プロセスや透明性にも着目することで、家族の命と生活を守る家づくりが可能になります。「耐震等級3」という表記を、ただのマークで終わらせないために、しっかりと目と知識を持って選びましょう。
許容応力度計算って?知らないと損する構造計算の落とし穴
耐震等級3の家を選ぶうえで、見逃してはいけないのが「構造計算の方法」です。とくに「許容応力度計算」は、構造安全性の信頼度を高めるうえで極めて重要なポイントです。
許容応力度計算とは、部材の一本一本にどのくらいの力がかかり、それにどれだけ耐えられるかを精密に計算する方法です。これに対し、一般的な木造住宅で用いられる「壁量計算」は、あくまで簡易的なチェックに過ぎません。
つまり、同じ「耐震等級3」であっても、構造計算の方法によって実際の安全性には大きな差が生じるのです。
以下の表でその違いを整理します。
| 計算方法 | 概要 | 信頼性 | 適用される場面 |
| 壁量計算 | 壁の量だけで判断する簡易な方法 | 低〜中 | 木造2階建て以下などの小規模住宅で主流 |
| 許容応力度計算 | 部材ごとの応力を詳細に検証する方法 | 高(精密かつ信頼性が高い) | 耐震等級3を確実に担保したい場合に推奨 |
とくに地盤条件が厳しい地域や、将来的な資産価値まで考える人にとって、許容応力度計算は避けて通れない選択肢となります。
「等級3相当」とうたっていても、構造計算の根拠が弱ければ“見かけ倒し”の安心に終わってしまう危険性もあります。確かな安心を得るには、住宅会社に「どの構造計算を採用しているか」を明確に確認する姿勢が不可欠です。
数字だけでは見えない違いが、いざというときの安全性に直結します。家づくりを後悔しないためにも、構造計算の“中身”に注目する視点を持ちましょう。
耐震等級3は、保険料にも安心をもたらす
耐震性能が高い住宅は、災害時の被害を軽減できるだけでなく、経済的なメリットももたらします。その一つが「地震保険料の割引制度」です。
耐震等級3を取得した住宅は、地震保険料が最大50%割引される制度があり、長期的なコストパフォーマンスに大きく貢献します。これは、被害リスクが低い住宅と認められているからこその恩恵です。
以下に、耐震等級による地震保険料の割引率を示します。
| 耐震等級 | 保険料の割引率 | 特記事項 |
| 等級1(基準法レベル) | 割引なし | 割引制度の対象外 |
| 等級2 | 30%割引 | 証明書の提出が必要 |
| 等級3 | 最大50%割引 | 耐震等級3の評価書を提出することで適用 |
この割引は、火災保険とセットで加入する地震保険においても非常に効果的で、年間数万円単位での節約が期待できます。また、保険会社によっては独自の割引制度を導入していることもあり、住宅性能の高さが評価されるケースが増えています。
つまり、耐震等級3は「命と生活を守る性能」であると同時に、家計を守る経済的な備えとしても機能する資産価値の高い選択といえるのです。
初期投資としては少し高く感じるかもしれませんが、保険料の割引や被災リスクの軽減という形で、長期的なリターンを生む仕組みがすでに整っています。防災と経済合理性を両立するためにも、耐震等級3は見逃せない要素です。
「命」と「暮らし」を守る、新しい住まい選びの基準

地震大国・日本に暮らす私たちにとって、「命を守る」だけではなく「その後も安心して暮らせる住まい」を選ぶことが、真の防災対策になります。耐震等級3は、そのための有力な基準であり、家族の未来を支える力そのものです。
建築基準法を満たしているだけでは、安心とは言い切れません。暮らしの継続、生活再建の速さ、精神的な安定、そして地域の防災力の向上――そのすべてに貢献するのが耐震等級3の住宅です。
今こそ、住まいの選び方を見直すときです。「そのときどうするか」ではなく、「そのときどうありたいか」から逆算した家づくりを考えましょう。
大切な人を守るために、そして未来の自分たちを守るために、
「地震に強い家」を超えた「地震後も暮らせる家」を選ぶという選択が、これからの新しい常識となっていくはずです。
憧れの大手メーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれる

住宅展示場や完成見学会にいくのは時間もかかるし大変…
そんなときに便利なのが「タウンライフ家づくり」です。
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
気になるメーカーや工務店を選び、希望の間取りや予算を入力するだけ。「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる!
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。

「タウンライフ家づくり」はこんな方におすすめ
- あなただけの間取りと見積もりを無料で手に入れ比較したい
- 営業されるのが嫌、苦手
- 自宅でじっくり信頼できるハウスメーカーを選びたい
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ




