この記事にはプロモーション・広告が含まれています
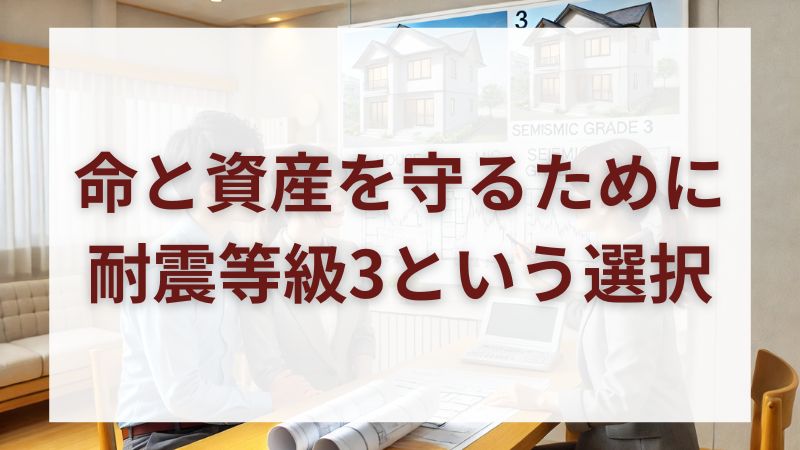
日本は世界有数の地震多発国であり、住宅の耐震性能は家族の命を守る重要な要素です。それにもかかわらず、住宅購入時に「耐震等級」という基準を正しく理解し、判断材料にしている人は多くありません。
>>【南海トラフ・首都直下地震に備える】高リスク地域にこそ「耐震等級3」の家を建てる理由
「耐震等級3」という言葉を聞いたことがあっても、それが具体的に何を意味し、どのような安心を提供してくれるのかを説明できる人は限られています。
この見落とされがちな基準こそが、「いざという時に本当に命を守ってくれる住まいかどうか」を分ける大きな指標となります。
家は見た目や間取りだけでは選べません。大切なのは、災害が起きた時にも壊れず、家族の避難場所として機能することです。
この記事では、「耐震等級3」の基礎知識から他の等級との違い、制度的な背景、そして購入・建築時の具体的なチェックポイントまでを網羅的に解説します。安全な住まいを選ぶために、知っておくべき“本当の安心の基準”を手に入れましょう。
等級1と3は“たった2ランク差”ではない

「等級3」と聞くと、「等級1」や「等級2」とそれほど違いがないように思えるかもしれません。しかし、この数字の差は単なる“ランクの違い”ではなく、建物の構造的な強さ、安全性、そして家族の生存可能性を左右する重大な違いです。
等級1は、建築基準法を満たす最低限の耐震性能であり、震度6強から7程度の地震でも「倒壊しないこと」を目的としています。一方、等級3はその1.5倍の耐震力を持ち、地震発生時にも「損傷を最小限に抑え、住み続けられること」を前提に設計されます。
この違いは、被害状況だけでなく、地震後の「生活の継続可能性」に大きな影響を与えます。避難所生活を余儀なくされるか、自宅で暮らし続けられるかという分かれ道になるのです。
等級3の住宅は消防署や警察署と同等の耐震性能を想定して設計されており、災害時の拠点となり得る強さを持っています。
>>【保存版】耐震等級3の実力とは?震度5〜7での性能を徹底検証
耐震性能別の違い
| 等級 | 耐震性能の基準 | 期待される被害 | 地震後の居住継続性 |
| 等級1 | 建築基準法の最低基準(震度6強~7で倒壊しない) | 大破または半壊の可能性あり | 再建・補修が必要な場合が多い |
| 等級2 | 等級1の1.25倍の強度 | 中破が想定される | 一時的な避難の可能性あり |
| 等級3 | 等級1の1.5倍の強度 | 軽微な損傷で済む可能性が高い | 自宅に住み続けられる可能性が高い |
「たった等級2つの差」が、家族の命、生活、そして将来を左右する可能性を持っています。見た目ではわからないこの違いこそが、耐震等級を正しく理解すべき理由です。
耐震性能と建築基準法の本当の関係
「建築基準法を満たしているから安心」と思っていませんか?これは大きな誤解です。建築基準法で求められるのは、あくまで“最低限の安全性”です。
等級1はその基準に準拠しており、「震度6強~7程度の地震で倒壊・崩壊しないこと」が目安です。しかし、「壊れない」ことと「住み続けられる」ことは別の話です。
たとえば、壁が大きくひび割れたり、柱が傾いたりすれば、住めなくなる可能性があります。耐震等級3は、同じ震度でも建物が軽微な損傷で済むよう設計されており、地震後も生活を継続できるレベルの強度を持ちます。
この違いを理解していないと、「法律を守っている家」でも大地震で住めなくなることがあります。「建築基準法=安全」は誤りであり、真の安心はその上にある耐震等級で評価すべきです。
| 規定・等級 | 耐震目標 | 被害の可能性 | 地震後の居住性 |
| 建築基準法(等級1) | 倒壊・崩壊の防止 | 大きな損傷の可能性 | 住めない場合も多い |
| 耐震等級3 | 損傷の最小化・機能維持 | 軽微な損傷に抑制 | 住み続けられる可能性が高い |
安心できる家づくりのためには、基準法を超えた耐震設計が必要不可欠です。耐震等級3はその象徴であり、地震に備えるための“次なる常識”となりつつあります。
“倒壊しなかった家”に共通する条件とは?

2016年に発生した熊本地震は、耐震性能が住宅の命運を大きく左右する現実を突きつけました。同じ地域、同じ規模の地震でも、被害の程度は住宅ごとに大きく異なっていたのです。
この地震で、耐震等級3を取得していた木造住宅の多くが倒壊を免れたという事実があります。一方、建築基準法を満たす等級1の住宅では、全壊や半壊が相次ぎ、避難生活を余儀なくされた世帯も少なくありませんでした。
国土交通省の調査では、耐震等級3を取得した住宅の中で、構造被害を受けた割合はわずか数%にとどまりました。これは、単なる偶然ではなく、「構造設計の精度と堅牢性」がもたらした結果です。
熊本地震における住宅被害の比較
| 耐震等級 | 全壊率 | 半壊率 | 軽微被害・無被害率 |
| 等級1 | 約15% | 約30% | 約55% |
| 等級2 | 約8% | 約25% | 約67% |
| 等級3 | ほぼ0% | 約3% | 約97% |
耐震等級3を満たす住宅は、設計段階で応力の分散や補強材の配置、壁量のバランスなどが厳密に計算されています。これにより、同じ揺れでも「壊れにくい構造」が実現されています。
地震に強い家には、明確な“設計上の裏付け”があることが熊本地震で証明されました。
この事実は、住宅選びの指針として極めて重要です。価格や設備だけでなく、耐震等級という“見えない性能”に注目することが、家族の安全を守る最善の選択です。
「耐震等級3」は本当に機能したのか
熊本地震は“想定外”の揺れが連続して発生した、極めて稀なケースでした。震度7の地震が2回発生したことで、建物に与えるダメージは累積し、多くの住宅が大きな被害を受けました。
そのなかで注目されたのが、「耐震等級3」を取得した住宅の生存率です。住宅金融支援機構などの調査では、等級3の木造住宅は2回の震度7にも耐え、「無被害、もしくは軽微な被害」で済んだ割合が9割を超えるという結果が出ました。
一方、同じ地域の等級1や未評価住宅では、1回目の地震で構造が弱まり、2回目で倒壊したケースが多く報告されています。これは、等級3が単なる“強い家”ではなく、連続する地震にも対応できる「持続的な強さ」を備えていることを示しています。
熊本地震で注目されたデータ
| 分類 | 等級3住宅(木造) | 等級1住宅(木造) |
| 無被害 | 約60% | 約20% |
| 軽微な被害 | 約30% | 約25% |
| 中・大破 | 約10% | 約55% |
この結果を受けて、国土交通省や建築士団体の間でも「等級3の取得を基本とすべき」との提言が強まりました。地震が“1度限りではない”という現実を前提とすれば、耐震等級3はもはやオプションではなく「必須要件」とも言えるのです。
将来起きるかもしれない“次の震災”に備えるために、熊本地震のデータは今、私たちに明確な選択肢を突きつけています。「過去の被害を教訓にできるか」が、安全な家づくりの第一歩です。
「無被害」だった家とそうでなかった家の差
熊本地震後、多くの被災地で目にしたのは、隣接する家の明暗がくっきり分かれる光景でした。片方は柱が折れ、瓦が落ち、住める状態にない一方で、もう片方はまるで地震がなかったかのように佇んでいる。この差を生んだのが、耐震等級という“目に見えない性能”の差だったのです。
等級3を取得していた家の多くは、揺れによる被害をほぼ受けず、日常生活を維持できました。対照的に、等級1や評価未取得の住宅は、地盤に問題がなくても構造そのものが脆弱で、被害を免れませんでした。
つまり、住宅の“被害の差”は立地や運ではなく、設計段階で既に決まっている可能性が高いのです。この事実は、これから家を建てる人、買う人にとって、非常に重い示唆を与えています。
被災現場で確認された主な被害差
| 評価の有無 | 主な被害 | 住居の使用可否 | 被災者の生活 |
| 耐震等級3取得済 | 軽微な壁面のヒビ程度 | 継続利用可能 | 通常生活維持 |
| 耐震等級1・未評価 | 壁の崩壊・屋根の損壊・基礎の亀裂 | 住めない・避難所生活 | 長期復旧・生活再建困難 |
等級3の住宅では、壁量のバランス、金物の配置、接合部の設計といった見えない部分が精密に組み立てられています。これが、たとえ同じ震度を受けても「被害の出方に圧倒的な差」が出る理由です。
安心は偶然ではなく、構造的に準備された結果。住宅の外観や価格に惑わされることなく、「どれだけ地震に備えてあるか」を判断基準とすることが、真の意味での安全な住まい選びにつながります。
保険もローンも“耐震等級3”が優遇される理由

耐震等級3の家を選ぶメリットは、命を守ることだけではありません。実は経済的な面でも大きなメリットがあり、保険料やローン金利が軽減される制度が数多く用意されています。
これは、保険会社や金融機関が「耐震等級3の家は壊れにくく、リスクが低い」と判断しているためです。つまり、性能が高い家ほど、地震による損害が少ないと見なされ、支援や優遇を受けやすくなるという仕組みです。
こうした制度を活用することで、住宅取得後のコスト負担を抑えることができます。耐震性能の高さが、家計にとっても“安心材料”になる時代です。
主な優遇制度とその概要
| 制度名 | 内容 | 耐震等級3による恩恵 |
| 地震保険 | 耐震等級に応じた保険料割引 | 最大50%の割引が適用される |
| フラット35S | 住宅ローンの金利引下げ制度 | 当初10年間で年0.25%の金利優遇 |
| 長期優良住宅 | 税制優遇・補助金の対象 | 登録により固定資産税の軽減など |
これらの制度は、条件を満たせば誰でも利用可能です。しかし、設計段階で「等級3を取得する意思表示」をしていなければ、適用対象外になる場合もあります。
住宅の性能が「コストメリット」に直結する今、耐震等級3は将来の家計にまで安心をもたらす選択肢です。災害リスクへの備えとして、そして経済的合理性の観点からも、耐震等級3の住宅は非常に優れた投資価値を持っているのです。
地震保険料がここまで変わる
耐震等級3の家を建てると、住宅ローンだけでなく「地震保険料」も大きく軽減されます。これは、保険会社が「耐震性が高い=保険金支払いリスクが低い」と評価しているためです。
実際に、地震保険では耐震等級に応じて最大50%の割引が適用されます。
割引率は以下の通りです。
| 耐震性能 | 割引名 | 割引率 | 適用条件 |
| 耐震等級1 | 耐震診断割引 | 最大10% | 建築士などの診断書が必要 |
| 耐震等級2 | 耐震等級割引(等級2) | 30% | 住宅性能評価書の提出が必要 |
| 耐震等級3 | 耐震等級割引(等級3) | 50% | 同上 |
年間保険料が5万円の地震保険に加入すると、等級3の家では年間2万5千円の割引を受けられる計算になります。10年加入すれば、25万円もの差が生まれるのです。
長期的に見れば「耐震性能の高さ=保険料の節約」と直結するということが明らかです。高性能な住宅は、万が一に備えるだけでなく、家計にも継続的な恩恵をもたらす“資産”とも言えるでしょう。
ローン金利が下がるのはどんな家?
地震に強い家は、安全だけでなく、住宅ローンにおいても優遇されます。とくに「フラット35S」は、耐震等級の高い住宅に対して一定期間、金利を引き下げる制度を提供しています。
フラット35Sでは、耐震等級2以上または免震構造を持つ住宅に対し、当初10年間にわたり年0.25%の金利引き下げが適用されます。これは、3000万円を借入れた場合、10年間で約50万円〜70万円の支払い軽減に相当します。
| 区分 | 対象住宅 | 金利引下げ内容 | 優遇期間 |
| フラット35S(Aプラン) | 耐震等級3・長期優良住宅など | 年0.25%引下げ | 当初10年間 |
| フラット35S(Bプラン) | 省エネルギー性能など | 年0.25%引下げ | 当初5年間 |
この制度を受けるためには、設計段階で該当する等級を取得し、住宅性能評価書などの証明書を金融機関に提出する必要があります。
「災害に強い=経済的にも優秀な住宅」であることが、住宅選びにおける新たな基準となっています。ローン負担を減らしたい人にとっても、耐震等級3は大きな味方となるでしょう。
耐震等級と税制優遇の見逃せない関係
耐震等級3の住宅は、安全性に優れるだけでなく、税制面でも多くのメリットが用意されています。その中でも代表的なのが、「長期優良住宅」としての認定です。
長期優良住宅は、耐震性・省エネ性・維持管理性などの基準をクリアした住宅に対し、登録を受けることで各種の税制優遇措置が適用されます。耐震等級3はその要件の一つであり、これを満たすことで、以下のような恩恵を受けられます。
| 優遇内容 | 詳細 | 耐震等級3による恩恵 |
| 登録免許税の軽減 | 新築住宅登記時の税率引下げ | 通常より最大50%軽減 |
| 不動産取得税の軽減 | 一定額まで課税対象から控除 | 耐震等級によって控除額拡大 |
| 固定資産税の減額措置 | 新築後一定期間の税額軽減 | 最大5年間、税額が1/2に減額 |
| 住宅ローン控除の優遇 | 控除期間・控除額の拡大 | 長期優良住宅は最大13年間対象 |
このように、設計段階から等級3を取得しておくことで、住宅取得後の税金負担を大きく抑えることが可能になります。
単に地震対策としてだけでなく、「長く、安心して、経済的にも得をする家づくり」として、耐震等級3の取得は非常に賢明な選択です。住宅ローンや補助金制度だけでなく、税金という大きな固定支出にも効果をもたらす点は見逃せません。
「耐震等級3を選びたい」と思ったときは?

耐震等級3の重要性を理解したとしても、実際に取得するにはいくつかのハードルがあります。その第一歩は、「建築会社や設計士に意思を明確に伝えること」です。
耐震等級3は自動的に付与されるものではなく、設計段階からその取得を前提にプランを立てる必要があります。工務店やハウスメーカーとの打ち合わせでは、「耐震等級3を取得したい」と明言することで初めて、専門的な対応が始まるのです。
設計や建築に関わるコスト面でも事前に確認が必要です。一般的に、等級1の住宅に比べて数十万円〜100万円程度の追加費用がかかるケースがありますが、地震保険料の割引やローン金利の優遇、さらには命を守る価値を考えれば十分に納得できる範囲といえるでしょう。
耐震等級3を選ぶために必要な準備
工務店・ハウスメーカーへの明確な依頼
「耐震等級3を取得したい」と初期段階で伝えることが重要です。
性能評価機関への申請準備
住宅性能表示制度を利用する場合、設計・施工時に評価機関の審査を受ける必要があります。
コストや設計上の制約を理解する
耐震性能を高めるには壁量や柱の配置に制限がかかることがあり、間取りやデザインとのバランス調整が必要です。
>>【平屋でも耐震等級3は必要?】知らないと危険な間取りと構造リスク
安心な住まいを実現するためには、「伝え方」と「段取り」がカギを握ります。思い描いた理想の家に耐震性能という本当の安心を加えるためにも、計画の最初から“等級3基準”を土台に据えましょう。
設計士や工務店に“どう伝えるか”が分かれ道
理想の住まいを手に入れるためには、家族の要望だけでなく、安全性への希望もしっかりと設計士や工務店に伝えることが欠かせません。しかし「耐震等級3でお願いします」と伝えるだけでは不十分なケースもあります。
実際には、「耐震等級3相当」のような表現で済まされることもあり、正式な認定が取れていないことがあります。この違いは保険料やローン、税制優遇にも影響し、将来的な資産価値にも関わる可能性があります。
そこで重要になるのが、“正式な等級取得”を明確に依頼する伝え方です。
「耐震等級3を取得したい」と明確に伝える
相手が経験豊富であっても、こちらの意思をしっかりと示すことで計画が確実に進みます。
住宅性能評価機関による認定取得を依頼する
ただ設計上の性能を満たすのではなく、公的な証明が必要です。
コストや構造変更への影響も事前に相談する
設計段階での確認によって、後からトラブルを避けられます。
「性能証明書」の取得を契約条件に加える
書面で残すことが、住宅の価値保証にもつながります。
耐震等級3を実現するには、施主自身が“賢く伝える力”を持つことが不可欠です。信頼できるパートナーと共に、確かな安心をカタチにしていきましょう。
>>耐震等級3の家は“信頼できる施工会社”で!悪質業者に騙されない見極め術
「耐震等級3相当」は同じじゃない?
住宅業界ではよく「耐震等級3相当」という表現が使われます。一見、正式な等級3と同等の強度を持つように思えますが、この言葉には大きな落とし穴があります。
>>耐震等級3でも倒壊リスク?見落としがちな落とし穴と安全に守る対策
「等級3相当」は、あくまで設計者や建築会社が“等級3と同じくらいの性能がある”と自主的に判断したものです。公的な評価機関による確認や証明がされていないため、地震保険の割引やローン優遇、税制優遇の対象にはならないことがほとんどです。
実際の証明力や資産価値の面では、「等級3相当」は正式な「耐震等級3」とはまったく別物と考えるべきです。
| 比較項目 | 耐震等級3(正式取得) | 耐震等級3相当 |
| 評価機関の認定 | あり | なし |
| 地震保険の割引対象 | 対象(最大50%) | 対象外が多い |
| フラット35Sなどの金利優遇 | 対象 | 基本的に対象外 |
| 税制優遇措置 | 対象 | 対象外 |
| 資産価値の証明 | 証明書あり | 証明なし |
同じように見えても、取得しているかどうかで「住まいの価値と安心度」は大きく異なります。「等級3相当」という表現が出てきたら、必ず「住宅性能評価書の取得済みか」を確認し、証明書の有無をチェックしましょう。
今の家は安全か?“あとから”でもできる対策

新築時に耐震等級3を取得していない家でも、後からできる対策はあります。既存住宅や中古住宅を購入する際には、まず現状の耐震性能を把握し、必要に応じて補強を施すことが極めて重要です。
>>【耐震等級3の中古住宅】相当とは違う?正しい見極め方と必ず確認すべき書類
耐震性の向上は大規模なリフォームだけではありません。壁の補強や接合金物の追加、基礎の補修など、比較的小規模な工事でも、一定の耐震性改善が可能です。
ただし、補強工事には費用もかかり、建物の状況によって対応方法が異なります。まずはプロによる診断と計画的な工事が必要です。
耐震診断の実施
現在の住宅の耐震性能を数値化し、どの部分が弱点かを明確にします。
補強工事の計画と見積もり
必要な補強内容と費用感を把握し、予算に応じて優先順位を設定します。
公的支援制度の活用
多くの自治体では、耐震診断や補強工事に対する補助金制度があります。
| 補強内容 | 主な工法 | 費用目安(木造住宅の場合) |
| 壁の補強 | 筋交いや構造用合板の追加 | 約10〜30万円/1箇所 |
| 基礎の補修 | クラック補修や無筋基礎の補強 | 約20〜50万円 |
| 屋根の軽量化 | 瓦から金属屋根への変更など | 約100万円前後 |
| 接合部強化 | 金物補強による耐震性向上 | 約10〜20万円/1階全体 |
既存住宅でも「安全な家」に近づく方法は十分にあります。まずは診断から一歩を踏み出し、家族の命と安心を守るための備えを始めましょう。
耐震診断で「知らなかったリスク」に気づく
住宅の外観は美しくても、内側に“構造的リスク”を抱えているケースは少なくありません。それを見つけ出す手段が「耐震診断」です。
耐震診断とは、建物の構造や基礎、接合部、壁量、屋根の重さなどを専門家が調査し、地震に対する安全性を数値で評価する方法です。1981年以前の旧耐震基準で建てられた住宅では、構造上の弱点が放置されていることが多く、早急な診断が推奨されています。
診断結果は、倒壊の可能性をA〜Eランクで示したり、補強が必要な箇所を具体的に示してくれます。そのため、リフォームや耐震補強の計画にも直結しやすいというメリットがあります。
築年数が古い住宅に住んでいる
旧耐震基準の住宅は現行の地震想定に合っていない場合があります。
外観はきれいだが、構造を見たことがない
リフォーム済でも構造補強されていない例があるため、診断は必須です。
地震のたびに揺れ方が気になる
体感と構造の揺れやすさは直結するため、診断で原因を突き止めましょう。
| 判定ランク | 意味 | 取るべき対応 |
| A(倒壊の可能性小) | 安全性が高い | 補強の必要は基本なし |
| B(可能性中) | 一部補強が推奨される | 局所補強などを検討 |
| C(可能性大) | 構造に弱点あり | 早急な補強が必要 |
| D〜E(危険) | 倒壊の恐れが高い | 全面改修・建替検討 |
「何も問題ないと思っていた家に潜むリスク」に気づくことで、命を守るための一歩を踏み出せます。診断費用の一部を補助してくれる自治体も多いため、まずは自治体窓口に相談してみるのもひとつの方法です。
補強すれば安心?費用と効果を正しく理解する
耐震補強は、見えない安心を手に入れるための投資です。しかし、闇雲に工事をしても、効果が十分に発揮されなければ意味がありません。重要なのは、「現状に応じた最適な補強方法」を選び、効果とコストのバランスを見極めることです。
耐震補強にはいくつかの主要な方法があります。
壁の補強
耐力壁の追加や構造用合板の施工により、揺れに対する抵抗力を高めます。
接合部の強化
柱と梁、土台などの接合部に金物を追加して、建物の一体性を高めます。
基礎の補修・補強
クラック補修や無筋基礎への鉄筋補強で、建物を支える力を強化します。
屋根の軽量化
瓦から軽い金属屋根に変更し、重心を下げて転倒リスクを軽減します。
| 補強方法 | 費用目安(30坪木造住宅) | 主なメリット |
| 壁の補強 | 約50〜100万円 | 揺れに耐える構造を確保 |
| 接合部の強化 | 約20〜40万円 | 倒壊の可能性を大幅に低減 |
| 基礎の補強 | 約50〜150万円 | 建物全体の耐力を底上げ |
| 屋根の軽量化 | 約100〜200万円 | 建物の重心を下げ、転倒防止 |
これらの工事は単独でも効果がありますが、診断結果に基づいて組み合わせて行うことが最も効果的です。
多くの自治体で補助金制度が設けられており、補強費用の一部が助成されるケースもあります。
「今すぐ建て替えることは難しい」という家庭でも、段階的な補強で“守れる家”に近づけることは十分可能です。未来の安心をつくる一歩として、補強の選択肢を前向きに検討しましょう。
耐震等級が上がることで変わる未来
家の性能が変わると、その家に住む人の“未来”も変わります。耐震等級が1から3へと上がったとき、得られるのは安全性だけではありません。
まず、「安心して暮らせる」という精神的な安定感は大きな価値です。地震が起きたとき、「この家なら大丈夫」と思えることは、日々の生活の質を高める要因になります。
子どもや高齢者がいる家庭では、「地震後も自宅で暮らし続けられる可能性」が、避難所生活という負担から家族を守ります。そして将来的に住宅を売却する際も、耐震等級3の証明があることで資産価値が評価されやすくなります。
>>「耐震等級3」が家族の未来を守る。地震後も“暮らせる家”の選び方とは
>>【命を守る家】子どもも高齢者も安心「耐震等級3」という最強の備え
>>耐震等級3の家は資産価値が落ちない?売却・賃貸で有利になる理由を徹底解説
| 変化の対象 | 耐震等級3による恩恵 |
| 日常生活の安心感 | 地震への不安が軽減され、精神的ストレスが少なくなる |
| 地震後の生活継続 | 避難不要の可能性が高く、ライフライン復旧まで自宅で過ごせる |
| 家族の健康と安全 | 揺れによる家具転倒や倒壊リスクを最小限に抑えられる |
| 資産価値 | 売却時や賃貸時に高評価、購入希望者の安心材料になる |
| 子どもへの教育的影響 | 防災意識のある家づくりを通じて“安全を考える力”が育まれる |
耐震等級を上げることは、単なる“構造の強化”ではなく、暮らしの質や家族の未来を変える選択肢です。
数
十万円の投資で、何十年もの安心と資産価値を手に入れることができるとしたら、それは「最も費用対効果の高いリフォーム」といえるかもしれません。
選ぶ前に知っておくべき“安心の基準”

住宅を選ぶとき、多くの人が重視するのは価格や立地、デザインといった目に見える要素です。しかし、命を守るという観点から見れば、「見えない性能」である耐震等級こそが最重要項目です。
耐震等級3の家は、大地震でも倒壊しにくく、地震後も住み続けられる構造を持ちます。それだけでなく、保険料やローン金利、税金まで優遇され、長期的な家計にも優しい設計です。
将来的な資産価値や売却時の評価にもつながるため、「今の安心」だけでなく「未来の安心」も得ることができます。
- 家族の命を守るための備えができる
- 経済的にも合理的な選択となる
- 老後まで安心して住み続けられる基盤になる
住まい選びの最初に「耐震等級3」を基準に据えることこそが、後悔のない選択につながります。
>>【耐震等級比較ガイド】等級1・2・3の違いと、あなたに合った選び方
見た目や価格に惑わされず、「本当に安心できる家とは何か?」を、今一度考えてみましょう。そして、家族の未来を守るための住まいを、確かな基準で選んでください。
憧れの大手メーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれる

住宅展示場や完成見学会にいくのは時間もかかるし大変…
そんなときに便利なのが「タウンライフ家づくり」です。
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
気になるメーカーや工務店を選び、希望の間取りや予算を入力するだけ。「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる!
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。

「タウンライフ家づくり」はこんな方におすすめ
- あなただけの間取りと見積もりを無料で手に入れ比較したい
- 営業されるのが嫌、苦手
- 自宅でじっくり信頼できるハウスメーカーを選びたい
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ




