この記事にはプロモーション・広告が含まれています
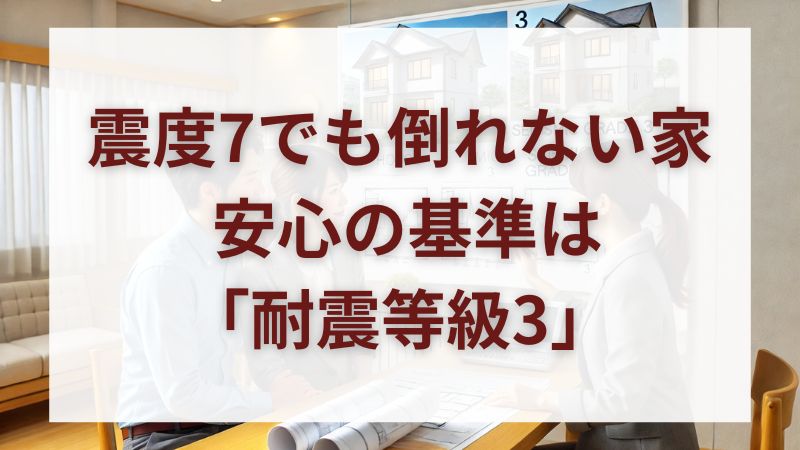
家づくりを考え始めたとき、多くの人が最初に不安に感じるのが「地震への備え」です。日本は地震大国であり、いつどこで大きな揺れが襲ってくるか分かりません。
そんな中で注目されているのが、「耐震等級3」という住宅性能です。これは現行の住宅性能表示制度における最も高い耐震レベルを示しており、地震に強い家づくりを目指す人にとって、大きな安心材料となります。
しかし、「本当に必要なのか?」「コストが高いだけでは?」といった疑問や、「震度7でも倒壊しないって本当?」という不安を抱く方も少なくありません。
この記事では、耐震等級3の性能を震度ごとにわかりやすく解説し、地震時に家族を守るための確かな情報を提供します。耐震等級1・2との比較や、実際の地震における実例なども紹介し、信頼できる選択ができるようサポートします。
初めての家づくりを安心して進めるために、ぜひこの記事を活用してください。
耐震等級3とは?基本から分かりやすく解説

家づくり初心者にとって、「耐震等級」という言葉は耳慣れないかもしれません。ですが、地震の多い日本で安心して暮らすには、この等級を正しく理解しておくことが非常に重要です。
耐震等級は、住宅の耐震性能を数値的に示した指標であり、住宅性能表示制度に基づいて設定されています。耐震等級3はその中で最も高く、「震度7クラスの大地震でも倒壊しない構造を持つ」ことが求められます。
一方で、耐震等級1や2との違いや、認定の基準は一般にはあまり知られていません。ここでは、制度の背景から、具体的な等級の違い、そして耐震等級3が今注目されている理由までを、分かりやすく解説していきます。
住宅性能表示制度における耐震等級の位置づけ
耐震等級は、「住宅性能表示制度」という国が推進する仕組みの中で評価されます。この制度は、住宅の性能を第三者が客観的に評価・表示することで、購入者が安心して家を選べるようにすることを目的としています。
| 評価項目 | 説明内容 |
| 制度の目的 | 購入者が性能を比較しやすくするための表示制度 |
| 評価機関 | 国土交通大臣登録の評価機関が判定 |
| 評価対象 | 構造の安定、劣化の軽減、断熱性能など10分野以上 |
| 耐震等級の位置づけ | 「構造の安定」の中に位置し、構造躯体の強さを示す |
この中でも耐震等級は、地震国・日本において非常に重視される項目です。評価を受けた住宅には、等級を明示するラベルが発行され、売買時の信頼性にもつながります。
耐震等級1・2・3の違いとは?基準と目安を比較
耐震等級は「1」「2」「3」の3段階で評価され、数値が大きいほど耐震性能が高くなります。それぞれの等級が想定する地震の強さと、耐えられる水準は以下の通りです。
| 等級 | 耐震性能の基準 | 想定される被害 |
| 等級1 | 建築基準法レベル(震度6強〜7で倒壊しない) | 最低限の耐震性能。損傷はある可能性がある |
| 等級2 | 等級1の1.25倍の強度 | 学校・病院などに求められる水準 |
| 等級3 | 等級1の1.5倍の強度 | 消防署・警察署と同レベルの構造。被災後も住み続けられる可能性が高い |
等級1は「最低限の安全基準」とされており、大地震時には大きな損傷や補修が必要になるケースもあります。それに対し、等級3は「震災後も暮らしを継続できる強さ」を持つとされ、災害時の避難所と同等のレベルです。
なぜ今「耐震等級3」が注目されているのか
近年、日本各地で頻発する大地震や南海トラフ地震の懸念により、多くの家庭が住宅の耐震性に高い関心を持つようになりました。
被害の甚大さが明らかになった熊本地震(2016年)
多くの住宅が倒壊した一方で、耐震等級3の家はほとんど無被害だったと報告されています。
防災意識の高まりと共働き世帯の増加
子どもや高齢者の安全確保に加え、「地震後も住み続けられる家」が求められるようになっています。
住宅ローン控除や保険料割引の対象
耐震等級3は、地震保険料の割引や税制優遇の対象になることも多く、経済的なメリットもあります。
これらの要因から、単なる「安心感」だけでなく、将来的な価値や経済面でも選ばれる理由が増しているのです。
耐震等級3の実力を震度別に検証

耐震等級3がどれほど信頼できる性能なのかを実感するには、具体的な地震の「震度」と照らし合わせることが有効です。震度ごとに起こりうる被害と、それに対する等級3住宅の耐性を比較することで、より現実的な安心感が得られます。
耐震等級3は、震度7を含む最大級の揺れにまで対応することを想定した構造です。ここでは、震度5強から震度7まで、それぞれの揺れが住宅に与える影響と、等級3住宅がどのように対応するかを詳しく見ていきます。
>>あなたの家、本当に大丈夫?“耐震等級3”が必要な現実とは
震度5強:被害は出る?出ない?住宅に与える影響
震度5強は、家具が大きく動き、固定されていないものが転倒する程度の揺れです。体感としてはかなり強く、初めて経験する人には恐怖を感じるレベルです。
| 項目 | 内容 |
| 人の体感 | 立っていられないことがある。恐怖を感じる。 |
| 建物の影響 | 老朽化した住宅や耐震性の低い住宅では壁や柱に軽微なひび割れが生じる可能性あり |
| 耐震等級3の対応 | 基礎・構造体はほぼ無傷。家具の転倒対策をしていれば、人的被害も回避可能 |
耐震等級3では、この程度の揺れでは「建物構造に目立った損傷が出ることはまずない」とされています。被害を防ぐには、むしろ室内の家具固定や転倒防止が重要です。
震度6弱〜6強:耐震等級3の家はどこまで持ちこたえるか
震度6弱から6強は、建築基準法でも想定されている「大規模な地震」の領域です。家具の多くが倒れ、ドアや窓が変形することもあります。
| 項目 | 震度6弱 | 震度6強 |
| 建物の影響 | 小規模住宅で軽微〜中程度の損傷 | 老朽家屋では倒壊の恐れ |
| 被害の例 | 壁や天井の落下、瓦の崩落など | 大規模な損傷、火災の誘発 |
| 耐震等級3 | 軽微な損傷で居住継続可能 | 柱・梁に変形が起きても倒壊には至らない設計 |
このクラスの揺れでも、耐震等級3の住宅は「構造的に安全」であることが前提となっています。外壁の亀裂や内装材の破損は避けられない場合もありますが、倒壊による生死のリスクを大きく減らすことができます。
震度7:倒壊のリスクは?過去の大地震から見る実例
震度7は、日本の観測史上で最も強い揺れに分類されます。阪神・淡路大震災や熊本地震でも記録され、多くの住宅が全壊・半壊しました。
| 項目 | 内容 |
| 被害の特徴 | 木造住宅では倒壊が多発。火災の発生も |
| 公的想定 | 建築基準法は「倒壊しない」ことが基準(等級1) |
| 耐震等級3 | 消防署・警察署と同等の強度で倒壊リスクは最小限 |
熊本地震(2016年)では、耐震等級3の住宅が繰り返し震度7に見舞われても倒壊しなかった事例が多数報告されました。被害はゼロではないものの、致命的な崩壊を回避できた点で、等級3の性能が実証された形です。
このように、震度別に見た場合でも、耐震等級3はあらゆる規模の地震に対して「命を守る性能」を備えた住宅構造であることがわかります。建物だけでなく、「暮らし」を守るという視点からも、その価値は非常に高いと言えるでしょう。
>>「耐震等級3」が家族の未来を守る。地震後も“暮らせる家”の選び方とは
「震度7でも倒壊しない」は本当か?実例で検証

耐震等級3の最大の売り文句とも言えるのが、「震度7でも倒壊しない」という表現です。しかし、本当にその通りなのでしょうか?このセクションでは、過去の大地震をもとに、等級3の住宅がどれだけの信頼性を持つのかを検証していきます。
実際の被害状況と耐震等級の関係を把握することは、住宅購入時の判断材料として非常に重要です。専門家や居住者の声も交えながら、リアルな視点で性能を見極めましょう。
阪神・淡路大震災・熊本地震に学ぶ耐震性能の限界と可能性
1995年の阪神・淡路大震災では、耐震基準を満たしていたにも関わらず、多くの木造住宅が倒壊しました。当時は、現行の「新耐震基準」導入からまだ年月が浅く、建物の老朽化や地盤条件も倒壊を招いた要因でした。
一方、2016年の熊本地震では、耐震等級3の住宅に対して非常に貴重なデータが得られました。震度7が2度観測されたこの地震では、倒壊や半壊が相次ぐ中、耐震等級3の住宅はほとんどが無事でした。
| 地震名 | 耐震等級3住宅の状況 | その他住宅との比較 |
| 阪神・淡路大震災 | 等級制度導入前のため実績なし | 多数の木造住宅が倒壊 |
| 熊本地震 | 繰り返す震度7にも耐え、倒壊ゼロの報告が多数 | 等級1以下の住宅では倒壊・半壊が多発 |
熊本地震は、「耐震等級3の性能が実地で証明された」非常に重要な事例です。繰り返す激震にも耐え、修繕をほとんど必要としなかった住宅も少なくありませんでした。
ただし、施工不良や設計ミスがあった住宅では例外的に被害が出たケースもあるため、「等級3なら絶対に安全」という過信は禁物です。
実際に耐震等級3の家がどうだったか?専門家・居住者の声
実際に耐震等級3の住宅に住んでいた人たちの証言は、その信頼性を裏付ける生のデータです。地震発生時の様子、被害の有無、住み心地など、住民自身の実感に勝る説得力はありません。
熊本県在住・築5年の等級3住宅に住むAさん
「2回の震度7でも家のゆがみやひび割れはなく、普通に生活を続けられました。隣家は壁が崩れて避難所生活になったので、本当にこの性能にしておいて良かったと思いました」
建築士・構造設計の専門家B氏の見解
「震度7の揺れに対しても耐震等級3の住宅は、構造的に粘り強く崩壊を回避できる設計がなされています。現場でもその通りの結果が出ており、『命を守る家』という点で現実的な選択肢と言えます」
こうした声を総合すると、耐震等級3の家は、現実の災害においても高い信頼性を示していることが明らかです。もちろん、性能を活かすためには、設計段階での構造計算や、正確な施工管理が欠かせません。
つまり、耐震等級3の真価は、設計・施工・実績の三拍子が揃ったときに初めて発揮されるのです。机上の数値だけでは測れない「実力」が、過去の震災によって証明された今、選ばない理由は見当たりません。
耐震等級3の認定に必要な条件とは?

耐震等級3は、単に「丈夫な家」というだけでは認定されません。制度として厳格な基準が設けられており、これをクリアするためには設計・施工の両面で高度な対応が求められます。
ここでは、どのような条件を満たせば耐震等級3の認定が得られるのかを具体的に解説します。家づくりを検討している方が設計事務所やハウスメーカーと話す際に役立つ知識です。
建築基準法との違いと追加の設計基準
耐震等級1は「建築基準法に準拠」した最低限の安全基準であり、震度6強〜7程度の地震で倒壊しないことを想定しています。しかし、耐震等級3はその1.5倍の強度が求められ、「建築基準法を満たすだけでは到達できない水準」です。
| 項目 | 建築基準法(等級1) | 耐震等級3 |
| 設計強度 | 震度6強〜7で倒壊しない | 等級1の1.5倍の地震力に耐える |
| 対象施設 | 一般住宅 | 警察署・消防署などと同等 |
| 対象地震 | 一度の大地震想定 | 繰り返しの大地震にも対応 |
| 設計義務 | 法的必須 | 任意(希望者のみ) |
等級3に到達するには、単なる構造体の強度だけでなく、バランスの良い間取りや適切な壁配置など、総合的な設計力が問われます。
>>【間取り制限は誤解?】耐震等級3でも叶う“自由設計”の家づくり完全ガイド
必須となる施工品質・構造計算のポイント
設計段階で耐震性能が計算されても、施工の品質が不十分であれば意味がありません。耐震等級3では、次のような要件が重要視されます。
壁量と壁配置のバランス
地震力を受け止める耐力壁を適切に配置し、偏りやねじれを防ぐ設計が必要です。
接合部の強化
柱と梁、土台との接合部には金物補強が必須。「力が集中しやすい部分の補強」が建物全体の耐震性を大きく左右します。
基礎構造の安定性
ベタ基礎や鉄筋コンクリートの配筋など、地盤からの揺れに耐える設計が求められます。
許容応力度計算の実施
木造2階建てでも、簡易計算ではなく「許容応力度計算」による構造チェックが行われるのが一般的です。
| 項目 | 詳細内容 |
| 耐力壁 | 計算上の必要量+バランスを確保する配置 |
| 接合金物 | 柱・梁・土台ごとに規定以上の補強を実施 |
| 基礎工事 | 鉄筋量・厚み・地盤との接続を明示 |
| 構造計算 | 構造全体を数値で検証する「許容応力度計算」が推奨 |
このように、耐震等級3の取得には「性能を見せる設計」と「性能を実現する施工」の両立が不可欠です。認定を受けることで、数値化された信頼性と、長期にわたる安心感を得ることができます。
住宅会社選びの際には、耐震等級3の取得実績や施工体制を確認し、「本当に等級3を実現できる会社なのか?」という視点を持つことが重要です。
コストと安心のバランス:耐震等級3は高いだけ?

耐震等級3は高性能である一方、気になるのが「費用がどれくらいかかるのか」という点です。家づくりではコストとのバランスを取ることが欠かせません。
このセクションでは、耐震等級3にかかる費用の目安や、標準仕様との比較、ローコスト住宅でも実現可能なのかという点を整理し、判断材料を提供します。
耐震等級3にかかる費用とその内訳
耐震等級3の住宅は、通常の建築よりも設計・構造・施工の各段階で手間とコストがかかります。構造計算や補強材、施工管理に関わる部分が主なコスト要因です。
| 費用項目 | 概要内容 |
| 設計費用 | 許容応力度計算や構造検討など、詳細設計が必要 |
| 建材費 | 接合金物や補強材など、耐震用部材の増加 |
| 工事費 | 耐力壁や基礎工事における追加作業費 |
| 認定取得費 | 性能表示評価機関への申請・審査料 |
総額としては、一般的な住宅に比べて30万〜80万円程度の追加費用が発生するのが相場とされています(延床30坪程度の木造住宅の場合)。
コスパを考える:標準仕様との価格差と長期的メリット
初期費用は増えるものの、長期的に見ると耐震等級3は「コスト以上の価値」があると言えます。以下は、標準仕様(等級1)との比較です。
| 比較項目 | 耐震等級1 | 耐震等級3 |
| 初期建築コスト | 比較的安価 | 約5〜10%アップ |
| 地震保険料 | 割引なし | 最大50%割引可能 |
| 修繕・補修コスト | 地震後に高額になる可能性あり | 被害が少なく、補修費が抑えられる |
| 資産価値 | 標準水準 | 評価額が高く、売却時にも有利 |
このように、初期コストを少し上乗せするだけで、保険料・修繕費・資産価値の面で将来的なリターンが期待できるのが等級3の魅力です。
ローコスト住宅でも耐震等級3は可能か?
「ローコスト住宅では耐震等級3は無理なのでは?」と考える方も少なくありませんが、結論から言えば可能です。ただし、いくつかの条件と工夫が必要になります。
シンプルな間取りにする
複雑な形状よりも、正方形・長方形に近いシンプルな構造の方が、耐震性を確保しやすくなります。
開口部(窓や扉)を抑える
窓が多いと壁の強度が下がるため、耐震設計が難しくなります。
規格型プランを活用する
ハウスメーカーが提供する等級3対応の規格住宅を選ぶことで、コストを抑えつつ高性能な家が実現可能です。
自社施工+設計対応の業者を選ぶ
設計から施工まで一貫して対応できる工務店は、余計な中間マージンが省けるため、同じ予算でもより高性能な家づくりが可能になります。
このように工夫次第で、「予算重視でも耐震等級3は実現できる」のです。むしろ、限られた予算内だからこそ、「必要な性能にだけお金をかける」という考え方が、賢い選択と言えるでしょう。
耐震等級3を取り入れているハウスメーカーの比較

耐震等級3を実現したいと考えたとき、どのハウスメーカーに相談すれば良いのかは非常に重要なポイントです。各社の対応は大きく異なり、標準仕様としているか、オプション扱いかによって、費用や設計の自由度も変わってきます。
ここでは、耐震等級3に積極的に対応しているハウスメーカーを比較し、選ぶ際の参考になる視点を整理します。
全棟標準で等級3対応のメーカーはどこ?
一部の大手ハウスメーカーでは、「全棟、耐震等級3」を標準仕様としており、高い安全性を重視する姿勢が明確です。こうしたメーカーは、設計や施工における品質管理も徹底されていることが多く、安心して任せられる要素が揃っています。
| メーカー名 | 対応内容 | 特徴 |
| 住友林業 | 標準で全棟等級3対応 | 木造住宅の設計自由度が高い |
| 一条工務店 | 全棟等級3+長期優良住宅対応 | 高断熱・高気密も標準装備 |
| セキスイハイム | 全シリーズで等級3取得可能 | 工場生産で品質が安定 |
| パナソニックホームズ | 鉄骨系住宅で等級3取得 | 耐久性やメンテナンス性にも強み |
これらのメーカーを選ぶことで、「耐震性能を妥協せず、設計自由度やデザイン性も保てる」家づくりが可能となります。費用面ではやや高めになる傾向がありますが、安心・信頼を重視するなら有力な選択肢です。
オプション扱いのメーカーに注意すべき点
一方、標準では等級1または等級2で、希望者にのみ等級3を提供する「オプション扱い」のメーカーも少なくありません。こうした場合には、事前に確認しておきたい注意点があります。
オプション料金の有無と相場を確認
等級3にするには追加設計費や補強工事が必要となり、数十万円の費用が加算されることがあります。
プラン変更の制約が出る場合がある
等級3の取得条件を満たすために、窓のサイズや部屋の位置を調整する必要が出る場合があります。
耐震等級の評価方法をチェック
「自社基準」として等級3をうたうケースもあるため、住宅性能表示制度による第三者評価であるかを必ず確認しましょう。
相談時に聞くべきチェックポイント
「等級3は取得可能か?」「構造計算は実施しているか?」「取得費用はいくらかかるか?」など、あらかじめ質問リストを用意しておくと安心です。
| 確認ポイント | 内容 |
| 評価方法の確認 | 第三者機関の表示制度に基づく等級3か |
| 費用の透明性 | オプション費用や構造計算費の内訳 |
| 設計制限の有無 | プラン選択時に耐震性が制約される可能性 |
等級3を「確実に」取得したい場合は、こうした点を踏まえて信頼性と透明性の高いメーカーを選ぶことが不可欠です。
結果として、等級3にこだわるのであれば、初めからその対応力を持ったメーカーを選ぶのが、費用面・設計面・安心面すべてでバランスの良い選択と言えるでしょう。
よくある誤解と不安を解消!耐震等級3のQ&A

耐震等級3は非常に高性能ですが、その分さまざまな誤解や疑問もつきまといます。ここでは、家づくりの現場でよくある質問をQ&A形式で整理し、安心して選べるよう疑問を解消します。
「地震保険は不要になる?」という誤解
耐震等級3を取得していても、地震保険は依然として重要です。
地震保険は建物が全壊・半壊・一部損壊した場合の損害を補償する制度です。等級3の住宅でも、外装や内装に被害が出ることはあり得るため、保険に加入する意義は十分にあります。
ただし、耐震等級3を取得している住宅では最大で50%の地震保険料割引が適用されるため、経済的負担を軽減しながら備えることができます。
| 項目 | 内容 |
| 加入義務 | 任意(住宅ローンによっては必須) |
| 等級による割引 | 等級1:割引なし/等級3:最大50%割引 |
| 補償範囲 | 倒壊以外にも修繕費用や家財損害など |
つまり、「耐震等級3だから保険は不要」ではなく、「耐震等級3だからこそ、保険も安く万全の備えができる」と考えるのが正解です。
「耐震等級3なら絶対安全?」の落とし穴
耐震等級3は非常に高性能であることは間違いありませんが、「絶対安全」ではないという点を正しく理解しておく必要があります。
>>耐震等級3は完璧じゃない?誤解しがちな10の落とし穴と正しい対策
- 想定を超える地震動が発生した場合には、どんな住宅も損傷を免れない可能性があります。
- 地盤の弱さや液状化、津波など、建物構造以外のリスクも存在します。
- 設計どおりに施工されていなければ、等級3の性能は発揮されません。
つまり、等級3はあくまで「現在の技術で想定できる最大級の地震に備えるもの」であり、過信せず正しく理解し、日頃の備えも並行して行うことが重要です。
>>耐震等級3でも倒壊リスク?見落としがちな落とし穴と安全に守る対策
「中古住宅でも等級3にできる?」
中古住宅に対しても耐震改修やリノベーションで性能を向上させることは可能ですが、耐震等級3の取得はかなりハードルが高いのが現実です。
>>【耐震等級3の中古住宅】相当とは違う?正しい見極め方と必ず確認すべき書類
| 項目 | 内容 |
| 必要な条件 | 基礎・構造の状態が良好であること |
| 改修方法 | 壁量の増加、接合部の補強、構造計算の再実施など |
| 費用目安 | 100万円〜300万円以上になることもある |
既存の構造体が等級3に対応していない場合、大規模な補強工事や間取り変更が必要となり、費用が新築に近づく可能性もあります。
そのため、中古住宅を購入して等級3を目指す場合は、事前に専門家の診断を受けて可否と費用感を把握することが欠かせません。現実的には、新築時に等級3を確保する方が効率的かつ確実です。
どんな人に耐震等級3は向いているのか?

耐震等級3はすべての人にとって有益な性能ですが、「このタイプの人には強くおすすめできる」という具体的なイメージがあります。ここでは、ライフスタイルや価値観別に、耐震等級3がフィットする人物像を紹介します。
家族の安全を最優先する人
小さな子どもや高齢の親と同居している家庭
地震が起きた際、自力で避難が難しい家族がいる場合、倒壊のリスクを最小限に抑える耐震等級3の家は、命を守る最後の砦になります。
共働きで家を空ける時間が長い家庭
不在時の地震に備えて、「倒れない家」にしておくことが家族の安心感につながります。
災害後もそのまま住み続けたいと考える人
避難所生活を避けるために、自宅の耐震性能を高めたいと考える人にも最適です。
>>【命を守る家】子どもも高齢者も安心「耐震等級3」という最強の備え
将来の資産価値を重視したい人
住宅の売却や相続を視野に入れている人
耐震等級3は住宅の性能評価として明記されるため、将来的な売却時に「資産としての優位性が高まる」という大きなメリットがあります。
長く住み続けることを前提とした家づくりを考えている人
長期にわたって安心して住める家を手に入れたい人にとって、耐震等級3はコストパフォーマンスの高い選択肢です。
住宅ローン控除や保険料割引など、制度面のメリットを活用したい人
耐震等級3は、地震保険料の割引対象になり、長期優良住宅の認定条件の一部でもあります。
ハザードマップでリスクが高い地域に住む人
南海トラフ地震の想定震源域に居住している人
地震発生のリスクが高い地域に住んでいる場合、高い耐震性能が必要不可欠です。
過去に地震被害を受けた経験がある人
再発を恐れる声も多く、より安心できる住まいを求める人にとって、耐震等級3は信頼の証になります。
地域の地盤が軟弱なエリアに住んでいる人
揺れが大きく増幅される可能性があるため、住宅の耐震性を高めておく必要があります。
このように、耐震等級3は「命を守る安心」だけでなく「将来の資産価値」や「地域のリスク対策」にもつながる選択肢です。誰もが恩恵を受けられますが、不安要素が多い家庭ほど、優先して導入を検討すべき価値があります。
>>【南海トラフ・首都直下地震に備える】高リスク地域にこそ「耐震等級3」の家を建てる理由
安心して家を建てたいなら、まずは“耐震等級3”を基準に考えよう

住宅の耐震性能は、命と暮らしを守る「最後の砦」です。日本のように地震が頻発する国では、住まい選びにおいて耐震性能は最優先すべき項目の一つといえます。
耐震等級3は、現行制度において最も高い耐震基準であり、震度7クラスの地震にも倒壊しない構造を備えています。数々の大地震においてその信頼性は実証されており、「ただ生き残る」だけでなく「住み続けられる住宅」を実現する性能水準」と評価されています。
費用面で不安を抱く方もいるかもしれませんが、初期投資以上に、地震保険料の割引や資産価値の維持、被災後の修繕コスト軽減といった「将来への安心という形で確かなリターン」が得られます。
>>耐震等級3の家は資産価値が落ちない?売却・賃貸で有利になる理由を徹底解説
設計や施工の段階でしっかりと耐震等級3を実現できるパートナーを選ぶことも重要です。信頼できるハウスメーカーや工務店との出会いが、安心の第一歩となるでしょう。
>>耐震等級3の家は“信頼できる施工会社”で!悪質業者に騙されない見極め術
今の家族を守るため、そして未来の自分を守るために。家づくりを始めるその時こそ、「耐震等級3」を基準に考えてみてください。それが、後悔のない選択へとつながります。
憧れの大手メーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれる

住宅展示場や完成見学会にいくのは時間もかかるし大変…
そんなときに便利なのが「タウンライフ家づくり」です。
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
気になるメーカーや工務店を選び、希望の間取りや予算を入力するだけ。「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる!
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。

「タウンライフ家づくり」はこんな方におすすめ
- あなただけの間取りと見積もりを無料で手に入れ比較したい
- 営業されるのが嫌、苦手
- 自宅でじっくり信頼できるハウスメーカーを選びたい
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ




