この記事にはプロモーション・広告が含まれています
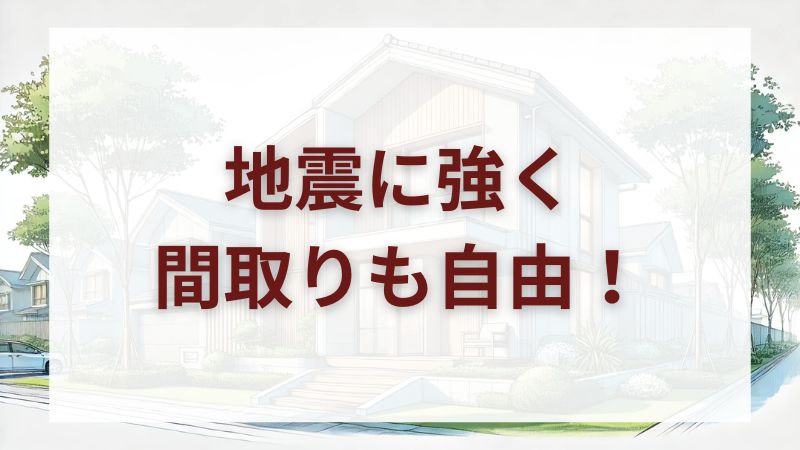
地震が頻発する日本において、住まいの耐震性能は住宅選びの最優先事項とされています。中でも「耐震等級3」は、最も高い耐震性能を示す指標として、多くの家庭が注目する基準です。
>>【南海トラフ・首都直下地震に備える】高リスク地域にこそ「耐震等級3」の家を建てる理由
一方で、「耐震等級3を取得するためには、間取りに大きな制限が出るのでは?」と不安に思う人も少なくありません。リビングを広くしたい、吹き抜けを取り入れたい、趣味の部屋を確保したいといった理想の間取りが、安全性のために犠牲になるのではという懸念です。
しかし、現代の建築技術と設計手法の進化により、耐震等級3の性能を維持しながらも、自由度の高い間取りを実現することが可能になっています。
耐震性と住まいの快適性は、決してトレードオフの関係ではありません。理想の暮らしを叶えつつ、安全性もしっかり確保できる住まいづくりのヒントをお届けします。
耐震等級3とは?基礎知識とその意義

理想の住まいを建てるにあたり、安心して暮らすための基準として注目されているのが「耐震等級3」です。この等級は、住宅の耐震性能を客観的に示す指標であり、家族の安全を第一に考える方にとっては重要な判断材料となります。
>>「耐震等級3」が家族の未来を守る。地震後も“暮らせる家”の選び方とは
>>【命を守る家】子どもも高齢者も安心「耐震等級3」という最強の備え
耐震等級の意味と、なぜ等級3が推奨されるのかを正しく理解することは、間取りを考える前提として非常に重要です。
耐震等級の定義と各等級の違い

日本の建築基準法では、住宅の耐震性を「耐震等級1~3」の3段階で評価します。以下の表は、それぞれの等級の違いを簡潔にまとめたものです。
>>【耐震等級比較ガイド】等級1・2・3の違いと、あなたに合った選び方
| 等級 | 耐震性能の目安 | 主な特徴 |
| 等級1 | 建築基準法に定められた最低限の耐震性 | 震度6強~7程度の地震で倒壊・崩壊しない |
| 等級2 | 等級1の1.25倍の耐震性能 | 学校・病院など災害時にも使用される施設と同程度 |
| 等級3 | 等級1の1.5倍の耐震性能 | 消防署や警察署など、防災拠点と同水準の強度 |
等級3は、震度7の大地震に繰り返し耐えられる設計基準であり、極めて高い安全性を実現します。
このため、等級3は「長期優良住宅」の条件としても求められ、将来的な資産価値を見据えるうえでも大きなメリットがあります。
>>【保存版】耐震等級3の実力とは?震度5〜7での性能を徹底検証
等級3が求められる具体的なケース

以下のような住宅計画では、耐震等級3の取得が推奨または必須となることがあります。
長期優良住宅を取得したい場合
税制優遇や住宅ローン控除を最大限活用するための要件の一つです。
住宅性能表示制度の活用を考えている場合
耐震等級は「構造の安定」の指標として評価対象となります。
金融機関から住宅ローンを有利に借りたい場合
耐震等級3を取得していることで、金利優遇や審査上の評価に有利になるケースがあります。
地震保険の保険料を抑えたい場合
等級3取得により、保険料の大幅な割引が受けられることもあります。
このように、耐震等級3は単に「安心」のためだけでなく、経済的なメリットや住宅の資産価値を高める意味でも非常に有効です。今後長く住む家だからこそ、安全性と価値を両立できる住宅性能は重要視されます。
>>耐震等級3の家は資産価値が落ちない?売却・賃貸で有利になる理由を徹底解説
耐震等級3と間取り設計の関係性

耐震等級3の住宅は、非常に高い耐震性を誇りますが、その性能を実現するためにはいくつかの構造的な制約が伴います。間取りに関して、「自由に設計できないのでは?」と懸念する声もあります。
しかし、構造的な要件を理解し、それに応じた設計手法を採用することで、安全性と間取りの自由度を両立させることは十分に可能です。
構造上の基本的な制約とその理由

耐震等級3を満たすには、建物全体のバランスと強度を高める必要があります。そのため、以下のような構造上の配慮が必要とされます。
耐力壁の配置バランス
耐震性を確保するためには、建物の四隅や中心部など、要所に耐力壁を設置する必要があります。
筋交い(すじかい)の設置
筋交いは、壁面に斜めに取り付ける構造材で、地震による横揺れに対抗する役割を果たします。
上下階の形状の一致
1階と2階の壁・柱の位置をある程度揃えることで、構造上の負担が均等になり、耐震性が向上します。
吹き抜けや大開口の制限
空間を開放的にする設計要素は、構造的な剛性を弱める場合があるため、補強設計とセットで考慮が必要です。
これらの要件は、建物が大きな地震に見舞われた際にも、構造が崩れないように設計するために不可欠です。
耐震等級3における間取りの自由度に関する誤解
耐震等級3の家は「自由な間取りができない」という印象を持たれがちですが、それは設計の工夫や技術の進化により、過去の話になりつつあります。
構造計算による自由度の確保
許容応力度計算などの構造計算を活用することで、壁や柱の配置を最適化しながら間取りの自由度を広げることができます。
高強度建材の活用
耐震性を確保するための壁を減らす代わりに、強度の高い材料を用いることで、開放感ある空間が実現可能です。
スキップフロアや吹き抜けも工夫次第で可能
必要な位置に補強を施せば、吹き抜けやスキップフロアのある間取りも耐震等級3を満たすことができます。
「耐震性と間取り自由度は両立できない」という思い込みは、現在の技術や設計ノウハウにおいては当てはまりません。
正しい知識と経験を持つ設計士との連携によって、理想の住まいづくりが可能になります。
耐震等級3の間取りの自由度を高めるための設計

耐震等級3の住宅において、設計の自由度を確保するには、構造上の制約を踏まえたうえで、意図的に「柔軟な設計戦略」を採用することが鍵となります。ここでは、間取りの自由度を高めながら、耐震性能も担保するための基本的な戦略を紹介します。
>>耐震等級3は完璧じゃない?誤解しがちな10の落とし穴と正しい対策
構造グリッドの適切な設定
構造グリッドとは、柱や壁など構造要素を配置するための「見えない設計上の基準線」のことです。このグリッドを計画的に設計することで、空間の使い方や自由度に大きな影響を与えます。
間取りのバランスを保ちながら、構造を安定させる
グリッドに基づいて柱や耐力壁を配置すれば、建物のねじれや偏りを防ぎ、構造的な安定を確保できます。
自由な間取りを阻害しない基盤となる
規則性のあるグリッドを設定することで、間仕切りの位置に柔軟性が生まれ、開放的な空間設計が可能になります。
直下率の最適化

直下率とは、2階部分にある柱や壁が、1階部分とどれだけ一致しているかを示す割合のことです。この数値が高いほど、建物の重心が安定し、地震に強くなります。
| 用語 | 内容 |
| 直下率 | 上下階の壁・柱の位置の一致度を示す指標(%) |
| 理想的な数値 | 壁直下率60%以上、柱直下率50%以上が目安 |
直下率が高い=構造バランスが良い
耐震性を確保しやすくなるだけでなく、吹き抜けや大開口を設ける余地も生まれます。
構造計算と併用して設計の自由度を確保
高い直下率を前提とした設計なら、他の部分に開放感を持たせる余裕が生まれます。
スケルトン・インフィル工法の採用
「スケルトン(構造)とインフィル(内装)」を分離して考える設計手法で、構造体と間仕切りを独立して扱えるのが特徴です。将来的な間取り変更や用途変更にも柔軟に対応できる設計が可能になります。
将来的なリフォームにも対応しやすい
家族構成の変化やライフスタイルの変化にも適応できる家づくりが可能です。
構造体に影響を与えず、間取りを変えられる
耐震性を損なわずに内部空間の柔軟性を保てるため、自由度の高い設計を実現できます。
これら3つの戦略は、耐震等級3という高性能住宅を成立させる上での設計基盤となるものであり、設計初期段階からの検討が不可欠です。
計画的な設計こそが、自由な間取りと安心の住まいを両立させる最大のポイントです。
耐震等級3を維持しつつ間取り自由度を実現するテクニック

設計戦略だけではなく、現場レベルでの具体的な設計テクニックも重要です。ここでは、耐震性能をしっかりと維持しながら、間取りの自由度や開放感を高めるための実践的な工夫を紹介します。
外周部での耐震性確保と内部空間の開放

耐震壁や柱などの構造要素を建物の外周に集中させることで、内部に自由な空間をつくることが可能になります。
外周部に耐力壁を集中配置する
建物の外側に強度を集めることで、内側に柱や壁を設けずに広い空間を確保できます。
内部の構造を最小限に抑える設計
壁を減らし、開放的なLDKや回遊性のある間取りが実現しやすくなります。
この設計手法は、開口部の配置や動線計画の自由度を高める効果もあります。
吹き抜けや大開口部の設計ポイント
吹き抜けや大開口部は、空間の明るさや広がりを生む一方で、構造的な弱点にもなりかねません。以下のような配慮が必要です。
| 項目 | 設計のポイント |
| 吹き抜けの大きさ | 2階床面積の1/4程度までに抑えるのが一般的 |
| 大開口部の補強 | 鉄骨梁や集成材、耐震フレームで補強 |
| 耐力壁の配置 | 吹き抜けの両側や四隅に耐力壁を配置するのが基本 |
構造計算でバランスを取ることが前提
吹き抜けと耐力壁の配置バランスは、計算に基づいて慎重に判断する必要があります。
意匠性と耐震性の両立を意識する
ガラス面や照明などで意匠的な工夫を施すことで、構造上の制約を感じさせない設計が可能になります。
スキップフロアやステップフロアの活用
段差を活かして空間を緩やかに分ける「スキップフロア」「ステップフロア」は、限られた面積でも立体的な広がりを演出できます。ただし、耐震性への配慮も必要です。
構造的な一体感を保つための連結設計
スキップフロア部分は、下階や上階と構造的につながっている必要があります。
補強材や水平構面の確保
中間階に梁や剛床(ごうゆか)を設けることで、揺れに強い構造に仕上げることができます。
収納や視線誘導で効果的に
スキップ下を収納スペースとして活用するなど、機能的にも無駄のない設計が可能です。
このように、建物の構造と設計意図をすり合わせた具体的な工夫を施すことで、耐震等級3の制約を逆手に取った魅力的な空間づくりが実現できます。
耐震等級3で実現できる多彩な間取りアイデア

ここでは、実際に耐震等級3を取得しながらも、デザイン性や快適性を追求した住まいの事例を紹介します。いずれも工夫次第で「耐震性と自由な間取りの両立」が可能であることを示す好例です。
開放感も安心も両立する、30坪のスマートプラン

延床約30坪の2階建てで、1階はLDKと水回りを集約し、生活動線をコンパクトに。2階には個室3部屋とバルコニーを配置しています。LDKの上部を大きく吹き抜けにすることで、コンパクトながらも開放的な空間に仕上がっています。
耐震性を意識しながらも、日々の生活がしやすく、気持ちよく過ごせる住まいをイメージしました。
関連記事:【間取りあり】吹き抜け×耐震等級3で叶える、家族がもっとつながる家づくり
ガレージと庭を両立した、アウトドア派に嬉しい住まい

延床約34坪の2階建て。1階には洋室と書斎、水回りとビルトインガレージを配置し、2階はLDKと個室が中心の構成。車や趣味、庭仕事といった“外の時間”と、“内の暮らし”が自然に溶け合うプランになっています。
ビルトインガレージを軸に、裏手には広めのデッキとアプローチガーデンを配置。外からの動線と家の中のつながりが滑らかになるように意識しました。
関連記事:【間取りあり】雨の日もBBQも地震対策も!ビルトインガレージ(インナーガレージ)×耐震等級3の家
耐震等級3を前提とした理想の間取りを叶えるための設計・施工パートナーの選び方

間取りの自由度と耐震性を両立するためには、設計や構造に強いプロフェッショナルと組むことが不可欠です。ここでは、住宅の完成度を大きく左右する「設計者」や「ハウスメーカー」の選び方を詳しく解説します。
設計力のある建築士・設計事務所の見極めポイント
構造とデザインの両立が得意かを確認
単に見た目のデザインが得意なだけではなく、構造計算に強く、耐震性を理解したうえで提案できる設計者を選ぶ必要があります。
構造設計士との連携体制があるか
建築士が一人で全てをカバーするのではなく、構造専門家とチームを組んでいるかどうかが、設計の完成度に影響します。
過去の実績や事例をチェック
耐震等級3で実現した自由な間取りの実例があれば、その経験値は信頼に値します。
設計段階での技術力と柔軟性が、理想の住まいを実現する最大の武器となります。
ハウスメーカー選びで注目すべき3つの視点
ハウスメーカーを選ぶ際には、以下の3点を必ずチェックしてください。
| チェック項目 | 見るべきポイント |
| 構造計算の体制 | 自社で許容応力度計算を実施しているか、外注かどうか |
| 耐震等級3の実績 | 耐震等級3の住宅を数多く手がけた経験があるか |
| 間取り提案の柔軟性 | 狭小地や吹き抜け、大開口の設計実績があるか |
大手であっても構造計算を外注していたり、自由設計に制限が多かったりする会社もあります。担当者の説明だけでなく、実例を見ながら判断することが大切です。
初回相談前に整理しておくべき要望・条件リスト
理想の間取りを設計士に正確に伝えるためには、自分自身の要望を事前に整理しておくことが重要です。
開放感を持たせたい空間
リビング、ダイニング、玄関など、どこに広さを求めるかを明確にしましょう。
将来的な間取り変更の有無
二世帯化や子どもの独立を見据えた可変性の希望を伝えましょう。
家族構成と生活動線の把握
子育て世帯や共働き家庭では、家事動線や収納動線の工夫が重要です。
事前に要望を明確にしておくことで、設計者との打ち合わせがスムーズに進み、納得のいく提案を受けやすくなります。
間取りの自由度を叶えるための打ち合わせ時のチェックリスト
打ち合わせ時には、以下のようなポイントを必ず確認しましょう。
- 吹き抜けや大開口に対して、構造面からの対策提案があるか
- 直下率や構造グリッドを考慮したプランか
- 建材の自由な選定に対応してくれるか
- 設計変更に柔軟に対応してくれるか
資料請求・見学時のコツ:実例から読み取る「設計自由度」
パンフレットの間取り事例を要チェック
間取りが画一的でないか、柔軟性が感じられるかを見極める材料になります。
モデルハウスや見学会で確認すべきポイント
吹き抜け、スキップフロア、大開口、耐力壁の配置、構造部材の見せ方など、構造とデザインのバランスに注目しましょう。
信頼できるパートナーとの出会いが、満足度の高い家づくりを左右します。慎重に、かつ主体的に情報を集めてください。
>>耐震等級3の家は“信頼できる施工会社”で!悪質業者に騙されない見極め術
耐震等級3に対応した主なハウスメーカー比較と選び方のポイント

注文住宅を建てる際、耐震性と間取りの自由度を両立させたい方にとって、どのハウスメーカーを選ぶかは非常に重要な判断材料です。耐震等級3の取得には、高度な構造設計や施工技術が求められるため、各社の特性を比較しておくことが大切です。
まずは、主要ハウスメーカーの対応状況を一覧で確認しましょう。
| ハウスメーカー名 | 主な構造方式 | 構造計算体制 | 設計自由度 | 特徴・備考 |
| 住友林業 | ビッグフレーム構法(BF) | 自社構造専門部門あり | 高い | 木造でも大開口や吹き抜けを実現できる独自工法。自由設計と高耐震性の両立が可能。 |
| セキスイハイム | ユニット工法(鉄骨・木質) | 工場製造+構造試験に強み | 中〜高 | 工場生産による精度の高さと高耐震性が魅力。間取りはやや制限されるが品質が安定。 |
| ミサワホーム | 木質パネル接着工法 | 許容応力度計算対応 | 中程度 | 独自の高耐震技術「センチュリーモノコック構法」。空間活用に優れた収納提案が特徴。 |
| 一条工務店 | 外内ダブル断熱+木造軸組 | 自社独自計算システム | やや低め | 高断熱・高気密住宅に強く、性能重視。自由設計の幅はやや限定される傾向。 |
| 積水ハウス | 鉄骨系:ダイナミックフレーム構造 | 社内構造設計チームあり | 高い | 耐震性能に加えデザイン性・自由度の高さが魅力。価格帯は高めだが総合力が高い。 |
| タマホーム | 木造軸組+モノコック構造 | 外注(構造計算書取得可) | 中〜高 | コストパフォーマンスに優れ、耐震等級3対応も可能。自由設計に柔軟に対応。 |
住友林業:木の魅力と構造性能を両立
「BF(ビッグフレーム)構法」により、高い耐震性と大空間設計を両立させています。木造で吹き抜けや大開口が可能なのは大きなメリット。耐震等級3取得も標準化されており、構造設計も自社で対応。
セキスイハイム:工場生産による高精度と高耐震
鉄骨系のユニット工法を採用し、工場で構造体を精密に製造することで耐震性を確保。標準仕様で耐震等級3に対応しており、住宅性能表示制度にも積極的。設計は規格的要素もあるが品質は安定。
ミサワホーム:収納空間と高耐震を両立
独自の「木質パネル接着工法」によって、地震への強さと空間提案の柔軟性を両立。蔵収納やスキップフロアなど、空間の使い方に特徴あり。耐震等級3取得にも積極的に対応しています。
一条工務店:性能重視派におすすめの高性能住宅
断熱・気密性能に特化した住宅づくりが特徴。標準で耐震等級3を取得できますが、設計はパターン化されており、自由度はやや低め。性能とコストバランスを重視する層に支持されています。
積水ハウス:自由設計と高耐震を両立する大手総合力
鉄骨構造を中心に、自由設計でありながら耐震等級3もクリアするバランス型のメーカー。設計自由度が高く、デザイン性も優れており、都市型の注文住宅でも柔軟に対応可能です。
タマホーム:コスパ重視で耐震等級3も可能
コストパフォーマンスが高く、自由設計も可能な木造軸組構法を採用。構造計算は外注ですが、耐震等級3にも十分対応可能。比較的若い層やローコスト住宅を検討する方に人気。
このように、ハウスメーカーごとに得意分野や対応力には違いがあります。「設計自由度」「構造性能」「価格帯」「デザイン志向」など、自分たちの希望条件を整理して比較することが大切です。
住宅展示場や完成見学会で実物を確認し、設計士や担当者と直接話をすることで、より具体的な判断材料が得られるでしょう。
耐震等級3対応のハウスメーカー・設計事務所の選び方

自由な間取りと耐震性能を両立させる住宅を実現するには、どのような企業や専門家と家づくりを進めるかが非常に重要です。ここでは、パートナー選びの具体的なポイントを解説します。
施工実績と技術力の確認ポイント

ハウスメーカーや設計事務所の中には、見た目のデザインに強い会社もあれば、構造設計に特化した会社もあります。重要なのは、「耐震等級3を取得しながら柔軟な間取り提案ができるかどうか」です。
| 確認項目 | 内容 |
| 実績数 | 耐震等級3の取得実績が豊富かどうか |
| 技術対応力 | 許容応力度計算や高強度建材への対応力があるか |
| プランの柔軟性 | 間取り変更に柔軟に対応する実績があるか |
設計・施工実績がある=ノウハウが蓄積されている
過去に似た要望に対応した経験があるかが、設計自由度の高い家づくりを可能にします。
技術力の裏付けは構造計算書や施工事例で判断
ただ話を聞くだけでなく、図面や資料を見て確認しましょう。
設計士との連携とコミュニケーションの重要性
理想の間取りを実現するには、施主の要望を設計士が正確に理解し、構造面とのバランスを取りながら提案できる力が求められます。
希望を言語化することが大切
「開放感がほしい」「家事動線を重視したい」など、言葉で明確に伝えることが、設計士の提案精度を高めます。
提案力と聞く力を持つ設計士を選ぶ
要望を引き出してくれる、対話力のある設計士が理想です。
信頼関係の構築が家づくりの成功を左右する
意見交換がしやすい雰囲気、質問に丁寧に答えてくれる姿勢があるかを初回面談で見極めましょう。
構造と間取り、両面からの最適解を導ける設計士こそ、理想のパートナーです。
時間をかけて信頼できる相手を見つけることが、満足度の高い住まいへの第一歩となります。
よくある質問Q&A

耐震等級3と間取りの自由度に関する疑問でまとめました。
Q1. 吹き抜けを設けても耐震等級3は取得可能か?
はい、可能です。ただし、吹き抜けを設けることで建物の上下のバランスが崩れやすくなるため、構造計算による補強が必要になります。
- 耐力壁の配置や水平構面の強化を行えば、吹き抜けのある設計でも耐震等級3は取得可能です。
- 天井の開放感と明るさを活かしつつ、安全性を両立させるには、設計段階からの構造検討が欠かせません。
設計の工夫次第で、吹き抜け空間を楽しみながら高い耐震性も手に入れられます。
Q2. 将来的な間取り変更は耐震性に影響するか?
間取り変更によって、耐震性が損なわれる可能性はあります。耐力壁や柱を撤去・移動するリフォームは要注意です。
- 安易な間仕切りの撤去は、構造バランスを崩す原因となることがあります。
- 将来を見据えて、スケルトン・インフィル工法や可動式間仕切りなどの採用がおすすめです。
事前に構造に配慮した設計を行っておくことで、将来のリフォームにも柔軟に対応できます。
Q3. 耐震等級2では不十分なのか?
耐震等級2も一定の耐震性を有しており、学校や病院などの公共施設でも採用されています。ただし、住宅における最も高い等級は3であり、将来的な価値や安心感を求めるなら、等級3の取得が推奨されます。
>>「耐震等級3は過剰」という声の真実|住宅選びに失敗しない知識と判断方法
| 等級 | 対応レベル | 主な使用例 |
| 等級1 | 最低基準 | 一般的な戸建住宅(基準法レベル) |
| 等級2 | 等級1の1.25倍 | 学校・避難所などの公共施設 |
| 等級3 | 等級1の1.5倍 | 消防署・警察署・防災拠点レベルの耐震性 |
地震大国である日本において、等級3の家は家族の安心を守る最上級の備えとなります。
>>あなたの家、本当に大丈夫?“耐震等級3”が必要な現実とは
Q4. 平屋と二階建てで間取り自由度に差はあるか?
基本的には、平屋のほうが構造的にシンプルで、間取りの自由度は高い傾向にあります。上下階の直下率を考慮する必要がないため、構造の自由度が大きくなります。
- 平屋は、耐力壁の配置が比較的自由で、開放的な設計がしやすいのが特徴です。
- ただし、敷地の広さが求められるため、土地条件によっては2階建てが有利な場合もあります。
耐震等級3を取得するうえでは、平屋も2階建ても十分に対応可能です。要望に応じた構造計画がカギとなります。
ま安心も理想も叶える、耐震等級3で自由な間取りをつくろう

耐震等級3という最上級の耐震性能を備えながらも、間取りに制約を感じることなく自由な住まいづくりを実現することは、決して夢ではありません。構造と設計のバランスを取りながら、適切な工夫を凝らすことで「安全性と快適性の両立」が可能になります。
本記事で紹介したように、構造グリッドや直下率の工夫、スケルトン・インフィル工法の活用、外周耐力壁の配置など、実践的なテクニックを活用することで、デザインの幅は大きく広がります。
信頼できる設計・施工パートナーと出会い、希望を的確に伝えることで、理想の暮らしに近づくことができます。事前の情報収集と整理、見学や打ち合わせの工夫が、家づくり成功の大きな一歩となるでしょう。
憧れの大手メーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれる

住宅展示場や完成見学会にいくのは時間もかかるし大変…
そんなときに便利なのが「タウンライフ家づくり」です。
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
気になるメーカーや工務店を選び、希望の間取りや予算を入力するだけ。「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる!
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。

「タウンライフ家づくり」はこんな方におすすめ
- あなただけの間取りと見積もりを無料で手に入れ比較したい
- 営業されるのが嫌、苦手
- 自宅でじっくり信頼できるハウスメーカーを選びたい
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ




