この記事にはプロモーション・広告が含まれています
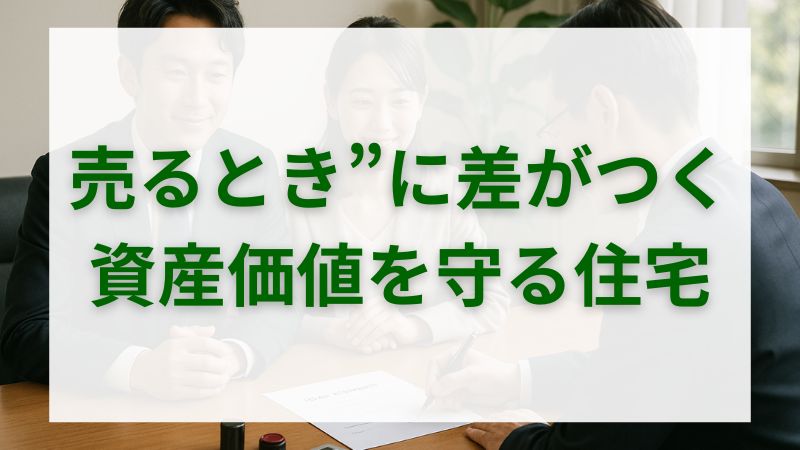
このトピックでわかること
- 購入後に後悔しない家を建てたい方におすすめ
- 耐震等級3が資産価値や売却価格にどう影響するかがわかる
- 損をしにくい家を建てるための判断基準が身につく
「耐震等級3」と聞いて、「地震に強い家」「安心・安全な構造」といったイメージを思い浮かべる方は多いでしょう。もちろん、それは事実です。しかし、それだけではありません。この“住宅性能”は、将来の資産価値やローンの残り方にも深く関係しています。この視点は、まだ広く知られていないのが実情です。

住宅性能が“売るときの価値”にも影響します。
たとえば10年後、転勤や家族構成の変化によりマイホームを手放すことになったとします。そのとき、「今の家はいくらで売れるか?」「売却後にローンが残らないか?」といった問題に直面する可能性があります。実はこうした場面で、住宅の“見えない性能”が売却価格に大きな影響を与えます。
この記事では、「耐震等級3」というスペックが、どのように“売却で損をしにくい家”につながるのかを詳しく解説します。資産価値・査定評価・制度の優遇・保険料・残債リスクといった要素を、具体的な数値や制度とともにわかりやすく整理し、購入前に押さえておきたい判断基準として紹介します。
「せっかく家を建てるなら、将来の安心まで考えた選択をしたい」。そう考える方にこそ、知っておいてほしい内容です。

300万円の差額実績あり
あなただけのオリジナルプランを今すぐ手に入れる
新築・中古戸建も比較してみたい
【PR】タウンライフ
耐震等級3の家は売却時の資産価値下落を防げる

このトピックでわかること
- 購入後に後悔しない家を建てたい方におすすめ
- 耐震等級3が資産価値や売却価格にどう影響するかがわかる
- 損をしにくい家を建てるための判断基準が身につく
マイホームの購入では、「住み心地」や「立地の便利さ」を重視する方が多い一方で、将来その家を売るときにどう評価されるかという視点は見落とされがちです。
耐震等級3の家は、ただ地震に強いというだけではありません。中古住宅市場で価格が下がりにくく、ローン残債とのバランスもとりやすい住宅でもあります。ここではその理由を、実例や制度を交えて紹介します。

地震に強いだけでなく、資産としても強い家です。
耐震性能の高さが中古住宅価格の維持に直結する

中古住宅市場では、築年数や立地に加えて、「住宅の性能」が価格に大きく影響します。大きな地震がたびたび起こる近年は、耐震性能が重視されることが多いです。
購入を検討する人にとって、「地震に強い家=安心できる家」であり、耐震等級3を取得している住宅は、“価格が下がりにくい資産”として評価されやすい傾向があります。これは一時的な流行ではなく、制度や査定基準とも連動した、現実的で信頼性のある評価基準です。

耐震等級3は中古市場でも高評価を得やすいです。
耐震等級3の有無で最大400万円の価格差が発生

首都圏の中古住宅市場では、耐震等級3の有無によって数百万円の価格差が出ている事例があります。
| 築年数 | 耐震等級3ありの売却価格 | なしの売却価格 | 価格差 |
| 10年 | 約3,800万円 | 約3,500万円 | 約300万円 |
| 15年 | 約3,400万円 | 約3,000万円 | 約400万円 |
| 20年 | 約3,000万円 | 約2,600万円 | 約400万円 |
※実際の取引事例を基にした概算。立地や住宅の規模により変動あり。
このように、築年数や広さが同じでも「耐震等級3かどうか」で大きく評価が変わるのが実情です。

等級3の有無で、売却価格に最大400万円の差も。
耐震基準の違いが売却リスクと査定額に影響する
過去の例として、「新耐震(1981年以降)」と「旧耐震」の中古住宅でもはっきりとした価格差が出ています。旧耐震基準の住宅は、ローン審査や保険加入に制限がかかることもあり、買い手がつきにくいという現実があります。
これと同じように、今後「耐震等級3の有無」によって取引のしやすさや価格に差が出る可能性は高いといえます。住宅性能を明確に評価した書類は、“資産価値を裏付ける証明書”として機能するのです。
第三者評価の有無が売却の信頼性と資産価値を左右する
家を買う人の多くは、建築の専門家ではありません。だからこそ、住宅の性能が客観的に証明されているかどうかが大きな判断材料になります。
耐震等級3の評価は、国が定めた基準に基づいて第三者が審査し、発行するものです。正式な評価があることで、購入者や金融機関に対して「信頼できる住宅である」という明確な根拠を示すことができます。
評価書のない等級3相当は売却時に不利となる
注意すべきなのは、「等級3相当」と記された住宅です。これはあくまで“等級3と同程度の仕様”であって、正式な評価書が発行されていないケースが多いのです。
評価書がない場合、売却時に買い手に住宅性能を正しく伝えられず、基本的にはローンの金利優遇や保険料の割引が適用されません。「等級3相当」と「等級3取得済」では、将来的な資産価値に差が出る可能性も高くなります。

「評価書付き」かどうかで、将来の価値が変わります。
性能評価付き住宅は査定時に加点対象となる
不動産会社による査定では、耐震等級が加点の対象になることがあります。とくに「住宅性能評価書付き」の住宅は、査定時にプラス材料として評価されやすい傾向にあります。
全国共通の明確な加点基準があるわけではありませんが、住宅の性能を裏づける情報は「ほかの物件との差別化要素」として大きく働きます。つまり、“売れる住宅”と見なされやすくなるのです。

しょーすけ
評価書は他の物件との差をつける武器になります。
売却の判断に役立つ「価格の目安」がわかる無料サービス&ブログ
このトピックについて
- 家の売却を考えるタイミングが近づいている方におすすめ
- 自分の家や土地の価格感が無料で把握できるサービスを紹介
- 査定前に価格相場を知り、冷静な判断ができるようになる
家の売却を検討するとき、最初に悩むのが「今、いくらで売れるのか」ということです。いきなり不動産会社に連絡するのは気が引けるという方も少なくありません。そんなときは、無料で価格の目安を調べられるサービスを活用するのが便利です。
土地や建物の相場情報を自分で調べておくことで、査定価格の妥当性や条件交渉の判断材料になります。ここでは、売却前の情報収集に役立つ2つの無料サービスをご紹介します。
トチノカチ
「トチノカチ」は、全国の公示地価・路線価・固定資産税評価額を一括で確認できる無料の地価検索サービスです。
住所を入力するだけで、その土地の参考価格や税制上の評価額がわかります。とくに「路線価」や「固定資産税評価額」は、相続や税金、金融機関とのやり取りで使われる重要な数値です。査定の相場観を把握したいときにも有効です。
地価に関する複数の公的データを一度に確認できるため、「土地の価値」を客観的に捉えるのに役立ちます。
ウチノカチ
「ウチノカチ」は、過去の売買事例をもとに、自宅の推定価格や近隣の相場がわかる不動産価格検索サイトです。
国土交通省が公開する約510万件の成約データをもとにしており、駅距離・築年数・広さなどの条件を入力すれば、類似物件の価格傾向が自動で表示されます。マンション・戸建て・土地・賃貸まで幅広く対応しています。
「売るならいくらぐらいか」「今の価値はどれくらいか」を感覚ではなくデータで把握したい方にぴったりのサービスです。
不動産売却デスク
不動産売却の関する知識・ノウハウを見てみたいなら以下のブログがおすすめです。
不動産売却を検討している方に向けて、初心者でも実践しやすい情報と信頼性の高い知識をわかりやすく提供している情報サイトです。売却の基本から、後悔しないための注意点、相場の見方まで、これから売る人が知っておくべき実用的なポイントを丁寧に解説しています。不動産に詳しくない方でも読み進めやすく、自分に合った判断ができる内容が揃っています。
耐震等級3の住宅はローン残債リスクを軽減できる

このトピックでわかること
- 売却時にローンが残ることに不安を感じている方におすすめ
- 耐震等級3がローン残債リスクの軽減にどう役立つかがわかる
- 資産価値を基準に住宅性能を比較・判断できるようになる
家を買うとき、多くの方が気にするのが「ローンを最後まで返済できるかどうか」という不安です。ですが、もうひとつ大切な視点があります。それは、「もし途中で家を売ることになったとき、ローンが残らずに済むかどうか」ということです。
ローンを完済しないまま売却しなければならなくなると、「自己資金での補填」や「売却できずにローンだけが残る」といったリスクが発生します。そこで注目したいのが、資産価値が下がりにくい家=耐震等級3の住宅です。
ここでは、耐震等級3が“ローン残債リスクを減らす住宅性能”でもあることを、具体的に解説します。

等級3の家は「売ってもローンが残りにくい」。
資産価値維持によりローン完済可能性が高まる

住宅ローンの返済期間は20〜35年と長期にわたります。その間には、転勤・介護・家族構成の変化・相続など、住まいを手放さざるを得ない事情が発生することもあります。
家を手放すとき重要になるのが、売却価格がローン残債を上回っているかどうかです。以下の2パターンを比較してみましょう。
| 項目 | 資産価値が下がりやすい家 | 資産価値が維持されやすい家(等級3) |
| 売却価格 | 2,500万円(築15年) | 3,000万円(築15年) |
| ローン残債 | 2,800万円 | 2,800万円 |
| 差額(手出し必要額) | ▲300万円(自己資金で補填) | +200万円(手元に残る可能性あり) |
このように、同じローンを組んでいても、家の資産価値が高く保たれていれば、売却によってローンを完済しやすくなります。将来、住み替えや転居といった選択が必要になったときも、経済的な負担を最小限に抑えることができます。

売却時に“手出し不要”になる可能性もあります。
明確な性能評価が資産価値の下落幅を抑制する
一般的に、築年数が経過するほど住宅の資産価値は下がっていきますが、耐震等級3のように「明確な性能評価がある住宅」は下落幅が比較的ゆるやかです。
- 安全・安心という評価が中古住宅でも有効に働く
- 買主の住宅ローン審査や地震保険料で優遇が受けられる
- 構造計算書や評価書の存在が“安心材料”になる
こうした要素が、「安心して購入できる住宅」としての評価を支えるため、売却時にも有利に働くのです。
減税や保険優遇でローン残債対策と家計負担を軽減できる
耐震等級3を取得しておくことで、購入当初から家計の負担を抑えられる制度も利用できます。制度を利用することが、結果的に将来のローン残債とのバランスを改善することにつながります。
- 住宅ローン減税:控除額が大きく、10〜13年にわたって所得税や住民税が軽減される
- 地震保険料の割引:耐震等級3で保険料が最大50%割引になる
住宅ローン減税や地震保険料の割引といった制度を活用することで、日々の支出を抑えながら、将来にわたって資産価値を維持しやすくなります。

制度を使えば、日常の支出も将来の安心も手に入ります。
耐震等級3の住宅は、「安心して暮らせる家」であると同時に、「家計にやさしく、将来の行動を縛らない家」でもあります。“売却してもローンが残りにくい家”という視点からも、非常に価値の高い住宅です。

300万円の差額実績あり
あなただけのオリジナルプランを今すぐ手に入れる
新築・中古戸建も比較してみたい
【PR】タウンライフ
制度優遇を受けられる耐震等級3住宅は総支払額を抑制できる

このトピックでわかること
- 金利や保険で得られる制度を活用したい方におすすめ
- 耐震等級3の住宅が受けられる優遇制度が具体的にわかる
- 購入時から支払い総額を抑える仕組みを理解し活用できるようになる
家を建てるときにかかる費用は、建物そのものの性能だけでは決まりません。実は、住宅ローンや地震保険などの制度でどんな優遇を受けられるかによって、最終的な支払い総額に大きな違いが生まれるのです。
耐震等級3の住宅は、国の基準を満たすことで、住宅ローン・地震保険・税制といった複数の制度による優遇を受けられます。ここでは、家計への影響がとくに大きい代表的な制度を紹介します。
耐震等級3はフラット35Sの最大金利優遇対象となる

住宅ローンの固定金利型として人気の「フラット35」では、一定の住宅性能を満たすことで金利が下がる優遇制度(フラット35S)を利用できます。
耐震等級3は、フラット35SのAプランの主な対象条件に含まれており、ローン契約から最初の5年間、金利が年0.5%引き下げられる優遇が適用されます。
以下はフラット35の標準金利に対する優遇内容の比較です。
| プラン | 金利引下げ幅 | 優遇期間 | 主な対象住宅性能 |
| Aプラン | 年▲0.5% | 当初5年間 | 耐震等級3・長期優良住宅など高性能住宅 |
| Bプラン | 年▲0.25% | 当初5年間 | 一定の省エネ基準を満たす住宅 |
| ZEHプラン | 年▲0.75~1.0% | 当初5年間 | ZEH認定住宅+長期優良住宅など(条件あり) |
※ZHEプランは別途条件あり
3,000万円を借りた場合、Aプランの適用だけでも5年間で最大75万円以上の利息軽減につながるケースがあります。

耐震等級3でフラット35の金利が大きく下がります。
フラット35Sの各プランは性能条件により優遇幅が異なる
それぞれのプランには、次のような性能条件があります。
Aプラン
耐震等級3や長期優良住宅など、構造や省エネ性能について国の認定を受けた住宅
Bプラン
一定の断熱性能や設備仕様を満たす省エネ基準対応住宅
ZEHプラン
高断熱+太陽光発電などで、一次エネルギー消費を実質ゼロに抑える住宅(より厳しい条件が必要)
耐震等級3は、Aプランの中でもとくに重視される性能の一つであり、もっとも手厚い金利優遇を受ける前提条件になります。
耐震等級3取得で地震保険料が最大50%割引される

耐震等級3の住宅は、地震保険でも明確なメリットがあります。国の制度により、保険料が最大50%割引になるからです。

震保険が半額に。生涯で10万円以上お得になることも。
たとえば、年間保険料が30,000円の木造住宅の場合、耐震等級3を取得していれば15,000円にまで下がることになります。
| 耐震性能 | 割引率 | 年間保険料の目安 |
| 等級1以下 | 0% | 約30,000円 |
| 等級2 | 30% | 約21,000円 |
| 等級3 | 50% | 約15,000円 |
※保険料は地域や構造、保険会社により異なります
保険期間は最大5年で、契約更新のたびに割引が適用されます。長期でみると、生涯で10万〜20万円以上の支払い差になる場合があります。
法改正により耐震等級3が住宅性能の標準になる
2025年の建築基準法改正により、木造2階建て以上の住宅では構造計算が事実上必須になります。これまでは一部の高性能住宅でしか行われていなかった構造計算が、すべての住宅に求められるようになるのです。
この動きを受けて、今後は耐震等級3を取得しやすい設計や申請の流れが整っていくと考えられています。
- 等級3の取得には、構造計算と第三者による性能評価が必要
- 法改正により、これらのステップが住宅設計の前提になる
- 長期優良住宅とのセット認定も受けやすくなり、制度利用の幅が広がる
つまり、これからの家づくりでは、耐震等級3を選ぶことが「特別なこと」ではなく「標準的な判断」になる可能性が高いということです。
耐震等級3の住宅は、安心して暮らせるだけでなく、住宅ローン・地震保険・査定評価といった制度を最大限に活用できる“性能の条件”にもなります。将来を見据えるなら、コスト以上のメリットが得られる住宅性能といえるでしょう。
耐震等級3は追加費用以上の資産価値を生む選択肢となる

このトピックでわかること
- 耐震等級3の取得にかかる費用が気になる方におすすめ
- 追加費用と将来の経済的メリットを具体的に比較できる
- 耐震等級3を「取るかどうか」の判断材料が手に入る
耐震等級3を取得するには、たしかに一定の費用がかかります。ですが、その追加コストは将来の売却や家計にとってプラスになる場面も多いのです。
ここでは、耐震等級3を取得するための費用相場と、それがどのように「長期的な得」につながるのかを紹介します。
耐震等級3取得には構造計算等で80〜150万円が必要

耐震等級3を取得するには、設計・申請・施工の各段階で専門的な対応や審査が追加されるため、通常よりコストがかかります。以下は一般的な費用の目安です。
| 項目 | 費用相場(概算) | 内容概要 |
| 構造計算費 | 20〜40万円 | 建物の構造安全性を証明するための計算業務 |
| 性能評価申請費(評価書) | 10〜40万円 | 評価機関への書類作成や審査にかかる費用 |
| 耐震施工の強化分 | 50〜70万円 | 金物・耐力壁など構造補強にかかる施工費 |
| 合計 | 約80〜150万円 | 規模や設計内容により変動 |
このほか、設計事務所や工務店によっては別途手数料が発生する場合もあります。
耐震等級3の取得費用は施工会社や地域により変動する
耐震等級3の取得費用は、依頼先や地域によって差があります。
- 都市部では申請手数料が高くなる傾向がある
- 耐震施工の実績が豊富な工務店は、効率的な対応でコストを抑えやすい
- 評価書の取得に非対応の会社では、外部の設計士を手配する必要がある場合も
そのため、「耐震等級3を標準対応しているかどうか」が、費用を抑えるうえでのポイントになります。契約前に、見積りと実績を確認することが重要です。
売却価格や制度優遇で耐震等級3の費用は回収可能
一見すると、80〜150万円という追加費用は大きな負担に感じられます。ただしこれを、将来の売却価格・保険料・ローン利息の削減といった経済効果まで含めて考えると、十分に元が取れる可能性があることがわかります。
具体的には以下のようなリターンが期待できます。
- フラット35Sによる金利優遇で、5年間で最大75万円以上の利息削減
- 地震保険料の割引により、30年間で10万円以上の節約が可能
- 中古売却時、耐震等級3の有無で300〜400万円の価格差が生じる実例あり
「高いからやめておこう」と判断したくなるかもしれません。ただ、数字で比較すると、耐震等級3の認定を取らないほうが結果的に損をすることも少なくありません。
家づくりで本当に考えるべきなのは、「建てるときにいくらかかるか」ではなく、「住み終えたときに、その家がどれだけ価値を発揮してくれたか」という視点です。そう考えると、耐震等級3は費用対効果に優れた選択肢といえます。
耐震等級3は将来の売却損や残債リスクを防ぐ最適解

これまで見てきた通り、耐震等級3の住宅は「地震に強い」だけではありません。将来の売却に備え、資産価値を守る手段としても大きな役割を果たします。
中古市場で価格が下がりにくく、買い手がつきやすくなる。売却時にローン残債が残りにくくなる。──それは、住宅としての信頼性が資産価値につながっている証拠です。
フラット35Sの金利優遇や地震保険料の割引など、制度面での後押しも受けられるため、初期コスト以上の経済的なメリットが期待できるのも特徴です。
たしかに追加費用は発生しますが、それは単なるコストではなく、「損しにくい家を建てるための先行投資」ととらえるべきです。

等級3はコストではなく、未来の安心への投資です。
- 中古市場で価格が下がりにくい
- 売却時にローン残債が残りにくい
- 買い手に選ばれやすい条件が整っている
- 金利・保険など制度面の優遇がある
- 法改正により今後は“標準仕様”になる流れ
「いつか売るかもしれない」「家族の将来は変わるかもしれない」──そうした“もしも”に備える意味でも、耐震等級3という住宅性能を選択肢に入れておく。それは、これから家づくりを始めるうえで後悔のない判断基準になるはずです。