この記事にはプロモーション・広告が含まれています
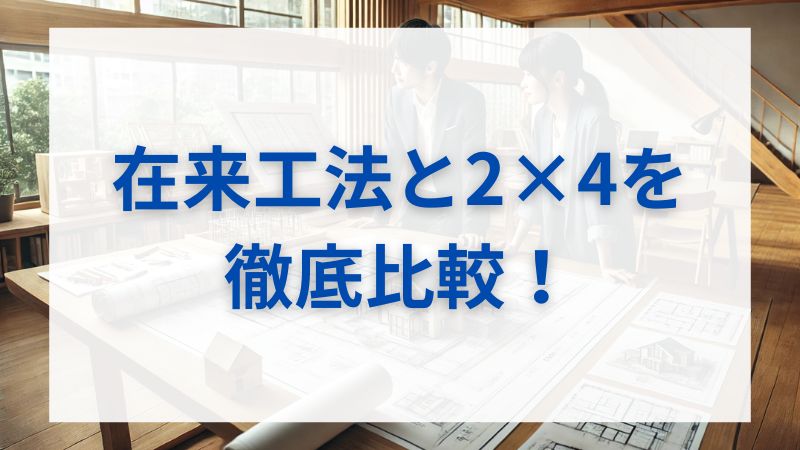
地震の多い日本に暮らす私たちにとって、「家族の命を守れる家づくり」は最重要課題の一つです。子どもを持つ家庭では、安全な住まいを選ぶことが、将来の安心と直結しています。
その中で注目されているのが、住宅性能表示制度における「耐震等級3」の家です。消防署や警察署など、災害時の拠点施設と同レベルの耐震性能を持つこの等級は、多くの家庭にとって大きな安心材料となります。
しかし、同じ「耐震等級3」の認定を受けていても、その構造や工法によって家の性能や暮らし方には違いが生まれます。「在来工法(木造軸組工法)」と「ツーバイフォー工法(木造枠組壁工法)」の違いは、見た目ではわかりにくいものの、地震時の耐震力や間取りの自由度、将来的なメンテナンス性に大きな影響を与えます。
本記事では、「在来工法とツーバイフォー、どちらが耐震等級3に向いているのか?」という素朴ながら重要な疑問に、専門的な視点と生活者目線を交えて丁寧に答えていきます。家づくりを考えるすべてのご家庭にとって、安心できる選択の一助となれば幸いです。
関連記事:【地震に備える家づくり】耐震等級3の設計基準と施主が知っておくべき注意点
「耐震等級3」は本当に安全?その基準と誤解しやすい落とし穴

耐震性能に関心のある方なら一度は聞いたことがある「耐震等級3」。これは住宅性能表示制度において最も高い耐震ランクであり、災害時の拠点施設と同等の基準です。
しかしながら、「耐震等級3だから絶対安全」ではないという点を見落としてはいけません。等級の数字だけに安心してしまうと、本当に必要な安全性を見誤る可能性があります。
耐震等級とは「建築基準法以上の備え」
住宅の耐震等級は、「建築基準法で求められる最低限の耐震性能(等級1)」を基準とし、それに対して1.25倍の耐震力が等級2、1.5倍の耐震力が等級3とされています。
関連記事:耐震等級3で家族を守る!地震に強い家を作るための完全ガイド
つまり、耐震等級3は建築基準法の基準より1.5倍の地震力に耐える設計がなされているという意味です。これは震度6強から震度7クラスの地震を想定し、住宅が倒壊しないことを目的としています。
この性能は、過去の震災から得た教訓を反映した極めて実践的な基準であり、南海トラフや首都直下型地震のような巨大地震への備えとして有効です。
関連記事:耐震等級3の家でも危ない?地震に負けない設備選びと設置のポイント
「等級3=絶対安心」ではない理由
耐震等級3が「倒壊しない強さ」を保証する一方で、実際の地震被害では倒壊を免れた家でも大きな損傷を受けるケースが多々あります。
熊本地震では「耐震等級3の家が全壊した」というケースも報告されました。その原因の多くは以下のようなものでした。
- 構造計算はクリアしていても、壁の配置バランスが悪かった
- 金物の施工不良や取り付けミスがあった
- 地盤の調査や基礎の設計が不十分だった
つまり、設計通りに施工されていない、あるいは設計の詰めが甘いと、いくら等級3であってもその性能は発揮されません。
このことから、住宅の耐震性能を評価する際には、「等級」だけでなく、設計・施工の品質や構造上のバランスの良さまで含めて総合的に判断する必要があると言えます。
耐震等級3を実現する方法にも差があります。「壁量計算だけで等級3を取得した家」と、「許容応力度計算で緻密に設計された家」では、安全性に大きな差が生まれることもあるのです。
耐震性能における「見えない差」を意識し、数値の裏側にある設計意図や施工精度を確認することが、真に強い家づくりへの第一歩となります。
同じ木造でも「構造の考え方」がまったく違う!在来工法とツーバイフォー工法の仕組み

見た目は似た木造住宅でも、構造の基本設計が異なれば「揺れへの強さ」「間取りの柔軟性」「将来の暮らしやすさ」に大きな差が生まれます。在来工法とツーバイフォー工法、それぞれの特徴を知ることが、後悔しない家づくりの第一歩です。
「柱で支える」在来工法の柔軟性と難しさ
在来工法は、自由設計とリフォームのしやすさが魅力ですが、耐震性の確保には高い設計力と施工力が求められます。
関連記事:狭小地・不整形地でも諦めない!L字・三角・旗竿地でも実現できる耐震等級3の家
設計自由度が高く、間取りの自由がきく
吹き抜けや大きな窓、複雑な形状も設計しやすく、デザイン性に富んだ家が実現できます。
リフォームがしやすい
将来的な間取り変更や設備更新がしやすく、長期的なライフスタイルの変化に対応できます。
耐震性は設計・施工の精度に左右される
耐力壁や金物の配置が適切でなければ、等級3でも構造が不安定になることがあります。
職人の技術力が品質を大きく左右する
経験豊富な施工者であれば高性能な家を建てられますが、スキルの差が仕上がりに影響します。
「面で守る」ツーバイフォーの合理性と限界
ツーバイフォー工法は、耐震性の安定と施工品質の均一性が特徴ですが、間取りやリフォームの自由度に制約があります。
関連記事:【保存版】住宅の引き渡し時に絶対見るべき!後悔しないためのチェックリスト
モノコック構造で耐震性を確保しやすい
パネル全体で外力を受け止め、揺れを分散させる仕組みで、安定した構造が得られます。
品質のバラつきが出にくい
材料や工法が標準化されており、どの職人が施工しても一定の品質が保たれやすい傾向があります。
間取りの自由度はやや制限される
耐力壁を多く確保する必要があるため、大開口や自由なレイアウトには不向きです。
リフォームが難しいケースがある
壁の一部が構造体を兼ねているため、後から間取りを変更するには制約が伴います。
両工法の特性を並べて比較すると、それぞれが持つ長所と課題がより明確に見えてきます。
| 特徴 | 在来工法 | ツーバイフォー工法 |
| 構造形式 | 柱と梁で支える軸組構造 | 面で支えるモノコック構造 |
| 設計の自由度 | 高い(間取り変更が容易) | 限定される(壁配置が制限) |
| 耐震性の確保 | 設計・施工に左右されやすい | 構造的に確保しやすい |
| 施工品質の安定性 | 職人の技術に依存 | 規格化され安定しやすい |
| 将来のリフォーム | 柔軟に対応可能 | 壁を抜けないことが多い |
「こだわりの家を一からつくりたい」なら在来工法、「耐震性と施工の安定性を重視したい」ならツーバイフォー工法が適しています。
それぞれの構造の違いが、暮らしやすさや将来設計にどう影響するかを踏まえ、自分たちに最も適した工法を選ぶことが重要です。
工法によって「耐震等級3の難易度」はどう変わる?

同じ耐震等級3でも、採用する工法によってその実現方法や難易度は大きく異なります。ここでは在来工法とツーバイフォー工法が「等級3をどう満たすのか」、その裏側にある構造的な違いや注意点を掘り下げます。
関連記事:【保存版】耐震等級3を確実に取る!設計審査の書類・手続き完全マニュアル
在来工法で「耐震等級3」を実現するには技術力がカギ
在来工法で耐震等級3を取得するには、壁量だけでなく、壁の配置や接合部の強度など、構造全体のバランス設計が不可欠です。次のような点に注意が必要です。
壁量の確保とバランス設計が必要
等級3を満たすには耐力壁の量だけでなく、配置バランスも適切でなければなりません。
金物の種類と施工精度が耐震性能に直結
金物が正しく取り付けられていないと、設計通りの性能が発揮できなくなります。
許容応力度計算の導入で性能を明確に
壁量計算では不十分な場合、より精密な構造計算が求められます。
吹き抜け・大開口の設計は注意が必要
空間設計にこだわるほど、耐震バランスに配慮が必要になります。
つまり、在来工法で等級3を目指すには、設計者と施工者の高度な連携が不可欠です。家づくりの自由度を活かしながら耐震性能を高めるには、それを実現できる実力ある建築会社を選ぶ必要があります。
ツーバイフォーなら「自然に耐震性が高い」?それでも見落とせない点
ツーバイフォー工法は、構造体そのものがパネルによって囲まれており、標準仕様でも耐震性が高く、等級3をクリアしやすい傾向があります。ただし、過信は禁物です。
関連記事:【要確認】モデルハウスで“本物の耐震等級3”を見抜く5つの視点とは?
パネル工法で壁量が取りやすい
各面に構造用合板が貼られ、地震力を分散しやすい構造です。
工場生産・プレカットが品質を安定化
部材が工場で規格生産されるため、現場施工のばらつきが抑えられます。
開口部の大きさに制限がある
窓や吹き抜けを大きくすると、必要な壁量が確保できず、耐震等級3の取得が難しくなります。
部分的な変更が難しく、設計初期での検討が重要
後からの調整や補強がしにくく、設計段階で耐震計画を完了させる必要があります。
つまり、ツーバイフォー工法は、「等級3のハードルが低い」反面、設計段階での制約が多くなるのが特徴です。高い耐震性能をスムーズに実現できる一方で、自由設計には限界があるため、設計の目的と優先順位を明確にしておく必要があります。
どちらの工法も耐震等級3の実現は可能ですが、「どこに手間がかかるか」「どこで性能が左右されるか」は異なります。次の表で、耐震等級3を実現するうえでの比較ポイントを整理します。
| 項目 | 在来工法 | ツーバイフォー工法 |
| 壁量の確保 | バランス設計が必要 | 自然に取りやすい |
| 耐力壁の自由度 | 高い(配置も選べる) | 低い(配置制限あり) |
| 開口部設計のしやすさ | 自由(耐震設計に影響) | 制限されやすい |
| 接合部の施工精度 | 職人の技術に依存 | 工場加工で安定しやすい |
| 設計変更・柔軟性 | 高い(リフォーム対応も可) | 低い(変更に制限が多い) |
| 耐震等級3の実現難易度 | 高い(計算・設計の工夫が必要) | 比較的容易(標準でも近づく) |
設計の自由を活かしながら耐震性を高めたいなら在来工法、設計に制約があっても確実な耐震性能を求めるならツーバイフォー工法が向いています。
工法選びは家の安全性だけでなく、「どう暮らしたいか」にも深く関わります。耐震等級3という数値の裏にある「構造の違い」を見極め、最適な選択をしていきましょう。
「耐震性が高い家」にするには?設計と施工で差がつくポイント

耐震等級3を取得していても、実際の地震で安全かどうかは「設計」と「施工」の質に大きく左右されるのが現実です。数値上の基準だけでなく、細部に宿る設計と現場の工夫こそが家の真の強さを決めます。
関連記事:耐震等級3を活かすには?地盤調査と基礎工事で家の強さは決まる
ここでは、耐震等級3の性能を引き出すために欠かせない設計と施工のポイントを具体的に解説します。
壁の配置バランスが家の強さを決める
耐震性能は単に「壁の量」で決まるわけではありません。壁の配置バランスが悪いと、建物がねじれたり片側だけが壊れる「偏心」が発生し、等級3でも損傷する恐れがあります。
壁量の確保だけでなくバランス配置が必要
壁が東西南北に均等に配置されているかが、揺れに耐える鍵です。
開口部とのバランスに注意
窓や吹き抜けが多いと壁が減るため、他の面で補う必要があります。
2階と1階の壁配置をそろえる工夫も重要
上下階で構造がズレると地震時の衝撃が集中しやすくなります。
許容応力度計算が「見えないリスク」を防ぐ
壁量計算では建物全体の大まかな耐震性能しか把握できません。構造上の安全性をより厳密に確保するためには「許容応力度計算」の導入が効果的です。
部材ごとの強度や接合部の力を計算
柱・梁・金物などにかかる応力を定量的に確認できます。
建物の「たわみ」や変形の程度も把握可能
倒壊しないだけでなく、損傷の程度まで設計段階で想定できます。
木造住宅でも対応可能
以前はRC造などに限定されていた手法ですが、今では木造住宅でも積極的に導入されています。
金物や接合部が弱点にならないために
どれだけ設計が優れていても、施工現場での金物不備や接合部の手抜きがあると耐震性能は発揮されません。見落としやすいポイントにこそ、強さの決め手があります。
指定通りの金物を正しく設置することが前提
種類や設置方向が間違っていると強度が著しく低下します。
釘やビスの本数・間隔も重要な構造要素
壁倍率(壁の強度)に影響するため、施工マニュアルの厳守が必須です。
第三者監査の導入で安心を担保
施工の確実性を高めるには、専門機関によるチェック体制の有無も重要な判断基準です。
耐震等級3を数値だけで満たしても、設計バランスの悪さや施工ミスがあれば安全性は大きく損なわれます。それを防ぐためには、以下のようなチェックポイントを重視すると良いでしょう。
| チェック項目 | 見るべきポイント |
| 壁の配置バランス | 偏りなく配置されているか |
| 計算方法の種類 | 壁量計算だけでなく構造計算も実施 |
| 金物の種類と施工精度 | 施工マニュアル通りの取付がされているか |
| 接合部や釘の規定 | 数量・位置・間隔のチェックがあるか |
| 第三者監査体制 | 完成前にプロによる確認が入るか |
「設計と施工の質」が、家族の命を守る最後の砦です。
住宅会社や建築士選びでは、こうした設計精度・施工品質まで確認する目を持ちましょう。安全な家づくりは、図面と現場の“精度”から生まれます。
工法の違いが「住み心地」や「将来の暮らしやすさ」にも影響する

耐震性能はもちろん重要ですが、「今の快適さ」や「将来の暮らしやすさ」に直結する視点も見逃せません。在来工法とツーバイフォー工法の違いは、リフォームの柔軟性や職人依存度、コストやメンテナンス性にも現れます。安全性と快適性の両立を考えるなら、このセクションが大きな判断材料になります。
リフォームや間取り変更のしやすさは意外と大事
家族構成や暮らし方は、10年、20年と変化していきます。構造がしっかりしていても、間取り変更が難しければ「住み続けにくい家」になってしまうこともあるのです。
在来工法は間取り変更に柔軟に対応できる
構造壁を避ければ自由に部屋をつなげたり仕切ったりでき、リノベーションしやすいです。
ツーバイフォーは構造壁が制限になることも
耐力壁の一部を抜くのが難しく、改修には費用や制約が多くなります。
将来の二世帯化やバリアフリー化も想定
柔軟な対応力がある工法ほど、長く安心して暮らせます。
職人の腕に左右されやすい工法、安定した品質が出やすい工法
どれだけ良い設計でも、現場での施工精度が低ければ性能は発揮できません。工法ごとの施工安定性と、それを担保する仕組みにも注目する必要があります。
関連記事:【徹底比較】耐震等級3の家づくりで後悔しない依頼先の選び方|ハウスメーカー・工務店・設計事務所の違い
在来工法は職人の技術力によって品質差が出やすい
木材の加工や接合、耐力壁の設置に熟練の技術が必要で、施工者によって仕上がりに差が生じやすいです。
ツーバイフォーはプレカットで品質が安定しやすい
工場加工の部材を現場で組み立てる形式のため、ミスが起きにくく品質も一定に保ちやすいです。
施工会社の監理体制や現場教育も重要なポイント
どの工法でも現場管理が徹底されていないと、設計通りの性能は得られません。
工期やコスト、メンテナンス性はどう違う?
初期費用だけでなく、工期の短さや将来的な維持費の面でも工法の違いは暮らしに影響します。選ぶ際には「総合的なコスト感覚」が大切です。
関連記事:【保存版】耐震等級3の家はいくらかかる?総費用と賢い資金計画の立て方
ツーバイフォーは工期が短く、ローコストで済みやすい
規格化された部材を使うことで効率よく施工でき、人件費も抑えられます。
在来工法は工期がやや長くなる傾向
現場での加工・調整が多く、オーダーメイドの要素が多いと時間とコストがかさみます。
メンテナンスしやすさは設計や構造による
設備配管の交換・壁内部の点検など、後々の管理性も含めて構造を選ぶと長く快適に暮らせます。
以下のように、耐震性以外の生活面でも工法ごとに特徴があります。
| 比較項目 | 在来工法 | ツーバイフォー工法 |
| 間取り変更のしやすさ | 高い(構造を避ければ柔軟) | 低い(構造壁の制約が大きい) |
| 職人依存度 | 高い(技術に左右されやすい) | 低い(品質が安定しやすい) |
| 工期と初期コスト | やや長く、高くなる傾向 | 短く、コストも抑えやすい |
| 将来の維持管理性 | 設計次第で柔軟に対応可能 | 開口・配線の制約で制限あり |
家づくりは一度きりの大きな選択ですが、暮らしはずっと続いていきます。耐震等級3という安全基準の裏にある「住み心地と将来性」にも目を向けることが、後悔しない選択につながります。
あなたに合った工法の選び方ガイド

「どちらの工法が優れているか」ではなく、「自分の暮らしに合っているのはどちらか」という視点が、後悔しない家づくりにつながります。家族構成や将来設計、土地の特性に応じて、在来工法とツーバイフォー工法を適切に選ぶためのガイドラインを紹介します。
家族の暮らしに合わせて選ぶ工法
ライフスタイルは家庭によってさまざま。「今」と「これから」を見据えた家づくりが、長く安心して暮らせる住宅の鍵です。
小さな子どもがいる家庭には柔軟な間取り変更が可能な在来工法
成長に合わせた部屋割り変更や、将来のリノベーションにも対応しやすいです。
共働き家庭や介護を見据えた二世帯同居にはツーバイフォー工法の安定性
耐震性と断熱性に優れ、世代を超えて快適に暮らせる環境を提供します。
趣味や仕事部屋など自由設計を重視するなら在来工法
空間の使い方にこだわる人にとって、自由な間取り設計は大きな魅力になります。
土地や気候で「向いている工法」は違う
土地条件や気候風土によっても、工法の向き・不向きがあります。構造的な強さだけでなく、環境に適した性能を引き出せる工法選びが重要です。
地震が頻発する地域ではツーバイフォーのモノコック構造が有利
揺れを面で受け止め、倒壊リスクを抑えやすくなります。
風が強い地域や雪国では壁構造の剛性が重要
面構造で均一に力を受けられるツーバイフォーが安定性を発揮します。
狭小地や変形地では自由な設計ができる在来工法
建築制限の多い都市部でも柔軟に対応でき、空間を有効活用できます。
信頼できる施工業者を見極める3つの視点
どの工法を選ぶにしても、最終的な品質を左右するのは「誰が建てるか」です。信頼できる施工業者を見極める際には、次の3つのポイントに注目しましょう。
技術力(施工実績・資格・構造計算対応)
耐震等級3を実現できる設計力と、正確な施工ができる技術力のある会社を選びましょう。
説明力(工法の長所・短所を誠実に伝える)
自社工法だけを押しつけるのではなく、複数工法を比較して説明できる会社は信頼度が高いです。
アフター対応(定期点検や構造保証の内容)
万が一のときにすぐ対応してもらえる体制があるかを事前に確認しておくと安心です。
理想の家づくりは、「安全性・快適性・将来性」のバランスで決まります。
| 判断軸 | 在来工法 | ツーバイフォー工法 |
| ライフスタイル適応 | 柔軟性が高く変化に対応しやすい | 安定性が高く長期的に安心 |
| 土地・環境との相性 | 狭小地・変形地に強い | 地震・風圧・積雪に強い |
| 施工会社の見極め | 技術力・経験のある職人が必要 | 管理体制が整った会社が安心 |
選ぶべきは「どの工法か」よりも「どんな暮らしを実現したいか」。
構造の知識と生活目線を重ねて、自分たちにとって本当に合った工法を選びましょう。
強くて暮らしやすい家を選ぶために、いま知っておくべきこと

在来工法とツーバイフォー工法、どちらも耐震等級3の取得は可能ですが、その実現方法や住み心地、将来性には明確な違いがあります。構造の違いを知り、ライフスタイルや価値観に合った選択をすることで、家族にとって「本当に安全で快適な家」をつくることができます。
「等級3だから安心」ではなく、「等級3をどう実現するか」にこそ注目すべきです。壁の配置や構造計算、施工品質まで含めて総合的に判断しなければ、本当の意味で安心できる住まいは手に入りません。
どちらの工法を選んでも、ポイントは以下の3つに集約されます。
- 工法ごとの構造的特徴と制約を正しく理解する
- 家族の暮らし方と将来計画に照らして選択する
- 信頼できる施工会社を見つけ、実現力を確保する
この記事で紹介した知識をもとに、住宅会社の比較・相談を始めることで、後悔のない家づくりが進められます。まずは複数の建築会社からの見積もり・プラン提案を受けることからスタートしてみましょう。
憧れの大手メーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれる

住宅展示場や完成見学会にいくのは時間もかかるし大変…
そんなときに便利なのが「タウンライフ家づくり」です。
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
気になるメーカーや工務店を選び、希望の間取りや予算を入力するだけ。「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる!
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。

「タウンライフ家づくり」はこんな方におすすめ
- あなただけの間取りと見積もりを無料で手に入れ比較したい
- 営業されるのが嫌、苦手
- 自宅でじっくり信頼できるハウスメーカーを選びたい
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ




