この記事にはプロモーション・広告が含まれています
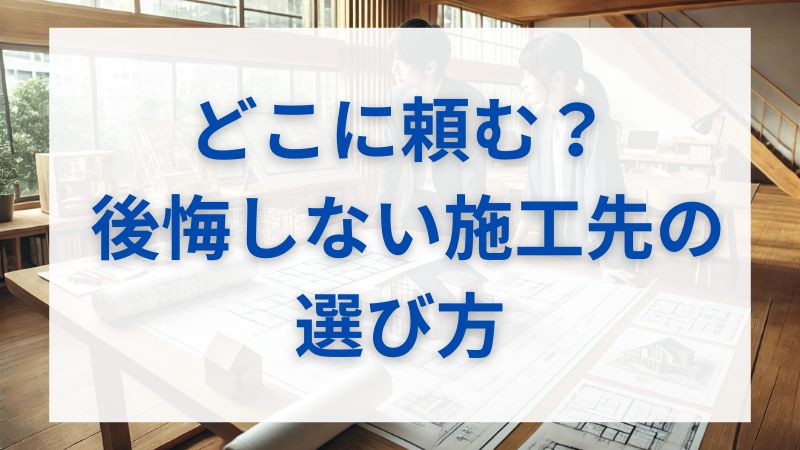
「地震に強い家を建てたい」と考えるとき、多くの人が注目するのが「耐震等級3」という性能指標です。これは、住宅性能表示制度における最高等級で、震度6強〜7クラスの地震にも倒壊しない強さを示すものです。
家族の命と財産を守るために、「耐震等級3の家を建てたい」と願う方は年々増えています。しかし、その実現には「誰に家づくりを依頼するか」という重要な判断が伴います。
工務店・ハウスメーカー・設計事務所――どの選択肢にも一長一短があり、「なんとなくの印象」で選んでしまうと、思わぬ後悔や不安につながることも少なくありません。
本記事では、「耐震等級3」を確実に実現するための依頼先選びのポイントを、徹底比較と事例を交えて詳しく解説します。性能と安心を両立させたい方にとって、確かな判断材料となる内容をお届けします。
まず比較!3タイプの依頼先、それぞれどんな人に向いてる?

耐震等級3の家を建てるためには、「どの依頼先に相談するか」が非常に重要です。工務店・ハウスメーカー・設計事務所のどれを選ぶかによって、設計の自由度や費用、そして耐震性能の実現度に大きな差が生まれます。
どの依頼先にもメリットとデメリットがあり、自分の理想と目的に合った選択が必要です。以下で、それぞれの特徴を比較しながら、向いている人・そうでない人の傾向を整理していきます。
施工先の特徴を一目でチェック
まずは、主要な比較ポイントを表にまとめました。どこに相談するかを迷っている方は、この一覧で大枠の違いをつかんでおきましょう。
| 比較項目 | ハウスメーカー | 工務店 | 設計事務所 |
| 設計自由度 | 制限あり | 比較的高い | 非常に高い |
| 耐震設計の実績 | 自社基準で安定 | 会社ごとに差がある | 構造専門家と組めば高性能も可 |
| 構造計算対応 | 一部対応(構造等級3標準も) | 会社により対応可否が異なる | 原則、設計ごとに対応 |
| 価格帯 | 高め(付加価値含む) | 中〜やや高め(仕様次第) | 設計料+施工費で割高傾向 |
| 保証制度 | 長期保証あり | 内容は会社ごとに異なる | 設計監理の有無で変動 |
| アフター対応 | 一括管理で明確 | 地域密着の柔軟対応あり | 設計完了後は別会社対応が多い |
この表からも分かるように、「安心の規格性」か「自由な設計」かによって選ぶべき依頼先は変わってきます。次に、それぞれの依頼先が向いているタイプを具体的に見ていきましょう。
関連記事:後悔しない!耐震等級3の家づくりに欠かせない施工業者の選び方とチェックポイント
向いている人・合わない人の傾向とは?
それぞれの依頼先に向いている人の特徴を整理しました。「自分はどのタイプに近いか」をチェックしてみてください。
| 依頼先 | 向いている人の特徴 | 合わない人の傾向 |
| ハウスメーカー | 忙しくて比較や管理が苦手/安心・手厚い保証を重視 | 独自の間取り・設計に強くこだわりたい人 |
| 工務店 | 地元で信頼できる会社と柔軟に家づくりしたい人 | 設計や施工に対して細かな不安がある人 |
| 設計事務所 | オリジナリティ重視/構造や素材も吟味したい人 | コストや完成後の管理まで一括で任せたい人 |
選択の分かれ道となるのは、「どこまで自分の要望を通したいか」と「誰が最終責任を持つのか」にあります。「耐震等級3を担保しつつ個性的な間取りにしたい」なら、設計事務所と構造設計者の連携が不可欠です。
一方で「忙しくてこだわる時間がない」「保証やメンテナンスがしっかりしているところがいい」という方には、ハウスメーカーの仕組みが安心感を与えてくれます。
依頼先選びで最も避けたいのは、「思い描いていた家と違う」「性能の根拠が不明確だった」という後悔です。性能・コスト・自由度のバランスを冷静に見極め、自分に合った依頼先を選びましょう。
関連記事:耐震等級3で後悔する人の共通点とは?必要な人・不要な人を徹底解説
「まずは調べて動く」が失敗を減らす:施工先選び4ステップ

家づくりで後悔しないためには、最初の一歩を「調べること」から始めるのが鉄則です。耐震等級3を目指す場合は、依頼先の実力や姿勢を見極めるための情報収集が欠かせません。
性能と信頼性を両立する家づくりは、情報の見極め力にかかっています。ここでは、施工先を賢く選ぶための4ステップをご紹介します。
ステップ1:一括資料請求で“対応できる会社”の全体像をつかむ
まず行うべきは、「耐震等級3に対応できる会社」をリストアップすることです。全国の工務店やハウスメーカーを一括で比較できる資料請求サービスを活用すると効率的です。
対応可能な会社の傾向や、標準仕様の違いを可視化できるため、最初の選別に非常に有効です。地域に根差した中小工務店も含めて把握できるため、選択肢を広く持つことができます。
ステップ2:公式サイトで“耐震の信頼性”を見抜く3つの視点
気になる会社を見つけたら、次は公式サイトを精査しましょう。見るべきポイントは以下の3点です。
- 構造計算の有無と公開度
- 耐震等級3取得の実績件数
- 第三者機関による検査・認証体制
これらの情報が明確に示されていない場合、実績や技術に不安がある可能性があります。本気で耐震等級3を掲げている会社は、構造の根拠や証明書の提示にも積極的です。
誇張的なキャッチコピーよりも、「何を根拠にしているか」を必ずチェックしましょう。
関連記事:【要確認】モデルハウスで“本物の耐震等級3”を見抜く5つの視点とは?
ステップ3:口コミ・SNSで見える“リアルな現場”
カタログやサイトには書かれていない“本音”を知るには、口コミやSNSが非常に有効です。実際にその会社で建てた人の声は、現場対応やアフターサービスの質を見極める上で欠かせません。
- 「営業対応が親身だったか」
- 「完成後の不具合にすぐ対応してくれたか」
- 「施工現場が整理整頓されていたか」
など、実際に経験したからこそわかる内容が多く投稿されています。良い意見だけでなく、不満やトラブル事例もあえて目を通すことで、会社の対応力や誠実さが見えてきます。
口コミを過信せず、複数の情報源から判断することが大切です。
ステップ4:面談・見学で“耐震力の根拠”を引き出す質問とは
最後は、実際にその会社の担当者と面談したり、完成見学会・構造見学会に参加するステップです。ここで聞くべき質問は、「耐震等級3をどのように保証しているか」に直結する内容です。
- 構造設計者は誰で、どう関与しているか?
- 耐震等級3の根拠となる計算書は提示されるか?
- 建築中のチェック体制はどうなっているか?
- 設計・施工・保証の責任分担はどうなっているか?
重要なのは「誰がどこまで責任を持っているか」を明確にすることです。回答が曖昧だったり、質問に対して不明瞭な説明しか返ってこない会社は、慎重に見極めるべきです。
このようなステップを経ることで、「実力と信頼性のある依頼先」に絞り込むことができます。調査に時間をかけることが、最終的には家族の命と安心を守る最大の近道です。
承知しました。以下に、該当セクション全体をスマホユーザー向けに視認性を高めつつ、引用形式を廃止し、必要な表現の構造改善・表形式の修正を加えたうえで再構成しました。
関連記事:【保存版】耐震等級3を確実に取る!設計審査の書類・手続き完全マニュアル
ハウスメーカーに頼むなら「安心の裏側」まで確かめよう

ハウスメーカーは、全国対応の施工体制やブランド力、アフターサービスの手厚さから「安心して任せられる依頼先」として高い支持を集めています。耐震性能においては、「耐震等級3相当」を標準化する企業も多く見られます。
しかし、“相当”という表現は正式な認定とは異なり、あくまで社内基準に基づいたものです。性能評価書や構造計算書の有無を確認し、第三者評価に裏付けられた耐震性能であるかを必ずチェックしましょう。
全国対応・大量施工の強みと弱み
ハウスメーカーの主なメリット・デメリットを整理すると、以下のようになります。
| 項目 | 強み | 弱み |
| 品質管理 | 資材・設計・施工方法の標準化により品質が安定 | 現場での柔軟な対応には限界がある |
| コスト効率 | 大量仕入れによる価格の平準化が可能 | 初期見積りからのオプション追加で割高になることも |
| 施工スピード | 工程がシステム化されており工期が短縮されやすい | 建て主の細かな希望を反映しにくい |
| カスタマイズ性 | 限定的なプラン変更は対応可能 | 間取り・構造の自由度が狭く、制約を感じやすい |
設計の自由度よりも品質・効率・サポートを重視したい方に向いています。
構造計算・保証制度の“自社基準”に要注意
ハウスメーカーの「耐震等級3相当」は、以下のような注意点があります。
- 正式な耐震等級3ではない可能性がある
住宅性能評価機関による認定がなければ、等級2以下の性能であることも。 - 構造計算を行っていないケースもある
木造2階建てでは法的に不要なため、根拠が示されないことがある。 - 第三者検査が省略されている場合もある
自社完結型のチェック体制では、性能評価に偏りが出るおそれがある。
これらは契約前に必ず確認し、「何を根拠に等級3と謳っているのか」まで明らかにすることが重要です。
関連記事:【地震に備える家づくり】耐震等級3の設計基準と施主が知っておくべき注意点
設計と仕様は「カスタマイズ可能かどうか」がカギ
ハウスメーカーでは基本プランが用意されており、大幅な変更は難しい場合があります。耐震等級3と希望の間取りを両立するには、以下の点を確認しましょう。
- 設計変更可能な範囲の具体的説明
- 間取りの変更による構造影響の説明
- オプションや仕様変更の追加費用の明示
希望通りの設計が“構造上の理由”で断られることがないよう、設計の自由度と構造担当者の確認体制を事前にチェックしてください。
関連記事:【徹底比較】在来工法とツーバイフォー、耐震等級3で本当に安心なのはどっち?
長期保証は本当に安心?実際に注意すべき契約内容とは
「30年保証」「地震保証あり」といった長期保証も、契約書を確認しなければ本質が見えてきません。以下のポイントを見逃さないようにしましょう。
| チェック項目 | 確認ポイント |
| 点検条件 | 無償か有償か/頻度・内容は明示されているか |
| メンテナンス義務 | 保証維持のために必要な作業とその費用 |
| 保証範囲 | 耐震・基礎・外壁など、対象部位が明確か |
| 失効要件 | 住まい方・改修などによる無効条件の有無 |
保証制度は“使える状態かどうか”が最重要です。契約前に必ず条文まで確認しておきましょう。
関連記事:【保存版】住宅の引き渡し時に絶対見るべき!後悔しないためのチェックリスト
ハウスメーカーを選ぶなら、この3点は外せない
ハウスメーカーで後悔しないために、以下の3つは必ず確認しておきましょう。
- 耐震等級3の正式な認定実績と構造計算の開示があること
- 設計のカスタマイズ性と構造安全性が両立可能であること
- 保証制度の内容・条件・失効要件が明確かつ実効性があること
この3点を満たす会社こそが、安心と性能の両立を叶えるパートナーです。ブランド名だけで判断せず、根拠ある確認を行いましょう。
工務店は「柔軟性×現場力」で選ぶべき理由

工務店は、地域に密着したフットワークの軽さと、柔軟な対応力で多くの支持を集めています。「自由設計で思い通りの家を建てたい」という方には、大手にはない魅力があります。
一方で、会社ごとに技術力や管理体制の差が大きく、「選び方次第で満足度が大きく変わる依頼先」でもあります。ここでは、工務店を選ぶ際に確認すべき強み・注意点を整理していきます。
地域密着だからできる対応力とその裏返し
工務店の最大の特長は「地域に根差した家づくり」ができる点です。設計・施工・管理を同じ会社が一貫して担うケースが多く、要望が伝わりやすいことが強みです。
| 項目 | メリット | 注意点 |
| 対応スピード | 担当者との距離が近く、相談や変更も迅速に対応 | 組織体制が弱く、担当者に依存しがち |
| コスト感 | 中間マージンが少なく、コストパフォーマンスに優れる | 標準仕様が決まっていないため費用差が出やすい |
| 施工品質 | 現場に裁量があり、細やかな施工ができる | 現場管理が甘いと施工ミスにつながるリスクもある |
柔軟な家づくりができる反面、品質は「その会社の実力次第」で大きく変わります。
関連記事:狭小地・不整形地でも諦めない!L字・三角・旗竿地でも実現できる耐震等級3の家
工務店が得意とするポイント・不得意とするポイント
説明文付きリストで整理すると、以下のようになります。
自由設計への柔軟な対応
顧客の要望に応じて構造や仕様を柔軟に調整できるのが強みです。
細かな施工管理がしやすい
担当者が設計から現場まで一貫して把握している場合、対応がスムーズです。
品質・体制のバラつきがある
各社の力量に差があるため、選定次第でトラブルに直結するリスクもあります。
保証・アフターが不明瞭なことも
長期保証制度が整備されていない会社もあるため、契約前に確認が必要です。
自由度の高さは魅力ですが、それを支える体制があるかどうかが鍵となります。
関連記事:耐震等級3を活かすには?地盤調査と基礎工事で家の強さは決まる
耐震等級3を“形だけ”にしないために聞いておきたいこと
工務店に依頼する場合、「耐震等級3に対応可能です」と言われても、どのようなプロセスでその性能を実現しているのかを明確に把握することが重要です。表面的な説明にとどまる場合、構造安全性の保証が曖昧になりやすいため注意が必要です。
以下は、契約前に確認すべき代表的な質問事項です。
構造設計は誰が行っているか
自社の設計者か、外部の構造専門家かで精度や保証内容が異なります。
構造計算はどの方式で行われているか
簡易な壁量計算だけでなく、許容応力度計算が行われているか確認します。
耐震等級3の根拠となる書類は提示されるか
評価機関の認定書や構造計算書の有無が信頼性を左右します。
設計と施工の責任範囲はどう分かれているか
トラブル時に「どこが責任を負うか」を契約時に明文化しておくべきです。
これらを質問することで、“口だけの耐震等級3”か、“根拠ある性能”かが判断できます。
工務店の中には構造設計を建築士1人で担当しているケースもあります。構造と意匠の両立が求められるなかで、バランスのとれた設計がなされているかどうかは、建築士の実績や説明力から見極めることが可能です。
設計自由度が高い反面、設計者の力量に依存しやすい
工務店の魅力は、細かな要望にも対応できる設計自由度にあります。しかし、自由設計には「構造の安全性を担保できるか」という視点が欠かせません。
構造的に無理のある間取りや開口部の設計は、耐震性能を損なうリスクがあります。このとき、安全性を確保できるかどうかは「誰が設計を担当しているか」によって大きく異なります。
以下の点を事前に確認することで、安全とデザインのバランスを保つことが可能です。
設計者の構造設計の実績
住宅性能評価付きの物件を複数手がけているか。
意匠と構造の整合性の説明力
デザインと強度を両立させるための工夫や制約を明確に説明してくれるか。
実際の施工事例の開示
見学できるモデルハウスやOB邸があるかで、品質の確認がしやすくなります。
「希望の間取りが叶ったけど、耐震性が不安」では本末転倒です。デザインと構造の両面で信頼できる工務店を選ぶことが、安心できる家づくりに直結します。
工務店選びで後悔しないための“現地確認ポイント”
契約前に信頼性を見極めるうえで、資料や説明だけでなく「実際の現場を見ること」が非常に効果的です。とくに耐震等級3を目指すなら、構造的な工夫や施工精度を自分の目で確認しておくことが重要です。
以下は、工務店選びで活用すべき現地確認のポイントです。
構造見学会への参加
上棟直後の構造部分を見学できる機会があれば、耐力壁の配置や金物の施工精度が確認できます。
施工中の現場の整理整頓状況
現場が整っている工務店は、職人の意識や管理体制がしっかりしている可能性が高いです。
OB施主の自宅訪問・見学
実際に住んでいる人の話を聞くことで、アフター対応や住み心地まで見えてきます。
社長・担当者との対話内容
小規模工務店では経営者や担当者の理念が家づくりに直結しているため、考え方の相性を確認しましょう。
現地確認を通じて得られるのは「会社の実力」だけではなく、「相性」や「価値観の一致」です。資料やHPだけで判断せず、現場を見て納得できる会社を選ぶことが後悔しない最大の秘訣です。
設計事務所に依頼するなら「こだわりと安全性」の両立を

設計事務所は、「完全自由設計で理想の家を実現したい」と考える方にとって強力な選択肢です。空間設計の美しさや、他にはない独創的な間取りを形にできる点が最大の魅力です。
一方で、自由度の高さは設計者の力量によって安全性に差が生じるリスクも伴います。「デザイン性と耐震性能をどう両立するか」が、依頼前に見極めるべき最重要ポイントです。
他にはない間取りやデザインが実現できる反面…
設計事務所に依頼する最大のメリットは、敷地条件や生活スタイルに応じた完全オーダーメイドのプランニングが可能な点です。しかし、それが同時に構造設計の難度を高めることにもつながります。
以下に、設計事務所の特長を整理しました。
| 項目 | メリット | デメリット |
| 設計の自由度 | 狭小地や変形地でも柔軟に対応 | 構造の複雑化で耐震性を損なうおそれがある |
| デザイン性 | 独自性の高い外観・内装を実現しやすい | 意匠に偏ると耐震計画が後回しになりやすい |
| 構造設計の責任 | 自由設計に対応する構造の工夫が可能 | 設計者の力量や構造担当の有無で安全性に差が出る |
「個性」や「美しさ」を重視する場合ほど、構造面の確認が欠かせません。見た目のインパクトがある間取りでも、きちんと耐震性能が担保されているかを確認しましょう。
設計の自由度が高いほど、構造の責任分担が重要に
設計事務所での家づくりは、意匠設計(デザイン)と構造設計(安全性)の役割分担が明確になっていないと、設計段階で耐震性が後回しにされる恐れがあります。
とくに「構造設計を外部委託している」ケースでは、以下の点を契約前に確認しておくことが重要です。
意匠担当と構造担当の連携体制
両者の協議・確認プロセスが定期的に行われているかを確認しましょう。
構造図や計算書の提示有無
設計説明時に構造計算書や伏図(ふくず)を開示できるかで信頼性が分かります。
設計変更時の構造影響への説明力
間取り変更のたびに構造への影響を説明できるかが、プロとしての力量を示します。
デザインを追求するほど、安全性とのバランス調整が欠かせません。意匠・構造の両軸で妥協のない設計体制を整えている事務所こそ、安心して任せられる依頼先です。
アフターや施工管理は設計者任せで本当に大丈夫?
設計事務所に依頼する場合、設計と施工が別会社になる「分離発注方式」を採用するケースが多くなります。この方式にはコスト調整や中立性のメリットがある一方で、施工管理やアフターサービスの責任が曖昧になるリスクがあります。
以下のポイントを事前に確認しておくことが大切です。
施工会社の選定プロセス
設計者が推薦する業者なのか、施主が自分で探す必要があるのか。
現場監理の実施体制
設計者が定期的に現場に足を運び、図面通りに施工されているか確認する頻度。
引き渡し後のトラブル対応
アフターサービスの窓口が施工会社なのか、設計者経由なのかを明確にしておきます。
施工とアフターを別の会社が担う場合は、責任の所在が曖昧になりがちです。「完成したら終わり」ではなく、住み始めてからも安心できる体制が整っているかを確認しましょう。
設計事務所を選ぶときに聞くべき5つの質問
設計事務所は魅力的な依頼先である一方、設計者の実力・考え方によって仕上がりに大きな差が生まれます。「耐震等級3の実現」を本気で目指すなら、以下の質問を遠慮せずに投げかけることが重要です。
耐震等級3の設計実績はどれくらいありますか?
構造計算付きで耐震等級3を取得した案件数が目安になります。
意匠設計と構造設計はどのように分担していますか?
自社内で完結か、外部委託か、その連携体制を確認しましょう。
間取りの自由度と耐震性の両立はどう実現していますか?
デザイン優先ではなく、構造的な裏付けがあるかをチェック。
使用している構造計算ソフトや方式を教えてください
許容応力度計算など、計算方式の説明ができるかが重要です。
施工会社との関係性と、監理の頻度はどれくらいですか?
分離発注の場合でも、設計監理にどれだけ関与してくれるかを確認します。
この5つの質問に対して、納得のいく答えを得られるかどうかが選定の分かれ道です。技術・経験・対応力を総合的に見極めて、後悔のない依頼先を見つけましょう。
施工先選びがカギ!理想の「耐震等級3住宅」を叶える最初の一歩

「耐震等級3」を本気で目指すなら、住宅性能そのものだけでなく、その性能を実現できる施工先との出会いこそが最初のカギです。構造計算の有無や設計の自由度、保証内容といった要素は、どの依頼先を選ぶかによって大きく異なります。
以下に、選定時に押さえておきたい要点を整理しました。
| 観点 | ハウスメーカー | 工務店 | 設計事務所 |
| 対応力 | 全国対応、体制が整っている | 地域密着で柔軟 | 担当者次第で大きく異なる |
| 設計の自由度 | 一部カスタマイズ可能 | 高い | 非常に高い |
| 構造の信頼性 | 自社基準が多く確認が必要 | 設計者次第 | 設計体制の明確化が重要 |
| 費用感 | 中〜高価格帯 | 中価格帯〜内容次第 | 設計料と施工分離でコントロール可能 |
| アフターサポート | 長期保証だが条件確認が必須 | 対応力にばらつきあり | 施工会社依存、監理体制の確認が必要 |
どの依頼先にもメリットとリスクがあるからこそ、「自分に合ったスタイル」を見極める視点が欠かせません。情報を集め、実績を比較し、説明に納得できる相手と出会うことが、理想の耐震住宅づくりへの第一歩となります。
そして、どの選択肢を選ぶにせよ、「耐震等級3」を実現するには、設計・構造・施工が一体で機能していることが何より重要です。不明点を残さず、納得して契約できる体制を整えた依頼先を見つけてください。
関連記事:耐震等級3住宅のスケジュール全公開!設計から引っ越しまで完全解説
憧れの大手メーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれる

住宅展示場や完成見学会にいくのは時間もかかるし大変…
そんなときに便利なのが「タウンライフ家づくり」です。
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
気になるメーカーや工務店を選び、希望の間取りや予算を入力するだけ。「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる!
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。

「タウンライフ家づくり」はこんな方におすすめ
- あなただけの間取りと見積もりを無料で手に入れ比較したい
- 営業されるのが嫌、苦手
- 自宅でじっくり信頼できるハウスメーカーを選びたい
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ




