この記事にはプロモーション・広告が含まれています
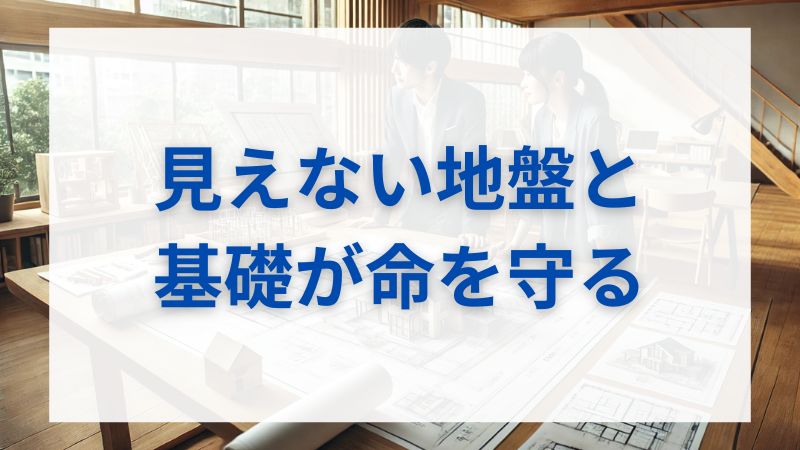
地震が多発する日本において、家づくりにおける耐震性能は命と資産を守るために欠かせない要素です。とくに「耐震等級3」は、建築基準法の1.5倍の地震力に耐える最高等級であり、多くの家庭が目指すべき水準です。
関連記事:耐震等級3で家族を守る!地震に強い家を作るための完全ガイド
しかし、耐震等級3の家が本当に安心・安全な家になるかどうかは、「構造計算」や「設計」だけでは決まりません。家の土台を支える「地盤調査」や「基礎工事」が適切に行われていなければ、設計上は等級3でも、現実の地震に耐えられない危険性があります。
本記事では、耐震等級3を目指す住宅づくりにおいて軽視されがちな「地盤」と「基礎」の重要性について詳しく解説します。見落としがちな施工前の準備工程を正しく理解し、家族の命を守る本当に強い家をつくりましょう。
構造だけで安心できる?耐震等級3の本当の意味とは

耐震等級3は「地震に強い家」の象徴ともいえる等級ですが、見落とされがちな落とし穴が存在します。制度が評価するのは“設計上の性能”であり、実際の地盤や施工品質は評価の対象外なのです。
耐震等級の基礎知識と誤解
耐震等級は以下のように区分されます。
| 等級 | 耐震性能の目安 |
| 等級1 | 建築基準法の最低限を満たす性能 |
| 等級2 | 等級1の1.25倍の耐震性能 |
| 等級3 | 等級1の1.5倍の耐震性能(最高等級) |
耐震等級3=絶対に安全という誤解が広がっていますが、これは大きな間違いです。評価の対象はあくまで構造設計であり、以下の点は含まれていません。
- 施工現場での精度やミスの有無
- 実際の地盤の強度や地耐力
- 基礎工事の施工品質や設計との整合性
そのため、いくら設計上は等級3でも、実際には耐震性能が十分に発揮されないケースも存在します。
評価基準の落とし穴:構造しか見ていない?
耐震等級評価における主な課題は以下の通りです。
構造設計だけで評価される
評価の対象は図面上の構造のみで、現場での施工や地盤状況は加味されません。
地盤と基礎は評価外
軟弱地盤や不同沈下のリスクがある場合でも、設計図面が整っていれば等級3の取得は可能です。
安全な施工かどうかは自己責任
実際の耐震性能は、施工会社の技術力や現場管理の精度に大きく左右されます。
このような背景を理解せずに「等級3だから安心」と思い込むことは危険です。本当に安心な家とは、“地盤と施工の信頼性”を備えた家であることを忘れてはいけません。
地盤調査の重要性

耐震等級3を実現するために、設計や構造計算ばかりに目を向けていませんか?前提として最も重要なのが「地震に耐えうる強い地盤」です。どれほど優れた設計をしても、弱い地盤の上では本来の性能を発揮できません。
関連記事:【地震に備える家づくり】耐震等級3の設計基準と施主が知っておくべき注意点
住宅は地盤の上に建つものです。地盤の強さ=家の土台の信頼性を意味します。調査を行わずに建築を進めるのは、例えるなら「泥の上に立派な家を建てるようなもの」です。
以下では、地盤調査の意義や方法、その活用法について具体的に解説します。
地盤調査の目的と意義
地盤調査には建物の重量に地盤が耐えられるかを確認し、安全な基礎設計を行うという明確な目的があります。
地盤の強度を無視した建築には、以下のようなリスクが伴います。
- 建物の傾き(不同沈下)
- 基礎の割れや破損
- 耐震性能の低下
これらは設計上の耐震等級とは無関係に起こります。つまり、耐震等級3でも“地盤次第で意味が薄れる”という事実を認識する必要があります。
主な地盤調査方法
住宅建築で一般的に用いられる地盤調査は主に2つです。
| 調査方法 | 特徴 |
| スウェーデン式サウンディング試験(SWS) | 簡易でコストが低く、小規模住宅に多く採用される |
| ボーリング試験 | 精度が高く、深層の地盤状況まで把握できる |
それぞれの調査方法には適した使い分けがあり、建物の規模や地形条件によって選定されます。以下で詳細を確認しましょう。
関連記事:狭小地・不整形地でも諦めない!L字・三角・旗竿地でも実現できる耐震等級3の家
スウェーデン式サウンディング試験(SWS試験)
スクリュー状のロッドに荷重をかけ、回転数と沈下量を計測する方法です。5〜10m程度までの浅い地盤調査に適しており、木造住宅に最も多く使われます。
- メリット:安価で手軽に実施可能
- デメリット:深層地盤までの把握には不向き
地耐力の目安を迅速に知りたい場合に有効な方法といえます。
ボーリング試験
専用の掘削機で地盤を深く掘削し、地層サンプルを採取して解析する方法です。支持層の有無や液状化のリスクまで詳細に把握できます。
- メリット:正確なデータが得られ、信頼性が高い
- デメリット:コストが高く、工期が長くなる傾向
軟弱地盤が疑われる地域や、地盤改良の要否判断に最適な手法です。
地盤調査結果の活用
調査結果は、地盤の強度に応じて基礎の設計や地盤改良の要否を判断する重要な材料です。適切に活用することで、より確実な耐震性を備えた住宅づくりが可能になります。
関連記事:耐震等級3の坪単価は本当に高い?差額・効果・後悔しない選び方を徹底解説
調査報告書の見方
地盤調査の結果は、専門用語が多くてわかりにくいものですが、以下のポイントを押さえれば理解が進みます。
- 地耐力(kN/m²):地盤が支えられる重さの指標
- N値:地盤の硬さや密度を示す値
- 支持層の深さ:基礎を支える硬い地層までの距離
| 用語 | 意味 |
| 地耐力 | 地盤が耐えられる最大荷重の目安 |
| N値 | 地盤の硬さ(数値が高いほど硬い) |
| 支持層 | 建物を支えるのに適した安定した地層 |
これらの数値が、基礎工事の方式や地盤改良の要否を判断する基準になります。
専門家に確認すべきポイント
調査結果を手にしたら、建築士や施工会社に以下の点を確認すると安心です。
- 「この地盤にベタ基礎で対応できますか?」
- 「地盤改良が必要な根拠は何ですか?」
- 「このN値で不同沈下のリスクはありませんか?」
不安な点を放置せず、専門家と納得いくまで対話を重ねることが重要です。建ててからでは取り返しがつかないため、事前の確認がすべてを左右します。
関連記事:【徹底比較】耐震等級3の家づくりで後悔しない依頼先の選び方|ハウスメーカー・工務店・設計事務所の違い
地盤改良の必要性と方法

地盤調査の結果、地耐力が不足している場合や不同沈下の可能性がある場合には、必ず「地盤改良」が必要です。これを怠ると、耐震等級3の設計でも家が傾いたり、基礎が損傷したりして、耐震性が発揮されません。
耐震性の信頼性は、設計よりもむしろ地盤処理の質に大きく左右されると言っても過言ではありません。地盤改良は「見えない工程」ですが、家づくりで最も重要なステップのひとつです。
関連記事:後悔しない!耐震等級3の家づくりに欠かせない施工業者の選び方とチェックポイント
地盤改良が必要なケース
以下のようなケースでは、地盤改良が必要と判断される可能性が高くなります。
- 地耐力が30kN/m²未満
- 造成地や埋立地に建設予定
- 地盤調査で支持層が深いと判明
- 液状化のリスクがある地域
新興住宅地では表面のみが整備されており、深部に不安定な地盤が残っていることもあります。表層が固くても油断は禁物です。
主な地盤改良工法
住宅規模の地盤改良には、地盤の状態や必要な支持力に応じていくつかの代表的な工法があります。
| 工法名 | 特徴 |
| 表層改良 | 表面1〜2mの地盤を固化する低コスト工法 |
| 柱状改良 | 地中に固化柱を築くバランス型工法 |
| 鋼管杭工法 | 支持層まで鋼管杭で支持する高耐力工法 |
それぞれの工法にはメリット・デメリットがあり、敷地条件や建物規模に応じた適切な選定が求められます。以下で各工法の具体的な内容を解説します。
表層改良
表層改良は、地表から1〜2メートルの範囲にセメント系固化材を混ぜて地盤を強化する方法です。施工が比較的簡単でコストも抑えられるため、多くの住宅で採用されています。
- 適用条件:浅い支持層があり、地盤の改善範囲が表層に限られる場合
- メリット:施工費用が安く、短期間で完了可能
- デメリット:深い軟弱層がある場合には対応不可
一般的な住宅地で使われる最もポピュラーな工法ですが、適用できる地盤条件には限りがあります。
柱状改良
地中に円柱状の改良体(セメント柱)を造成し建物を支える工法です。地表から支持層まで届かない場合でも、地中で安定性を確保できます。
- 適用条件:支持層が2〜8m程度の深さにある場合
- メリット:広範囲な地盤に対応可能で、支持力も高い
- デメリット:施工コストが表層改良より高くなる傾向
軟弱地盤に広く対応でき安定性も高いため、採用実績が非常に多いのが特徴です。
鋼管杭工法
支持層まで鋼製の杭を打ち込み建物を杭で直接支える工法です。支持層が深い場合や高耐力が必要な場合に使用されます。
- 適用条件:支持層が深く、通常の改良で対応が難しい地盤
- メリット:非常に高い耐力と耐久性が得られる
- デメリット:施工費用が高く、専門機材が必要
地盤条件が厳しい場所や、大型建物に適した高性能工法ですが、コスト面では注意が必要です。
地盤改良工事で失敗しないために
地盤改良は「見えない工事」であり、施主が施工品質を直接確認することは難しいものです。だからこそ、以下の点をしっかり押さえておくことで、トラブルを未然に防ぐ必要があります。
工法選定の根拠を必ず確認する
なぜその工法が選ばれたのか、調査結果との整合性が取れているかを施工会社に確認しましょう。
施工計画書と改良範囲の説明を受ける
改良の深さや範囲、使用材料などが明示された書面をもらい、内容を理解しておくことが大切です。
第三者機関の検査を活用する
保険法人による地盤改良工事の中間検査などを活用することで、見えない部分の品質確保が可能になります。
地盤改良は住宅の安全性を大きく左右する重大な工事です。判断を施工業者に任せきりにせず、施主自身が納得のいく確認を行うことが、安心につながります。
基礎工事の種類と選定ポイント

家を支える「基礎」は、地震の揺れから建物全体を守る役割を果たします。どれだけ構造設計や耐震等級が優れていても、基礎の種類や施工品質が不適切であれば、その性能は大きく損なわれます。
関連記事:【保存版】耐震等級3の家はいくらかかる?総費用と賢い資金計画の立て方
地盤の状態や建物の構造に応じて、最適な基礎工事を選定する必要があります。ここでは、代表的な基礎工法であるベタ基礎と布基礎の違いや選定のポイントを詳しく解説します。
ベタ基礎と布基礎の違い
住宅の基礎工法には、大きく分けて「ベタ基礎」と「布基礎」の2種類があります。それぞれの構造的特徴を把握し、適切な工法を選ぶことが重要です。
| 基礎の種類 | 特徴 |
| ベタ基礎 | 地面全体に鉄筋コンクリートを打設 |
| 布基礎 | 建物の外周や間仕切り下に帯状の基礎を配置 |
それぞれの工法にはメリット・デメリットがあり、地盤の性質やコスト、施工のしやすさに応じて使い分けがされます。以下で具体的に見ていきましょう。
ベタ基礎の特徴
ベタ基礎は、建物の床全体を厚い鉄筋コンクリートで覆う工法で、面全体で建物の荷重を分散させます。軟弱地盤にも比較的強く、地震の揺れにも安定した強度を発揮します。
- 耐震性:荷重が広く分散されるため、地震に強い構造となります。
- 湿気対策:地面からの湿気を抑制しやすく、カビや白アリの対策にも有効です。
- コスト面:コンクリートや鉄筋の使用量が多く、布基礎よりも費用が高くなりがちです。
耐震性と耐久性を重視するなら、ベタ基礎が第一選択肢となるケースが多いです。
布基礎の特徴
布基礎は、建物の壁の下に帯状にコンクリート基礎を設ける工法です。地面全体を覆わない分コストは抑えられますが、地盤によっては沈下や傾きのリスクが生じます。
- コスト面:資材・施工費用が抑えられ、予算にやさしい工法です。
- 施工性:ベタ基礎より簡易で、着工から完了までの期間が短い傾向があります。
- 地盤依存性:地盤が弱い場合には、不同沈下のリスクが高くなります。
地盤が十分に強固であれば有効な選択肢ですが、リスク評価が不可欠です。
基礎の選定基準
適切な基礎工法の選定は、地盤の状態や建物構造を踏まえて慎重に行う必要があります。一律に「ベタ基礎が安心」と決めつけず、条件に応じた判断が求められます。
以下は、基礎選定時に確認すべき主なポイントです。
地耐力の数値
地盤調査で得られた地耐力が小さい場合は、面で支えるベタ基礎が有利です。
建物の構造・重量
重量鉄骨やRC構造のように重い建物は、ベタ基礎が基本となります。
建設地の地盤履歴
埋立地や造成地は不同沈下リスクが高く、基礎強化や地盤改良が必要になります。
湿気・白アリへの配慮
湿気が多い地域や白アリの被害が懸念されるエリアでは、ベタ基礎が優位になります。
予算とのバランス
耐震性だけでなく、コストも検討要素となります。構造設計者としっかり相談しましょう。
基礎は「建物の足元」です。足元が不安定な家に、真の耐震性は望めません。調査と設計をもとに、納得できる根拠ある選定を行うことが大切です。
住宅性能表示制度に足りない視点とは?地盤・基礎が“見えない評価”になる理由

耐震等級3を取得した家でも、地震で被害を受けるケースがあります。その一因が、「住宅性能表示制度」において地盤調査や基礎工事の品質が評価に反映されないという構造的な問題です。
制度上の評価基準と、現場での実際の施工内容とのギャップを正しく理解することが、安全な家づくりへの第一歩となります。
関連記事:【保存版】耐震等級3を確実に取る!設計審査の書類・手続き完全マニュアル
制度の目的と限界を正しく理解する
住宅性能表示制度は、国土交通省が定めた「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の性能を客観的に評価・表示する仕組みです。耐震性、省エネ性、劣化対策などを数値で表すことができ、施主にとっての「比較・選択の基準」となります。
しかしその一方で、制度には以下のような限界があります。
評価は設計図面に基づいて行われる
実際の施工状況は含まれず、机上の設計どおりに正しく施工されているかは確認されません。
施工中の品質管理は対象外
地盤調査の実施内容や基礎工事の品質は、制度の評価には含まれていません。
施工業者の技量や現場管理の差が無視される
実際には大きな影響を与える施工力が、制度では数値化されないのです。
| 項目 | 評価対象に含まれるか |
| 構造設計の内容 | ○ |
| 地盤調査の実施内容 | × |
| 基礎工事の施工精度 | × |
| 工務店の施工管理体制 | × |
つまり、設計図面どおりに家が完成しているとは限らない点に注意が必要です。制度の限界を認識することで、見落とされがちなリスクに目を向けることができます。
「耐震等級3」の過信を避けるために
耐震等級3という評価を得ると、「これで安心」と思ってしまいがちです。しかし、その評価は「設計上の強さ」にすぎず、「実際の施工精度」や「地盤の安定性」とは別物です。
見落としがちなポイントは以下の通りです。
- 設計通りに配筋・打設されていない基礎
- 不十分な地盤調査による不同沈下リスク
- 改良が必要な地盤に対して施工が未実施
これらの要素が一つでも欠ければ、耐震等級3の家でも大きな被害を受けるリスクがあるのです。
制度が評価していない部分まで含めて注意を払うために、施主自身が主体的に動くことが大切です。以下のような行動が、安全な家づくりにつながります。
- 地盤調査の内容と結果を必ず確認する
- 必要に応じて地盤改良の施工内容を把握する
- 基礎工事の現場を見学・質問する
- 完成前に第三者の検査を受ける
見えない部分にこそリスクが潜んでいることを認識し、制度の「安心感」に依存しすぎない姿勢が重要です。本当に強い家を建てるには、設計・制度の枠を超えた「現場の実態」への目配りが求められます。
ハウスメーカー・工務店選びの注意点

耐震等級3を目指すうえで、どの会社に家づくりを依頼するかは極めて重要な判断です。設計上の性能はあくまで「理論上の強さ」であり、それを現実の建物として正しく形にできるかどうかは、施工会社の力量次第です。
関連記事:【要確認】モデルハウスで“本物の耐震等級3”を見抜く5つの視点とは?
地盤調査や基礎工事は、目に見えない部分であるため、業者の対応力や管理体制が仕上がりの質を大きく左右します。
施工管理力の重要性
施工管理とは、設計通りに正確かつ丁寧に工事が進んでいるかをチェックし、品質を保証するプロセスです。これが疎かになると、設計図通りの強度が得られないばかりか、施工ミスによる欠陥が後から発覚する恐れもあります。
以下は、施工管理体制に信頼がおける会社かを見極めるポイントです。
現場監督が常駐しているか確認する
現場のチェックを適切に行う体制があるかどうかは、施工品質を守る基本です。
第三者機関による検査を導入しているか
社内検査だけでなく、外部機関の中間検査や完了検査を採用しているかを確認しましょう。
担当者が調査結果や施工計画を丁寧に説明してくれるか
技術的な内容を分かりやすく説明できるかどうかも、信頼性を判断する材料になります。
アフターサービス体制が明確か
施工後に不具合が起きた場合の対応や、保証内容も重要な比較ポイントです。
高性能な家は、「設計」だけでなく「施工」があってこそ成立することを忘れてはいけません。
地盤調査と基礎工事の対応力
どれだけ優れた設計を行っても、現場での判断や対応が不適切であれば、家の耐震性は保てません。施工会社の「地盤調査」「基礎工事」に対する取り組み姿勢を事前に確認することが極めて重要です。
以下のような視点で比較・検討することをおすすめします。
地盤調査の内容を公開しているか
調査方法やその結果について、施主にもわかりやすく説明してくれる会社は信頼性が高いです。
必要に応じて複数の調査手法を使い分けているか
スウェーデン式サウンディング試験だけでなく、ボーリング試験なども活用できる体制か確認しましょう。
地盤改良の判断と説明が的確か
改良工事の根拠や仕様について、数値データと共に説明があるかが重要です。
基礎の施工精度に関する実績があるか
ベタ基礎・布基礎を適切に施工した事例や、配筋写真を公開している会社は信頼できます。
| 比較ポイント | 評価の基準例 |
| 調査・改良の透明性 | 結果をわかりやすく説明してくれる |
| 多様な調査手法の活用 | 地盤条件に応じた選定ができる |
| 改良根拠の明確さ | 数値に基づく説明がある |
| 施工精度の実績 | 写真・データで確認できる |
信頼できる施工会社は「目に見えない工程」にも自信を持って説明できます。家づくりのパートナー選びでは、こうした技術力と誠実さの両方を備えた会社を見極めましょう。
「耐震等級3」を真に活かす家づくりのカギは、地盤と基礎にある

耐震等級3の家づくりにおいて、構造設計や評定数値だけに目を向けていては、本当の意味での「地震に強い家」は実現できません。家を支える土台である地盤と基礎こそが、見えないがゆえに最も重要な要素であることを、この記事を通じて理解いただけたのではないでしょうか。
関連記事:【保存版】住宅の引き渡し時に絶対見るべき!後悔しないためのチェックリスト
- 地盤調査で「建てられる地盤かどうか」を見極める
- 地盤改良で「揺れに耐える下地」を作る
- 基礎工事で「荷重を受け止める構造」を築く
この3つは、いずれも耐震性の土台であり、「等級3」の信頼性を現実の強さへ変える鍵です。
関連記事:【2025年法改正】耐震等級3が事実上の義務に!建築基準法改正で家づくりはどう変わる?
そしてそれを確実に実行するためには、「誰に家づくりを任せるか」という選択が決定的に重要になります。施工管理力・調査対応力に優れた会社を選ぶことが、家族の命と資産を守る最善の判断です。
まずは、信頼できる施工会社を複数比較し、自分の理想を実現できるパートナーを見つけましょう。
憧れの大手メーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれる

住宅展示場や完成見学会にいくのは時間もかかるし大変…
そんなときに便利なのが「タウンライフ家づくり」です。
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
気になるメーカーや工務店を選び、希望の間取りや予算を入力するだけ。「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる!
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。

「タウンライフ家づくり」はこんな方におすすめ
- あなただけの間取りと見積もりを無料で手に入れ比較したい
- 営業されるのが嫌、苦手
- 自宅でじっくり信頼できるハウスメーカーを選びたい
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ




