この記事にはプロモーション・広告が含まれています
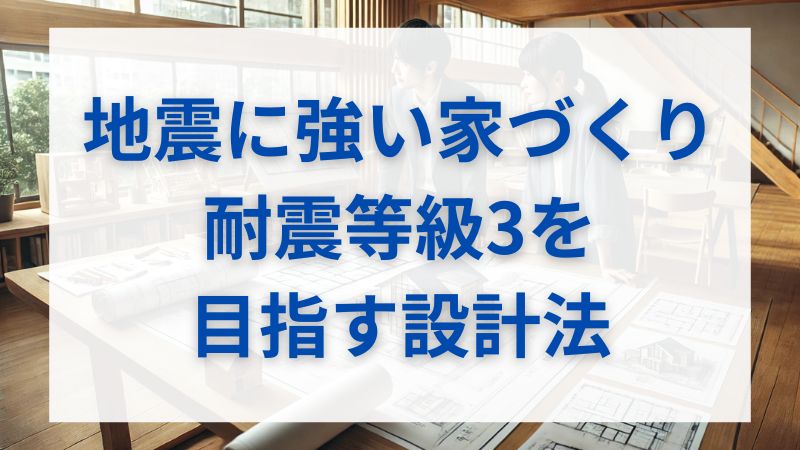
近年、日本各地で発生する大地震を受けて、住宅の耐震性能への関心がますます高まっています。その中でも、国が定めた最高基準である「耐震等級3」の住宅は、将来の大震災にも耐えうる安全な住まいとして注目されています。
関連記事:【保存版】耐震等級3の家はいくらかかる?総費用と賢い資金計画の立て方
新築住宅を計画する施主にとって、「どのような素材を選べばいいのか」「どんな設計上の工夫が必要なのか」といった疑問を持つ方は多いでしょう。単に「頑丈に作る」だけでは実現できないのが、耐震等級3の家です。
耐震等級3の住宅は、素材の選定から構造設計、基礎の仕様に至るまで、細かなバランスと検証が必要な高水準の住まいです。
関連記事:【地震に備える家づくり】耐震等級3の設計基準と施主が知っておくべき注意点
本記事では、これから家づくりを始める施主のために、地震に強い住宅を実現するための素材と構造設計のポイントを詳しく解説していきます。
設計段階での注意点や建築士との連携、構造ごとの特徴や選定基準までをわかりやすくまとめてお届けします。大切な家族を守る「地震に負けない家づくり」を成功させるための知識を、ぜひここで身につけてください。
構造設計におけるバランスの重要性

地震に強い家づくりの基本は、建物全体の構造バランスにあります。どれだけ強固な素材を使っても、構造的に偏った設計では、その力を発揮しきれません。
建物がバランスよく地震の揺れを受け流すためには、柱や壁の配置・吹き抜けの扱いなど、構造全体の整合性が極めて重要です。
関連記事:狭小地・不整形地でも諦めない!L字・三角・旗竿地でも実現できる耐震等級3の家
関連記事:耐震等級3を活かすには?地盤調査と基礎工事で家の強さは決まる
ここでは、バランス設計における具体的な工夫と検討ポイントを紹介します。
構造グリッドの設定
建物の柱・壁などの垂直構造部材は、上下階で揃えることで力の伝達がスムーズになります。これを「構造グリッドを揃える」と呼びます。
構造グリッドが整った設計
上下階で柱や壁の位置を合わせることで、地震の力を真っ直ぐ伝え、ねじれや崩壊のリスクを軽減します。
構造グリッドがずれた設計
柱や壁の位置が上下階でズレていると、力がうまく伝わらず、局所的に構造部材に大きな負担がかかります。
| グリッド状態 | 構造への影響 |
| 揃っている | 力の伝達がスムーズで、揺れに強い構造になる |
| ずれている | 力が分散せず、建物にねじれや傾きが生じやすい |
関連記事:【徹底比較】在来工法とツーバイフォー、耐震等級3で本当に安心なのはどっち?
直下率の確保
直下率とは、2階の柱や壁がどれだけ1階の柱や壁と一致しているかを示す指標です。耐震等級3を狙うなら、この直下率が高い設計が求められます。
直下率が高い設計
地震力を効率よく地面に逃がすことができ、全体の構造安定性が高まります。
直下率が低い設計
一部の部材に過度な力が集中し、局所破壊や変形を招く恐れがあります。
吹き抜けや大開口部の影響
開放感のある吹き抜けや広い窓は人気の設計要素ですが、構造的には注意が必要です。
吹き抜けがある場合
上下階の壁や柱が失われることで、直下率が下がり、バランスを崩しやすくなります。
大きな開口部がある場合
耐力壁が減るため、必要な耐震性能を確保するには補強材や特殊な構法の導入が必要になります。
視覚的なデザインや空間演出を重視する場合でも、構造的バランスを犠牲にしない設計が重要です。
建築士と相談しながら、安全性とデザインの両立を目指しましょう。
素材選びのポイント

耐震性を高めるには、使用する構造素材の選定も非常に重要です。設計の工夫だけでなく、建物を構成する素材そのものが地震に対する耐性に大きな影響を与えます。
構造素材は建物の重量・しなり方・破壊の仕方に関係し、耐震設計の前提を根本から左右します。
ここでは、主な構造素材の特徴を比較し、耐震等級3の実現における視点から見た選び方を紹介します。
木造、鉄骨造、RC造の比較
住宅の構造には主に「木造」「鉄骨造」「RC(鉄筋コンクリート)造」の3つがあります。それぞれに耐震性・コスト・施工性といった特徴があり、どれが優れているかは一概には言えません。
| 構造種別 | 特徴 | 耐震性の傾向 | メリット | デメリット |
| 木造 | 軽量で加工しやすい | 揺れに対して柔軟に対応 | コストが安く、省エネ性も高い | 設計の自由度にやや制限あり |
| 鉄骨造 | 柱・梁が鋼材 | 強度が高く、変形に強い | 間取りの自由度が高い | 熱伝導性が高く断熱に工夫が必要 |
| RC造 | コンクリートと鉄筋の複合 | 極めて堅牢で耐震性が高い | 耐火性・遮音性に優れる | 重量があるため基礎に負担がかかる |
どの構造でも耐震等級3は取得可能ですが、設計者と相談して適材適所の選択が重要です。
制振材・構造用合板の活用
建物の「しなり」や「揺れの吸収」を制御するために、制振材や構造用合板を効果的に使うことで、より実効的な耐震性を実現できます。
制振材の導入
地震時の揺れを吸収・分散し、構造体にかかる負荷を減らす。吹き抜けのある住宅や大開口のある間取りで有効。
構造用合板の設置
建物の面剛性を高め、横揺れに対する抵抗力を強化する。耐力壁の一部として効果を発揮。
面材工法との組み合わせ
軸組と面材を一体化させることで、壁全体として揺れに強くなる構造を実現できる。
見た目ではわからない内部構造への工夫こそが、真の耐震性を支える重要な要素です。
設計初期から「揺れにどう対応するか」を素材レベルで議論することが、耐震等級3取得への近道となります。
屋根の重量と耐震性の関係

住宅の耐震性を高めるうえで、屋根の重量は見過ごされがちですが、構造全体に大きな影響を与える要素の一つです。地震時には、建物の上部が重ければ重いほど揺れの影響を受けやすくなります。
重い屋根は建物の重心を高くし、揺れによる転倒やねじれのリスクを高める原因になります。
そのため、耐震等級3を目指す住宅では、屋根材の選定にも慎重さが求められます。
屋根材の種類と重さの違い
各種屋根材は見た目や機能性だけでなく、重量にも大きな差があります。以下に代表的な屋根材の重量を比較します。
| 屋根材の種類 | 重量(1㎡あたり) | 特徴 |
| 瓦(和瓦・陶器瓦) | 約40〜60kg | 重厚感があり耐久性が高いが、地震に不利な重量 |
| スレート(コロニアル) | 約18〜20kg | 軽量で普及率が高く、デザイン性も豊か |
| 金属屋根(ガルバリウム鋼板など) | 約5〜10kg | 非常に軽量で耐震性に優れ、メンテナンス性も良好 |
屋根材の重量を軽くするだけでも、建物全体の地震時の揺れを大幅に軽減する効果があります。
2階建て以上の住宅では、その差が顕著に表れます。
軽量屋根のメリットと注意点
耐震性の向上
建物上部の重量が軽くなることで、揺れの際の振り幅や応力が小さくなる。
施工のしやすさ
軽量素材は扱いやすく、施工期間の短縮にもつながる。
注意点:遮音・断熱性
軽量屋根は音や熱を通しやすい傾向があるため、断熱材や遮音材を併用する必要がある。
軽量化によるメリットを最大化するには、屋根だけでなく壁・基礎とのトータルバランス設計が不可欠です。
屋根選びも「デザイン」だけでなく「構造安全性」の観点から考えましょう。
関連記事:家族の命を守る防災住宅──地震に「強い家」で暮らそう
許容応力度計算の重要性

耐震等級3を取得するためには、建物の構造が厳密に計算・検証されていることが求められます。その中でも重要なのが「許容応力度計算」です。
許容応力度計算は、建物の各部材が地震などの外力を受けたときに、安全な範囲内で耐えられるかを判断するための構造計算方式です。
壁の枚数や配置だけで評価する「壁量計算」よりも、精密な安全性の評価が可能になります。
関連記事:【2025年法改正】耐震等級3が事実上の義務に!建築基準法改正で家づくりはどう変わる?
壁量計算と許容応力度計算の違い
| 比較項目 | 壁量計算 | 許容応力度計算 |
| 精度 | 簡易的 | 高精度 |
| 検証内容 | 壁の量やバランス | 部材1本ごとの強度や接合部の応力まで検証 |
| 使用条件 | 耐震等級1や2に多い | 耐震等級3ではほぼ必須 |
| 施工の自由度 | 高め | 制限ありだが確実な設計が可能 |
壁量計算は早く簡単に設計できますが、安全性はあくまで目安レベルです。一方で、許容応力度計算は手間がかかる反面、根拠ある強度設計が可能になります。
関連記事:【保存版】耐震等級3を確実に取る!設計審査の書類・手続き完全マニュアル
設計段階での検証ポイント
耐震等級3の取得を見据えた設計では、以下のような要素を事前に細かく検討・計算する必要があります。
基礎や土台の断面と強度
地震時に負荷が集中する基礎周りは、材料や形状によって安全性が左右されます。
接合部の補強金物の選定
柱や梁の接合部は、揺れによって最も破断しやすい部分。適切な金物と設置方法の選定が不可欠です。
梁や柱のたわみ量・たわみ制限の確認
揺れによる部材の変形量が過度になると、構造的な崩壊につながります。
これらを全て構造計算ソフトやエンジニアリング手法で確認し、安全が証明された設計であることが耐震等級3には求められます。
単に見た目の安心感ではなく、数値で証明された安全性こそが「等級3」の信頼につながるのです。
関連記事:耐震等級3住宅のスケジュール全公開!設計から引っ越しまで完全解説
関連記事:後悔しない!耐震等級3の家づくりに欠かせない施工業者の選び方とチェックポイント
基礎設計のポイント

耐震性の高い住宅を実現するためには、建物を支える「基礎」の設計が極めて重要です。地震の力はまず地盤から伝わり、基礎を通じて建物全体に作用します。
基礎が不安定であれば、どれだけ強固な構造でも揺れに耐えられません。
ここでは、耐震等級3を実現するために押さえるべき基礎設計の重要ポイントを紹介します。
べた基礎と地中梁の役割
べた基礎は、建物の荷重を面で受け止める工法で、耐震性能を高める基本的な構造形式のひとつです。地中梁を組み合わせることで剛性が向上し、地震時の変形を抑える効果が期待できます。
| 項目 | 詳細内容 |
| べた基礎 | 建物全体の荷重を均等に地盤へ伝える。地震時の不同沈下に強い。 |
| 布基礎 | 狭小住宅などで採用されるが、べた基礎に比べ耐震性は劣る。 |
| 地中梁 | 基礎スラブ内に梁を設け、剛性を高める。吹き抜けなどの構造弱点部に有効。 |
地盤の状態が良くない場合
表層改良や柱状改良など、地盤補強工法と組み合わせることで、基礎の安定性を高められます。
構造的な不整形建物の場合
地中梁の配置を工夫することで、荷重バランスの偏りを調整できます。
人通口の設置と補強
基礎内の点検や配管経路の確保のために「人通口」と呼ばれる開口部を設ける場合、その周囲の構造補強が重要になります。
開口部の補強金物の設置
開口部は構造的な弱点となりやすいため、鉄筋を追加したり、開口補強金物を使用して耐力を確保します。
開口部のサイズ・位置の工夫
極端に大きな開口は避け、基礎の隅や応力集中が予測される位置には設置しないようにします。
基礎設計では、安全性とメンテナンス性の両立が求められます。
構造計算だけでなく、実際の暮らしやすさまで見据えた設計判断が重要です。建築士と連携しながら、合理的で安全な基礎づくりを進めましょう。
建築士との打ち合わせポイント

耐震等級3の住宅を実現するためには、設計段階からしっかりと建築士と連携を取ることが不可欠です。耐震性能を確保するためには、専門家の知識を活かした綿密な打ち合わせが求められます。
建築士との打ち合わせでは、単にデザインや間取りだけでなく、耐震性を高めるための設計意図や具体的な手法についても確認することが重要です。
以下に、打ち合わせ時に確認すべきポイントを挙げます。
設計意図の共有
耐震等級3を目指す場合、ただ単に強固な構造を作るのではなく、地震時に建物全体が適切に機能するように設計を進める必要があります。
耐震性に優れた設計理念の共有
建物全体のバランス設計や、各部材の配置方法に対する建築士の考え方をしっかりと理解し、納得できる設計を進めましょう。
重要部材の配置に関する確認
耐力壁や耐震補強材の位置、梁や柱の強度に関する設計意図を確認します。設計士と協力して、各部材がどう作用し合うかを理解することが大切です。
メンテナンス性と長期的な耐震性
初期の設計段階で、将来的なメンテナンスや修繕のしやすさも視野に入れた設計を依頼しましょう。長期的な視点での耐震性能も重要です。
コストと耐震性のバランス
耐震等級3の住宅を建てる際、コスト面のバランスも重要な要素です。高い耐震性を確保しつつ、予算内で施工可能な範囲を探る必要があります。
耐震等級3の取得に必要な追加コストの見積もり
高耐震設計は当然コストがかかりますが、その分のコストをどのように配分するかが重要です。コスト面で調整が可能な部分を建築士と共に検討します。
コスト対効果の高い材料選定
コスト削減のために、強度が十分でありながら、コスト効率の良い材料を選定する方法を相談しましょう。無理なく耐震性を確保できる方法を提案してもらいましょう。
無理のない構造補強の提案
予算に余裕がない場合でも、必要最低限の構造補強が可能な方法を検討し、コストを抑えつつ十分な耐震性を持たせる方法を見つけます。
建築士としっかりとコミュニケーションを取ることで、費用対効果の高い、かつ十分に耐震性を確保できる住宅を建てることが可能となります。
設計とコストをバランスよく調整し、最適なプランを提案してもらいましょう。
地震に強い家づくりの決定版:耐震等級3を実現するための最適設計ガイド

耐震等級3を取得した住宅は、地震に強い家を実現するために非常に重要な基準となります。耐震設計は単に強固な構造を作ることにとどまらず、適切な素材選び、バランス設計、細部にわたる計算・確認が必要です。
耐震性を高めるためには、建物全体の構造や基礎、屋根などの設計を総合的に見直し、地震の揺れにどう対応するかを考えることが大切です。
建築士とのしっかりした打ち合わせや、コストと耐震性のバランスを考えた設計が不可欠です。
素材選びと構造設計の重要性
木造、鉄骨造、RC造の各構造における耐震性の特徴を理解し、適切な素材を選定することが大切です。
基礎の設計と補強
べた基礎や地中梁を効果的に活用することで、地震時の揺れに強い基盤を作ることができます。
耐震計算の精度の重要性
許容応力度計算によって、より精密で安全な設計を実現し、耐震等級3の基準を満たすことができます。
建築士との連携
耐震性を最大限に引き出すためには、設計段階から建築士との密なコミュニケーションが不可欠です。
耐震等級3の家を建てるためには、これらのポイントをしっかりと押さえ、専門的な知識と経験を持つ建築士と共に進めることが成功のカギとなります。地震に強い家を建てるためには、まずはしっかりと計画を立て、実行に移すことが重要です。
憧れの大手メーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれる

住宅展示場や完成見学会にいくのは時間もかかるし大変…
そんなときに便利なのが「タウンライフ家づくり」です。
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
気になるメーカーや工務店を選び、希望の間取りや予算を入力するだけ。「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる!
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。

「タウンライフ家づくり」はこんな方におすすめ
- あなただけの間取りと見積もりを無料で手に入れ比較したい
- 営業されるのが嫌、苦手
- 自宅でじっくり信頼できるハウスメーカーを選びたい
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ




