この記事にはプロモーション・広告が含まれています
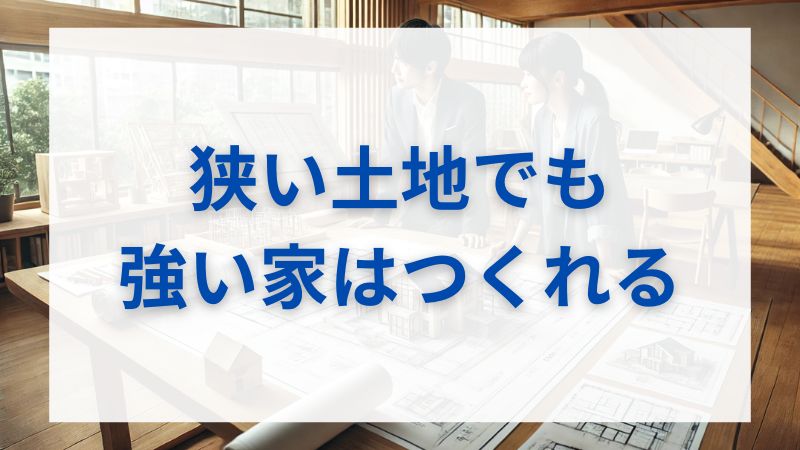
「うちの土地は狭いし形もいびつ。だから耐震等級3の家なんて無理だろう」。そう思い込んでいませんか?
実は、狭小地や変形地でも「耐震等級3」の家を建てることは十分に可能です。限られたスペースでも、設計と構造の工夫を重ねれば、強くて安心できる住まいを実現できます。
近年、都市部を中心に変形地や狭小地への住宅建築が増えています。こうした土地は価格的な魅力もあり、選択肢として検討する人が多くなっていますが、一方で「安全性に不安がある」との声も少なくありません。
しかし、実際には建築のプロがきちんと関わり、耐震等級3の基準に沿った設計と構造計算を行えば、どんな敷地でも「家族の命を守る住まい」は叶えられます。
この記事では、制約の多い土地でも実現可能な「耐震等級3」の家づくりについて、現実的な工夫と成功事例を交えてわかりやすく解説します。あなたの土地でも、安心できる住まいはつくれます。最初の一歩を一緒に踏み出しましょう。
54万人(2025年9月時点)以上が利用!信頼できるメーカーが見つかる
\ 複数社の比較で300万円以上の差 /
家を建てるなら相見積もりで
複数社比較をやらなきゃ損!
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。
- 簡単な質問に回答(約3分)
- 希望のハウスメーカーを選択(複数可)
- 無料で「間取り」「見積もり」「土地探し」が届く!
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ
「特殊な土地=不安定」とは限らない?狭小・変形地の“現実”と向き合う

「狭い土地」「変な形の土地」と聞くと、家づくりに不利だと感じる方も多いでしょう。実際、都市部では隣地との距離がほとんどないケースや、道路から奥まった旗竿地、鋭角な三角地など、個性的な土地が珍しくありません。
しかし、それらの条件があるからといって、安全な家が建てられないというわけではありません。狭小地や変形地でも、適切な設計と構造対応を行えば、耐震等級3の家は十分に実現可能です。
重要なのは、土地の“形”や“広さ”だけに目を奪われず、そこにどう建てるかという“設計の視点”です。プロの建築士が加われば、土地の制約を逆に活かす間取りや構造の工夫が見えてきます。
狭小地・変形地ならではの不安や課題、その正体を見極めよう
狭小地や変形地では、建物配置の自由度が限られる分、耐震設計上の工夫がより重要になります。以下に代表的な不安や課題を整理してみましょう。
建物のバランスが取りづらい
狭さや形状の制約で、耐力壁の配置が偏りやすく、バランスの良い構造計画が難しい傾向にあります。
開口部が集中しやすい
採光・通風を確保するために窓が集中しやすく、耐震性の面では壁量不足やバランス崩れの要因になります。
基礎形状に制約が出やすい
複雑な地形では基礎設計にも制限がかかり、施工上の工夫が求められるケースが多くなります。
地盤の状態が読みにくい
周辺建物の影響や盛土・切土の履歴などから、地盤のばらつきが大きい場合があります。
これらは決して致命的な欠点ではなく、早い段階で正確に把握し、設計で適切に対応することで十分克服できる課題です。問題を「避ける」のではなく、「どう向き合うか」が耐震等級3への鍵となります。
関連記事:【地震に備える家づくり】耐震等級3の設計基準と施主が知っておくべき注意点
「耐震等級3」とは?数字以上の価値を知ることで家づくりが変わる
耐震等級3とは、国の住宅性能表示制度における耐震性能の最高ランクです。建築基準法の1.5倍の耐震力を持ち、消防署や警察署など防災拠点と同等の強度が求められます。
耐震等級1が「倒壊を免れる最低限の性能」だとすれば、等級3は「災害後もそのまま住み続けられるレベルの安全性」を意味します。実際、熊本地震でも耐震等級3の住宅は倒壊や大破の被害が極めて少なかったことが調査で確認されています。
つまり、耐震等級3を選ぶということは、単に「家が壊れにくい」だけでなく、家族の命と生活の継続を守るための確かな選択なのです。
狭小地や変形地であっても、その価値は変わりません。むしろ、土地条件が厳しいからこそ、より高い安全性を確保する意義は大きくなると言えるでしょう。
関連記事:【要確認】モデルハウスで“本物の耐震等級3”を見抜く5つの視点とは?
限られた土地でも“強い家”はつくれる―設計の工夫と新しい視点

狭小地や変形地では、限られたスペースに家族の暮らしと安全性を両立させる必要があります。その中で「耐震等級3」を実現するには、設計段階から耐震性を意識した工夫が欠かせません。
耐震設計の基本は、「構造バランス」と「剛性の確保」です。狭小・変形地では、この2点が難しくなりがちですが、工夫次第でしっかりとクリアできます。ここでは、限られた敷地条件でも高い耐震性能を実現するための具体的な設計手法を紹介します。
小さな敷地に潜む「耐震」のチャンス―耐力壁とバランス設計の可能性
耐震等級3を目指す上で最も基本的かつ重要なのが「耐力壁の配置バランス」です。これは建物全体の揺れを均等に受け止めるための構造計画であり、狭小地では左右前後の壁量や配置に偏りが出やすくなります。
壁の位置と量のバランスを整える
特定の方向だけに壁が集中しないように、全体を見てバランスよく配置することが求められます。
コーナー部分の補強
L字型や凹凸のある変形地では、角の部分が弱点になりやすいため、構造補強や壁の配置が重要になります。
筋交いや構造用合板の活用
壁を構造的に強化するために、筋交い(すじかい)や構造用合板などを組み合わせて設計します。
耐力壁の最適な配置は、家の“形”に合わせて計算することが重要です。プロによる構造計算を伴うことで、耐震等級3の取得が現実のものになります。
関連記事:後悔しない!耐震等級3の家づくりに欠かせない施工業者の選び方とチェックポイント
開口部が多いと本当に危ない?“窓の工夫”で変わる耐震性
狭小地では隣家との距離が近く、採光・通風を確保するために大きな窓や開口部が必要になるケースがあります。しかし、窓の多い家は壁量が不足し、耐震性が低下するリスクも。
そこで注目すべきは「開口部と耐力壁のバランス」です。以下の工夫により、開口部の自由度を保ちながら耐震性を確保できます。
窓と窓の間に壁(柱)を確保する
開口部の連続を避け、最低限の壁を残すことで構造バランスを保ちます。
耐力壁となるサッシを採用する
構造計算上で有利な耐力壁サッシを使用することで、開口部を確保しながら壁としての機能も持たせられます。
窓のサイズ・配置にメリハリをつける
全面ガラスではなく、視線の必要な部分だけ開けるなど、機能性と安全性のバランスを図ります。
窓が多い=弱い家とは限りません。適切な設計と選定で、明るく強い家が両立できます。この点も、設計士との密な相談が成否を分けるポイントです。
柱や梁、ほんの少しの配置見直しで変わる家の強さ
狭小地や変形地の家づくりでは、柱や梁の配置が設計の要となります。限られたスペースの中で耐震性能を最大限に高めるには、構造の“骨組み”をどれだけ合理的に配置できるかがカギです。
重要なのが、耐力壁だけでなく、柱と梁の連携によって建物全体の剛性を保つことです。これは単なる「間取りの調整」ではなく、家の安全性を支える戦略的な工夫といえます。
通し柱の活用で構造強度を確保
2階建て以上の建物では、1階から2階までを貫く通し柱を配置することで、縦方向の強度が高まります。
梁のスパンと接合部を最適化
梁が長すぎるとたわみやすくなるため、スパン(梁の長さ)を短く区切り、強固な接合部を確保することが大切です。
柱位置と間取りのバランスを調整
耐震性を優先しつつ、使い勝手を犠牲にしない柱配置を目指します。収納や間仕切りを利用すれば、動線を妨げずに構造強化が可能です。
柱や梁の配置を数十センチ調整するだけで、耐震性能が大きく変わることもあります。このような細かな検討が積み重なることで、狭小地でも強くしなやかな家が実現します。
基礎と床が「家の要」―狭小地で頼れる土台のつくり方
どんなに優れた設計でも、基礎と床がしっかりしていなければ耐震性能は成立しません。狭小地では、支持地盤の深さや施工スペースの制約を考慮した基礎計画が必要です。
ベタ基礎で面全体に力を分散
狭小住宅では、布基礎よりもベタ基礎が採用されるケースが多く、地震の力を面で受け止めて建物全体を安定させます。
狭小地でも施工しやすい基礎形状を選定
地盤の状況に応じて、深基礎や地中梁などを併用し、複雑な形状にも対応できる設計を行います。
剛床構造で水平力に対応
床全体を一体化させる剛床構造(ごうしょうこうぞう)を採用することで、地震の横揺れに強い建物になります。
家の耐震性は、目に見えない基礎と床から始まります。これらの部分にこそ、丁寧な設計と施工が求められます。敷地に制約があるほど、その精度が家全体の強さを左右するといえるでしょう。
関連記事:耐震等級3を活かすには?地盤調査と基礎工事で家の強さは決まる
複数社の比較で300万円以上の差
家を建てるなら相見積もりで
複数社比較をやらなきゃ損!
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。
- 簡単な質問に回答(約3分)
- 希望のハウスメーカーを選択(複数可)
- 無料で「間取り」「見積もり」「土地探し」が届く!
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ
狭くても暮らしやすく、安全に―間取りとデザインの“逆転発想”

限られた土地条件の中でも、快適性と耐震性を両立するには、発想の転換と空間の使い方に工夫が求められます。ここでは、狭小地や変形地での間取りとデザインのアイデアをご紹介します。
関連記事:【徹底比較】耐震等級3の家づくりで後悔しない依頼先の選び方|ハウスメーカー・工務店・設計事務所の違い
暮らしやすさと安全性を同時に満たす家づくりは難しく見えて、実は設計次第で大きく変わります。逆転の発想で空間を活かすことが、制約のある土地でも希望を形にする鍵となります。
吹き抜け・大開口も諦めなくていい?空間づくりと耐震のバランス
吹き抜けや大きな窓は開放感を演出する反面、耐力壁を設置できる面積が減るため、耐震性とのバランスをどう取るかが重要になります。しかし、以下のような工夫によって、デザイン性と構造安全性は両立できます。
吹き抜けの位置を中央に配置する
家の中心に吹き抜けを設けることで、構造バランスを崩さずに空間の広がりを演出できます。
部分的な大開口と構造壁の組み合わせ
開口部を一面に集中させず、構造壁との交互配置によって耐震性を確保します。
鉄骨や集成材など高耐力材を活用
木造でも構造材の工夫により、開放感を保ちながら耐震性能を補う設計が可能です。
デザインと耐震性は相反するものではなく、両立できる要素です。設計者と目的を共有することで、安全性を損なわずに理想の空間が叶えられます。
スキップフロアや縦の空間で感じる“広がり”と安心感
限られた面積を有効活用する手法として、スキップフロアやロフトなどの縦空間を活かす設計が注目されています。実際の床面積以上の“体感的な広さ”を演出できます。
スキップフロアで段差に機能を持たせる
階高をずらすことで空間を分け、収納や書斎など多目的な用途を持たせられます。
ロフト空間の活用で収納と居住性を両立
天井高を確保しつつ、非日常的な空間として子ども部屋や趣味部屋にも応用できます。
構造的な一体感を意識した縦使い
縦方向の空間構成も構造設計の一部として捉え、耐震性との整合性を取りながら設計します。
“狭い”という固定観念を超える立体的な空間利用は、設計の力で可能になります。縦の広がりを意識することで、閉塞感のない、居心地の良い住まいが実現します。
「モノが多い家こそ」動線&収納の工夫で暮らしが整う
狭小地ではどうしても収納スペースが限られがちです。その結果、モノが溢れやすく、動線が乱れてしまうという悩みを抱える家庭も多いでしょう。ですが、動線と収納を計画的に整えることで、暮らしやすさと安全性の両立が可能になります。
耐震性を考えるうえでは、「モノの配置」も見逃せないポイントです。家具が倒れたり、避難経路をふさいだりしないような設計が求められます。
動線のシンプル化で災害時の安全を確保
曲がりくねった動線は災害時に避難しにくいため、できるだけ直線的な移動ができる間取りを目指します。
階段下・壁厚の利用で収納力アップ
通常はデッドスペースになりがちな場所を収納として活用することで、生活空間を圧迫せずに収納を確保できます。
壁面収納や天井吊り収納で空間活用
床面を占有せず、視界を広く保てる収納は、狭さを感じさせない工夫として有効です。
倒れにくい家具配置と固定の工夫
地震時の家具転倒を防ぐため、背の高い家具は壁に固定したり、低い位置に置いたりと、安全性を意識した配置が必要です。
片付いた動線と安全な収納設計は、災害時にも命を守る役割を果たします。設計の初期段階から収納と動線を一体的に考えることで、狭くても快適で安心な住まいが手に入ります。限られた面積を「どう使うか」が、家全体の価値を大きく左右します。
見逃しがちな地盤対策。「家を守る」ための最初の一歩とは

建物の構造や設計がどれだけ優れていても、それを支える地盤が弱ければ、家の耐震性は根本から崩れてしまいます。とくに狭小地や変形地は、埋め立て地や盛土が含まれる場合もあり、地盤の状態にばらつきが出やすいため、より慎重な対応が求められます。
耐震等級3を取得するには、構造計算だけでなく、その前提となる「地盤の安定性」も確認される必要があります。つまり、安全な家づくりは、土地を知ることから始まるのです。
“調べて終わり”ではない。地盤調査がもたらす安心
地盤調査は、建物の重さに地面が耐えられるか、液状化のリスクがあるかなどを確認するために行います。多くの住宅ではスウェーデン式サウンディング試験(SWS試験)が主流で、比較的簡易に実施できます。
地盤の強度を「数値」で把握できる
目視では分からない地盤の硬さや層構成をデータとして把握でき、補強が必要かどうかの判断に役立ちます。
設計や基礎工法の最適化につながる
地盤に合わせて基礎を選定できるため、無駄なコストを抑えながら必要な強度を確保できます。
不動沈下や傾きのリスクを未然に防げる
将来の不同沈下を防ぐためにも、事前の調査は極めて重要なステップとなります。
地盤調査は義務ではないケースもありますが、耐震等級3を目指すなら事実上“必須の工程”です。設計の精度や安心感にも直結するため、早い段階で調査を依頼しましょう。
地盤補強、その必要性と実感できる効果を知っておこう
地盤調査の結果、支持力が不足していたり、液状化のリスクがあると診断された場合は、地盤補強工事が必要になります。これは「建物を支える力を地面に持たせる」ための作業であり、耐震性能を確保するためには欠かせないステップです。
補強方法は地盤の状態により異なりますが、大きく分けて「表層改良」「柱状改良」「鋼管杭工法」などがあり、それぞれ施工方法と費用、効果の持続年数が異なります。
表層改良
軟弱な地盤の表面を掘削し、セメント系固化材を混ぜて締固める方法。比較的浅い地盤に有効です。
柱状改良
セメントミルクを注入し、地中に柱状の支持体をつくる方法。中程度の深さの地盤に適しています。
鋼管杭工法
鋼管を地中に打ち込んで強固な地盤まで達する工法。支持地盤が深い場合や、支持力を確実に確保したい場合に用います。
これらの工事は、「建物の倒壊を防ぐ」だけでなく、「建物の傾きや不同沈下を防ぐ」という効果もあり、長期的に見て家の資産価値を守ることにもつながります。
耐震等級3を取得するうえでも、設計の前提となる地盤条件を整えることは非常に重要です。狭小地や変形地ほど、地盤の状態が複雑になりやすいため、補強の必要性が高まる傾向にあります。
「目に見えない部分こそ、家の命を支えている」。その意識を持つことが、強い家づくりの第一歩です。
複数社の比較で300万円以上の差
家を建てるなら相見積もりで
複数社比較をやらなきゃ損!
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。
- 簡単な質問に回答(約3分)
- 希望のハウスメーカーを選択(複数可)
- 無料で「間取り」「見積もり」「土地探し」が届く!
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ
耐震等級3取得は“計算ありき”―構造計算がもたらす確かな安心

耐震等級3は、単に「頑丈な家」というイメージだけでは成り立ちません。明確な数値と根拠に基づく構造計算によって、はじめて公的に認められる性能等級です。狭小地や変形地のような、設計に工夫が求められる条件下では、構造計算による裏付けが不可欠となります。
設計者の経験や勘に頼るだけではなく、数値で裏付けられた「確かな強さ」を証明することが、家族の安心を支える根拠になります。構造計算は、目に見えない部分の信頼性を、具体的に「見える化」するプロセスです。
許容応力度計算、「難しそう」の先にある納得感
耐震等級3を取得するには、「許容応力度計算」という精密な構造計算が必要です。これは、建物にかかる荷重と、それに耐える部材の強さを比較し、安全な設計になっているかを確認する仕組みです。
- 荷重=地震や風などの外力、建物自体の重さ
- 応力度=構造部材にかかる力の強さ
- 許容応力度=部材が耐えられる限界の強さ
この計算を通じて、「どこに、どんな強さの柱や梁が必要か」「どこまでの揺れに耐えられるか」といった根拠を得ることができます。
許容応力度計算は確かに複雑ですが、それゆえに得られる安心感は大きく、構造の信頼性を保証する最も客観的な方法と言えます。費用や手間を惜しまず、最初の設計段階で導入することが、家づくり全体の質を底上げします。
関連記事:【保存版】耐震等級3を確実に取る!設計審査の書類・手続き完全マニュアル
構造計算の流れと、知っておくべきポイントをチェック
構造計算は、単に「建築確認に必要な書類」という位置づけにとどまりません。安全性を数値で証明し、設計の信頼性を確保するための設計プロセスです。とくに耐震等級3を目指す際には、その精度と妥当性が直接、家の耐震性能に直結します。
構造計算の一般的な流れは以下のとおりです。
建物形状・間取り・荷重条件の設定
屋根材・外壁材・内装などの重さを考慮し、正確な荷重を算出します。
各構造部材(柱・梁・壁など)にかかる応力の計算
地震時や風圧時などの力を想定し、各部材にかかる力を数値化します。
応力度の判定と安全率の確認
各部材が「想定される力」に耐えられるかどうかを、設計基準に照らして評価します。
計算結果に基づく構造設計図の作成
必要な耐力壁の位置、梁や柱の寸法、基礎形状などが反映された設計が完成します。
このプロセスのなかで、設計者と構造設計者が密に連携することが不可欠です。狭小地や変形地では、敷地条件に合わせた調整も必要になるため、一般的な四角い土地に比べて設計自由度が下がる分、「構造と間取りのバランス」を見極める経験値が求められます。
施主としては、「構造計算をどの段階で実施するのか」「どの程度までの耐震性能を目指すのか」を、初期の打ち合わせ段階で明確にしておくことが重要です。
耐震等級3を希望する場合は、あらかじめその意思を設計者に伝え、「許容応力度計算による設計が可能かどうか」も確認しておきましょう。
「特殊な土地でここまでできる」―実例で広がる希望と可能性

「狭い土地ではムリ」「変形地では安全性が不安」といった声は、家づくりを前にした多くの方が抱く共通の懸念です。しかし、実際には設計の工夫や適切な構造計算によって、こうした土地でも耐震等級3の取得は十分に可能です。ここでは、特殊な敷地条件を活かした成功事例を紹介します。
まず注目したいのが、都市部に多いL字型や三角地の活用事例です。限られた敷地を最大限に活かすため、建物形状にあわせた耐力壁の配置や柱・梁の最適化が行われています。壁面のバランスや開口部の調整など、地震時のねじれを抑える設計がカギとなります。
実際の事例では、変形地に対して以下のような設計工夫が行われています。
不規則な外形に対して、内部は直線的な間取りに整える
外壁は土地の形状に合わせながらも、室内空間は使いやすさを重視して整形化する設計が主流です。
耐力壁と開口部をセットで設計する
大きな窓を配置したい場合は、隣接する壁にしっかりとした耐力壁を設けてバランスを取ります。
吹き抜けを活かして光と風を取り入れる
狭小・変形地では外壁に窓が取りにくいため、上部からの採光や通風が重要です。
こうした工夫によって、形の不利を性能の優位に変えることができます。土地の個性に合わせた設計は、ただの妥協ではなく、むしろ魅力ある住まいを生み出すきっかけにもなり得ます。次のセクションでは、具体的な土地形状別の事例を紹介します。
実例で見る「耐震等級3」の家づくり:安心と満足を実現した家族の選択

耐震等級3の家づくりを選んだ施主たちの実例を通じて、その魅力と効果を具体的にご紹介します。
Aさん家族の選択:早川木材株式会社で建てた自然素材の家
岡山県福山市に住むAさん家族は、自然素材を活かした家づくりを得意とする早川木材株式会社に依頼しました。
耐震等級3を取得したこの住まいは、地震への強さだけでなく、木の温もりを感じられる空間設計が特徴です。
Aさんは「家族の安全を第一に考え、耐震性の高い家を選びました。自然素材の心地よさもあり、安心して暮らせています」と語っています。
Bさん家族の選択:Nacca Designで叶えたデザインと性能の両立
福山市のBさん家族は、デザイン性と性能を兼ね備えた家を求め、Nacca Design(有限会社 N’s)に依頼しました。
耐震等級3を取得したこの住まいは、パッシブ設計を取り入れ、省エネ性能にも優れています。
Bさんは「デザインも性能も妥協したくなかった。耐震等級3の安心感と、美しいデザインに満足しています」と話しています。
Cさん家族の選択:株式会社せらちゅう建設で実現した理想の暮らし
福山市のCさん家族は、地域密着型の株式会社せらちゅう建設に依頼し、耐震等級3の家を建てました。
構造計算をしっかり行い、地震に強い家を実現。Cさんは「地元の工務店で信頼できるところにお願いできて良かった。安心して暮らせる家ができました」と述べています。
関連記事:耐震等級3で家族を守る!地震に強い家を作るための完全ガイド
実例から学ぶ:耐震等級3の家づくりのポイント
これらの実例から、耐震等級3の家づくりにおいて重要なポイントが見えてきます。
信頼できる施工会社の選定
耐震等級3の取得には、確かな技術と経験が必要です。実績のある施工会社を選ぶことが重要です。
デザインと性能の両立
耐震性だけでなく、デザイン性や快適性も重視することで、満足度の高い住まいが実現します。
地域に合った設計
地域の気候や風土に合わせた設計を行うことで、より快適で安心な暮らしが可能になります。
これらのポイントを踏まえ、自分たちの理想の住まいを実現するためには、信頼できる施工会社との出会いが不可欠です。
無料の一括見積もりサービスを活用することで、複数の施工会社の提案を比較検討し、自分たちに最適なパートナーを見つけることができます。
家族の安全と快適な暮らしを実現するために、耐震等級3の家づくりを検討してみてはいかがでしょうか。
L字型・三角地・旗竿地…不利と言われた土地の逆転劇

一見すると建築に不向きとされるL字型や三角地、旗竿地などの変形地。しかし、これらの土地でも耐震等級3の住宅を実現した事例が増えています。限られた敷地条件を逆手に取り、創意工夫で安全性と快適性を両立させた成功例を紹介します。
L字型の敷地でも耐震等級3を実現:株式会社小林建設の事例
埼玉県の株式会社小林建設は、L字型の変形地においても耐震等級3を取得した住宅を手がけています。この事例では、「囲の字型プラン」を採用し、敷地の形状を活かした設計が特徴です。許容応力度設計を用い、柱・梁・土台には高強度の材料を使用することで、耐震性能を確保しています。このような設計手法により、変形地でも高い耐震性を持つ住宅が実現可能であることが示されています。
三角地でも快適な住まい:フリーダムアーキテクツデザインの事例
フリーダムアーキテクツデザインは、三角形の敷地においても耐震等級3の住宅を設計しています。この事例では、敷地の形状に合わせて建物を配置し、無駄なスペースをなくすことで、効率的な間取りを実現。耐震性能を高めるために、構造用合板や耐力壁を適切に配置し、建物全体の剛性を確保しています。変形地でも快適で安全な住まいが可能となっています。
旗竿地での挑戦:ノークホームズの取り組み
福井県のノークホームズは、旗竿地と呼ばれる細長い敷地においても、耐震等級3の住宅を建築しています。この事例では、建物の配置を工夫し、敷地の奥行きを活かした設計が特徴です。耐震性能を確保するために、ベタ基礎や高強度の構造材を使用し、建物全体の安定性を高めています。限られた敷地条件でも安全で快適な住まいが実現されています。
これらの事例からもわかるように、変形地でも適切な設計と施工により、耐震等級3の住宅を実現することが可能です。土地の形状に合わせた柔軟な設計と、高い技術力を持つ建築会社の選定が重要となります。
変形地での家づくりを検討されている方は、これらの事例を参考に、信頼できる建築会社とともに、安全で快適な住まいを目指してみてはいかがでしょうか。
複数社の比較で300万円以上の差
家を建てるなら相見積もりで
複数社比較をやらなきゃ損!
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。
- 簡単な質問に回答(約3分)
- 希望のハウスメーカーを選択(複数可)
- 無料で「間取り」「見積もり」「土地探し」が届く!
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ
狭小地の3階建て住宅。高さを活かして叶える耐震性

都市部では土地の取得が難しく、限られた敷地での住宅建築が求められます。狭小地においても、高さを活かした3階建て住宅で耐震等級3を実現することが可能です。以下に、実際の事例を紹介しながら、その工夫とポイントを解説します。
狭小地での耐震等級3実現の工夫
実際の事例を紹介しながら、その工夫とポイントを解説します。
1. 清菱建設の事例:17.7坪の敷地に建つ3階建て住宅
東京都足立区の清菱建設が手掛けた事例では、17.7坪の狭小地に耐震等級3の3階建て住宅を建築しました。構造計画をプランニング段階から考慮し、許容応力度計算に基づいた設計を行っています。高気密・高断熱性能も兼ね備え、快適な住環境を実現しています。
2. 荒川区の事例:間口5mの細長い敷地に建つ住宅
東京都荒川区では、間口5m・奥行き15mの細長い敷地に耐震等級3の3階建て住宅が建築されました。ベースセッターを活用した耐力壁の配置により、車庫スペースと玄関アプローチを確保しつつ、耐震性を確保しています。
3. 岐阜市の事例:30坪の敷地に延床面積42坪の住宅
岐阜市鷺山の閑静な住宅街に建てられたT様邸では、30坪の敷地に延床面積42坪の3階建て住宅を実現しました。SE構法を採用し、耐震等級3を取得しています。駐車スペースも3台分確保し、狭小地でも快適な暮らしを提供しています。
狭小地での耐震等級3住宅建築のポイント
- 構造計算の重要性:狭小地では建物のバランスが重要です。許容応力度計算やSE構法など、構造計算に基づいた設計が求められます。
- 耐力壁の配置:限られたスペースでも耐震性を確保するために、耐力壁の配置や種類(例:ベースセッター)の選定が重要です。
- 高気密・高断熱性能:狭小地では隣接建物との距離が近いため、断熱性能や気密性能を高めることで快適な室内環境を維持できます。
- 空間の有効活用:3階建てにすることで、限られた敷地でも十分な居住スペースを確保できます。収納や動線の工夫も重要です。
狭小地での住宅建築は制約が多いものの、適切な設計と工法の選択により、耐震等級3の安全で快適な住まいを実現できます。家族の安心と快適な暮らしを守るために、信頼できる建築会社と共に計画を進めましょう。
狭小地における3階建て住宅の建築は、限られた敷地を最大限に活用する手段として注目されています。しかし、縦に伸びる構造は耐震性の確保が課題となります。ここでは、実際の事例を通じて、狭小地での3階建て住宅における耐震性の工夫を紹介します。
清菱建設:17.7坪の敷地に建つ耐震等級3の3階建て住宅
東京都内の17.7坪という限られた敷地に、清菱建設が建築した3階建て住宅は、耐震等級3(許容応力度計算)を取得しています。施主のYさんは、狭小地での耐震性に不安を抱えていましたが、同社の構造計画と高性能な断熱材の施工により、安心して暮らせる住まいを実現しました。日射取得と遮蔽を考慮した設計により、快適な居住空間が確保されています。
BXカネシン:間口5mの細長い敷地に建つ耐震等級3の3階建て住宅
東京都荒川区の間口5m・奥行き15mの細長い敷地に、BXカネシンが建築した3階建て住宅は、耐震等級3を取得しています。「ベースセッター」という金物を使用し、車庫の片側に5壁集めて配置することで、駐車スペースと玄関へのアプローチを確保しつつ、耐震性を高めています。
ユニバーサルホーム:23区内の狭小地に建つ耐震等級3の3階建て住宅
ユニバーサルホームが建築した、東京都23区内の狭小地に建つ3階建て住宅は、耐震等級3を取得しています。線路近くという立地条件にも関わらず、耐震性と防音性を兼ね備えた設計が施されています。階段下や小屋裏収納など、空間を有効活用する工夫が随所に見られます。
これらの事例から、狭小地においても設計と構造の工夫により、耐震等級3の3階建て住宅を実現することが可能であることがわかります。限られた敷地を有効活用しつつ、安全で快適な住まいを目指す際の参考にしてみてください。
設計士・建築会社選びは“経験と提案力”がカギ。後悔しないためにできること

狭小地や変形地での家づくりは、一般的な住宅設計とは異なる高度な専門性が求められます。限られた敷地条件の中で、快適性と耐震性を両立させるためには、豊富な実績と柔軟な提案力を持つ設計士や建築会社の選定が極めて重要です。
「施工実績あります」の言葉を、どう見極める?
「狭小地の施工実績があります」といった言葉を鵜呑みにするのではなく、具体的な内容を確認することが大切です。以下のポイントを参考に、実績の真偽を見極めましょう。
施工事例の詳細確認
実際の施工事例を見せてもらい、敷地面積や建物の間取り、工法などを確認します。写真や図面があれば、より具体的にイメージできます。
施主の声や評価の確認
実際にその建築会社で家を建てた施主の声や評価を確認します。口コミサイトやSNS、OB訪問などを活用すると良いでしょう。
現地見学の依頼
可能であれば、実際に施工された住宅を見学させてもらいましょう。現地での確認は、設計や施工の質を直接感じ取ることができます。
構造計算や耐震設計、“丸投げしない”姿勢で選ぶ理由
狭小地や変形地では、構造計算や耐震設計が重要です。以下の点を確認し、信頼できる設計士や建築会社を選びましょう。
構造計算の実施有無
構造計算を実施しているかどうかを確認します。耐震等級3を取得するためには、構造計算が必須です。
耐震設計の実績
耐震設計の実績が豊富かどうかを確認します。過去の施工事例や取得した耐震等級などを参考にしましょう。
設計者とのコミュニケーション
設計者と直接コミュニケーションを取り、設計意図や構造計算の内容について説明を受けることが大切です。疑問点や不安な点は遠慮せずに質問しましょう。
素直な相談ができる設計士は見つかる?信頼のポイント
信頼できる設計士や建築会社を見つけるためには、以下のポイントを意識しましょう。
コミュニケーションのしやすさ
自分の要望や不安を素直に話せる雰囲気があるかどうかを確認します。初回の打ち合わせ時に、話しやすさや対応の丁寧さを感じ取ることができます。
提案力と柔軟性
要望に対して柔軟に対応し、具体的な提案をしてくれるかどうかを確認します。狭小地や変形地では、柔軟な発想と提案力が求められます。
アフターサポートの充実
施工後のアフターサポートが充実しているかどうかを確認します。長期的な視点でのサポート体制が整っているかをチェックしましょう。
狭くても、形がいびつでも。「強い家」はつくれる

狭小地や変形地といった制約のある土地でも、適切な設計と施工によって、快適で安全な住まいを実現することが可能です。重要なのは、信頼できるパートナーを見つけ、自分の要望や不安をしっかりと伝えることです。
家づくりは一生に一度の大きなプロジェクトです。だからこそ、慎重に、そして前向きに進めていきましょう。あなたの理想の住まいは、きっと実現できます。
制約のある土地条件でも、耐震性をあきらめる必要はありません。狭小地や変形地であっても「耐震等級3」を実現するための方法は、設計力と情報収集によって確実に見つかります。
もし今「自分の土地でも可能なのか?」「費用や工期はどうなるのか?」と迷っているなら、まずは複数の専門家に相談してみましょう。無料で始められる一括見積もりサービスを利用すれば、複数社の提案や価格帯を比較でき、納得のいく一歩を踏み出せます。
憧れの大手メーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれる

住宅展示場や完成見学会にいくのは時間もかかるし大変…
そんなときに便利なのが「タウンライフ家づくり」です。
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
気になるメーカーや工務店を選び、希望の間取りや予算を入力するだけ。「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる!
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。

「タウンライフ家づくり」はこんな方におすすめ
- あなただけの間取りと見積もりを無料で手に入れ比較したい
- 営業されるのが嫌、苦手
- 自宅でじっくり信頼できるハウスメーカーを選びたい
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ


