この記事にはプロモーション・広告が含まれています
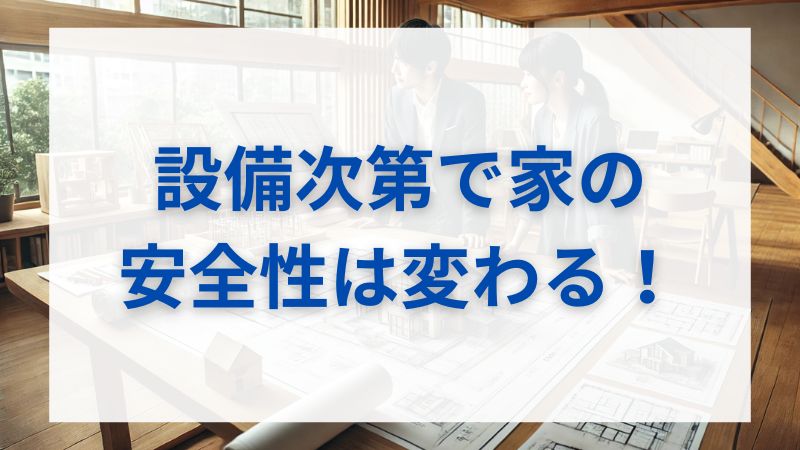
「耐震等級3」とは、住宅性能表示制度における最高ランクの耐震性能を指します。消防署や警察署など災害時の拠点施設と同等の強さを備えた構造であり、建物の倒壊を防ぐための強固な基準です。地震の多い日本において、この等級を選ぶことは、家族を守るうえで非常に賢明な判断だといえます。
しかし、安心は構造の強さだけでは成り立ちません。実際の被災現場では、建物自体は無事でも、内部設備の転倒や破損によって生活機能が失われ、在宅避難が困難になるケースが多数報告されています。つまり、耐震等級3の住宅であっても、設備の選び方や設置方法によっては被害を受けるリスクが残されているのです。
本記事では、耐震等級3の住宅にふさわしい設備選びのポイントと、安全性を高める設置の工夫について解説します。見落とされがちな「設備」という視点から地震対策を見直し、構造+設備の両面から真に地震に強い家づくりを目指すヒントをお届けします。
関連記事:【地震に備える家づくり】耐震等級3の設計基準と施主が知っておくべき注意点
54万人(2025年9月時点)以上が利用!信頼できるメーカーが見つかる
\ 複数社の比較で300万円以上の差 /
家を建てるなら相見積もりで
複数社比較をやらなきゃ損!
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。
- 簡単な質問に回答(約3分)
- 希望のハウスメーカーを選択(複数可)
- 無料で「間取り」「見積もり」「土地探し」が届く!
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ
耐震等級3の誤解と設備の重要性

耐震等級3という言葉には、「最高等級だから万全」というイメージがつきまといます。しかし、この等級が保証するのはあくまで構造躯体が倒壊しないレベルの耐震性能であり、内部の家具や設備、生活機能まではカバーしていません。
実際には、耐震等級3の住宅でも、内部設備の固定が不十分だったり、設置位置が不適切だったりすれば、地震時に大きな被害を受ける可能性があります。とくにキッチンや洗面所、リビングといった生活空間にある設備が転倒・破損すると、家族の安全を脅かすだけでなく、日常生活を継続することも難しくなります。
耐震等級3の限界と設備の役割
耐震等級3の家が倒壊しないからといって、設備や家具の転倒・破損が起きないわけではありません。むしろ、揺れが収まった後の生活に直結する設備こそが、住まいの安全性に大きな影響を及ぼします。
以下のような設備の損傷が、実際の地震後に多く見られます。
- 冷蔵庫や食器棚の転倒による出入口の塞がり
- 温水器や洗濯機の破損による水漏れ
- 屋外設置のガス機器や蓄電池の脱落・故障
- 配管のズレによる漏水や火災のリスク
これらの事例からも分かるように、構造の強さだけでなく、設備の選定・設置まで含めた包括的な耐震対策が必要不可欠です。
地震時に危険となる設備とその対策

建物の構造が無事でも、地震によって住宅内の設備が転倒・破損すれば、二次被害や生活の混乱を招きます。背の高い家具や大型家電、固定されていない水回り機器などは注意が必要です。
関連記事:耐震等級3で家族を守る!地震に強い家を作るための完全ガイド
転倒・破損リスクの高い設備
地震時に危険性が高い主な設備は以下の通りです。
大型冷蔵庫
重心が高く扉が開く構造のため、転倒や扉の飛び出しが起きやすい。
食器棚・本棚
中の物が飛び出しやすく、倒れた際に出入口や通路を塞ぐリスクがある。
ガス給湯器・エコキュート
屋外に設置されていることが多く、基礎との固定が不十分だと落下・故障の可能性がある。
洗濯機・乾燥機
排水管や電源との接続部が揺れで損傷し、水漏れや漏電につながる。
テレビ・電子レンジ等の家電
据え置き型の場合、滑りやすい棚や台の上から落下しやすい。
これらの設備は、多くの家庭で日常的に使用されており、倒れることで怪我の原因になったり、復旧作業を大きく妨げる可能性があります。
関連記事:後悔しない!耐震等級3の家づくりに欠かせない施工業者の選び方とチェックポイント
安全性を高める改善策
リスクを軽減するには、設備の固定や設置場所の見直しが有効です。以下のような対策を講じることで、被害を最小限に抑えることができます。
耐震ラッチ付きの収納家具を選ぶ
扉の飛び出しを防止し、内部の物が落下するのを抑えます。
転倒防止金具・耐震ジェルマットを活用する
家具や家電の底部を床や壁に固定し、揺れによる滑りや転倒を防ぎます。
給湯器・屋外設備の基礎固定を確認する
ボルトやアンカーで確実に固定されているかを点検し、不足があれば補強します。
高さのある家具は壁面固定する
L字金具などを使い、背の高い家具を壁にしっかりと留めましょう。
家電製品は滑り止めを使用する
テレビや電子レンジなど、移動可能な家電には耐震マットを敷いて安定性を高めます。
これらの改善策は、初期投資が小さい割に効果が大きいため、耐震等級3の家であっても必ず実施すべき基本対策といえます。
複数社の比較で300万円以上の差
家を建てるなら相見積もりで
複数社比較をやらなきゃ損!
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。
- 簡単な質問に回答(約3分)
- 希望のハウスメーカーを選択(複数可)
- 無料で「間取り」「見積もり」「土地探し」が届く!
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ
設備の配置と固定方法による安全性の向上

耐震等級3の住宅であっても、設備の配置や固定方法が適切でなければ、地震時の安全性は確保できません。実際の被災地調査では、構造は無事でも「家具が避難経路を塞いだ」「重要設備にアクセスできなかった」といった事例が数多く報告されています。設備の設置場所と固定の工夫が、家族の安全と生活維持に直結するのです。
関連記事:【保存版】住宅の引き渡し時に絶対見るべき!後悔しないためのチェックリスト
設備の適切な配置
地震発生時に素早く避難できるかどうかは、家具や設備の配置次第です。通路や寝室まわりのレイアウトは慎重に考える必要があります。
避難経路上に家具を配置しない
廊下や出入口周辺には、倒れる可能性のある家具・家電を置かないようにします。
寝室に背の高い家具を置かない
就寝中の転倒事故を防ぐため、ベッド付近には低めの家具のみを設置します。
家族が集まる場所は開放的に保つ
リビングやダイニングなどは、動線を妨げる配置を避け、余裕のあるスペースを確保しましょう。
非常用設備へのアクセスを確保する
蓄電池や非常用給水タンクなどは、家族全員が迷わずたどり着ける場所に設置しておくことが大切です。
固定方法の工夫
設備の転倒や移動を防ぐためには、設置時の固定方法が重要です。とくに大型家電や収納家具には、専用の耐震金具を使うのが基本です。
壁面固定:L字金具やベルトで壁と一体化させる
高さのある家具や食器棚などは、壁にネジ止めして固定すると安定性が増します。
床面固定:耐震マット・滑り止めシートの活用
冷蔵庫や洗濯機など、床に置く機器には耐震マットを敷き、振動や滑りを防止します。
配管部の補強:柔軟性のあるホースや可動式継ぎ手の導入
洗濯機や給湯器の配管部には、揺れに対応できる部材を使い、断裂や漏水を防ぎます。
電子機器の固定:ストッパーや耐震バンドを使用
テレビや電子レンジなどは専用の耐震バンドで棚に固定し、落下を防ぎます。
このように、配置と固定を見直すだけで、地震時のリスクを大幅に低減することができます。
非常時に役立つ設備の選び方と配置

地震の直後、電気・ガス・水道などのライフラインが一時的に停止することは珍しくありません。そんな中でも一定期間、自宅での生活を継続するには、非常用設備の備えが欠かせません。耐震等級3の住宅においても、これらの設備がうまく機能しなければ「安心して住み続けられる家」とは言えません。
非常用設備の選定ポイント
以下の設備は、災害発生後の数時間〜数日間、在宅避難を成立させるうえで重要です。
蓄電池・ポータブル電源
停電時にも照明やスマートフォンの充電が可能になり、情報収集と安全確保に役立ちます。
非常用給水タンク
上下水道が止まっても飲用・生活用水を一定量確保でき、トイレや手洗いに対応できます。
ガス・灯油式のポータブルコンロ
調理が可能になり、乳幼児や高齢者がいる家庭でも温かい食事を提供できます。
簡易トイレ・災害用トイレセット
排水設備が使えない場合の衛生対策として必須。長期間の避難にも対応できます。
非常用ライト・懐中電灯・ラジオ
夜間や停電時の行動、情報収集に欠かせません。電池や充電器の常備も重要です。
これらの設備は、購入するだけでなく、「どこに、どのように保管・設置するか」が生死を左右する場合もあります。
効果的な配置戦略
非常用設備は、いざという時にすぐに取り出せて使えることが重要です。そのためには、家の中での「配置」と「動線」の工夫が必要です。
蓄電池や給水タンクは玄関近くか納戸内に設置
外部搬出や交換がしやすく、かつ普段は邪魔にならない場所が適しています。
キッチン付近にポータブルコンロとボンベを常備
調理動線を活かして、火気使用の安全性を確保しつつ使用できる配置が望ましいです。
各部屋に小型ライトと懐中電灯を設置
夜間の停電に備え、枕元や棚に常備することで、暗闇での行動リスクを軽減できます。
トイレ横に災害用トイレセットを備蓄
使用場所の近くに備えておくことで、急な断水時でも迷わず対応できます。
家族で保管場所を共有・ラベリングしておく
誰が見てもすぐ分かるよう、収納にラベルを貼ったり、定期的に家族で場所の確認を行います。
非常時こそ「使える場所にあること」が最優先です。設備の性能だけでなく、導線設計や収納場所まで意識することで、より実効性の高い防災住宅が実現します。
複数社の比較で300万円以上の差
家を建てるなら相見積もりで
複数社比較をやらなきゃ損!
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。
- 簡単な質問に回答(約3分)
- 希望のハウスメーカーを選択(複数可)
- 無料で「間取り」「見積もり」「土地探し」が届く!
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ
設備のメンテナンス性と地震後の復旧しやすさ

地震による設備被害を最小限に抑えるには、耐震性や固定方法だけでなく、日頃からのメンテナンス性にも注目する必要があります。点検や修理がしやすい設計は、被災後の復旧スピードに大きく影響します。断水・停電時の復旧対応を円滑に進めるには、設備の配置や種類選びにも配慮が欠かせません。
メンテナンス性を高める工夫
設備が故障しやすい状況に備え、メンテナンスのしやすさを設計段階で確保しておくことが重要です。以下のポイントを押さえておきましょう。
給排水設備の点検口を設ける
床下・壁内に点検口があると、水漏れや配管トラブルの早期発見が可能になります。
フィルターや電池交換のしやすい家電を選ぶ
空気清浄機・換気扇・ガス検知器などは、メンテナンスの手間が少ない機種を選ぶと安心です。
設備マニュアルと保証書を一箇所に保管
メンテナンス時に必要な情報をすぐ確認できるようにまとめておくと、復旧対応がスムーズになります。
修理対応の早いメーカー・施工業者を選定
アフターサポートの体制が整っている会社を選ぶことも、復旧時の時間短縮につながります。
普段から手が届く場所にあり、構造を壊さずに点検できることがメンテナンス性の第一歩です。
地震後の復旧を考慮した設備選び
被災後にできるだけ早く通常の生活に戻るには、設備そのものの耐久性や復旧のしやすさも事前に考えておく必要があります。以下のような選定基準が有効です。
部品交換で対応できるモジュール構造の設備を選ぶ
給湯器やトイレなど、全交換ではなく部分修理が可能なタイプは復旧も早く経済的です。
自動停止機能付きの設備を導入する
揺れを感知して自動的に停止する給湯器や電源装置は、二次被害の防止と復旧の簡便さに寄与します。
耐水性・耐衝撃性に優れた屋外設備を選ぶ
屋外設置の蓄電池や配電盤は、防水構造のものを選ぶことで、豪雨や余震の影響を受けにくくなります。
復旧時に専門業者が不要な設備を検討する
一部の機器はユーザー自身で設定や復旧が可能な設計になっているため、即時の再使用が可能です。
これらのポイントを押さえておくことで、「壊れにくく、壊れても直しやすい」住宅設備を構築できます。
設計段階からの導入検討で得られるメリット

設備の耐震性や非常時の機能維持を後から追加・改善しようとすると、コストや手間がかさむだけでなく、空間的な制約により最適な対策が取りにくくなることもあります。だからこそ、住宅の設計段階から設備の安全性・利便性を考慮することが非常に重要です。
関連記事:耐震等級3の坪単価は本当に高い?差額・効果・後悔しない選び方を徹底解説
コスト面でのメリットの具体例
設計段階であらかじめ必要な設備や固定方法を想定しておくことで、施工時のコストや長期的な維持費用を抑えることができます。
関連記事:【保存版】耐震等級3の家はいくらかかる?総費用と賢い資金計画の立て方
設備スペースの確保により、後付け工事が不要になる
設計段階で収納・配線・配管のスペースを用意しておけば、後から壁や床を壊す必要がなくなります。
一括施工による割引や工賃削減が可能
建築と同時に設備の設置や補強を行うことで、工事回数が減り、コストダウンが期待できます。
無駄な機器選定の回避で予算の最適化
建築士や設備業者と連携して計画することで、必要十分なスペックの設備を選定でき、オーバースペックを防げます。
将来的な増設や交換も見据えた設計が可能
可変性のある設計にすることで、ライフスタイルの変化に応じた柔軟な対応ができます。
トータルでの費用を抑えつつ、機能性を高める設計が実現できるのは、初期段階の計画あってこそです。
トラブル回避のためのポイント
設計時から設備の選定と配置を検討しておくことで、将来的なトラブルや後悔を未然に防ぐことができます。以下のようなポイントが重要です。
関連記事:【徹底比較】耐震等級3の家づくりで後悔しない依頼先の選び方|ハウスメーカー・工務店・設計事務所の違い
設置位置による使い勝手の違いを事前に確認する
非常用設備や収納の配置をシミュレーションしておけば、実生活での不便を避けられます。
設備の点検・更新がしやすい構造にしておく
屋根裏や床下に配線・配管が集中しすぎると、点検時に手間がかかります。点検性を考慮した動線設計が大切です。
余震や水害も想定した設備の設置レベルを決める
地盤や地域特性に応じて設備の設置高さや基礎構造を調整しておくことで、災害全般への耐性が高まります。
情報共有と管理体制の設計段階での明確化
誰がどこに何を管理しているか、家族全員が理解している状態を築いておくと、緊急時にも慌てず対応できます。
設計段階から設備を含めた耐震対策を意識することで、「構造・設備・使い勝手・コスト」のすべてを高い水準でバランスよく整えることが可能になります。こうした配慮が、住まい全体の耐震性能と安心感を引き上げるカギとなるのです。
構造だけじゃない、設備まで備えてこそ本当に強い家

耐震等級3の住宅は、確かに地震に強い構造を持つ優れた住まいです。しかし、その性能を真に活かすには「内部設備の安全性と機能維持」までを含めた対策が不可欠です。いざという時に生活機能を失わないよう、設備の選定・設置・配置・固定・メンテナンスまで、包括的に備えることが求められます。
重要なのは以下のポイントです。
- 設備の固定・配置で二次被害を防ぐ
- 非常用設備の導入と使いやすさの確保
- 地震後の迅速な復旧を可能にする設計
- 初期設計段階での設備計画によるコスト削減とトラブル防止
これらを踏まえ、住宅を計画・設計する段階で、構造だけでなく「設備の耐震性と利便性」も重視すれば、家族全員が安心して長く暮らせる住まいが実現します。
地震に強い構造だけでなく、非常用設備や復旧のしやすさまで備えてこそ、家族を守れる本当に強い家となります。
憧れの大手メーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれる

住宅展示場や完成見学会にいくのは時間もかかるし大変…
そんなときに便利なのが「タウンライフ家づくり」です。
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
気になるメーカーや工務店を選び、希望の間取りや予算を入力するだけ。「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる!
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。

「タウンライフ家づくり」はこんな方におすすめ
- あなただけの間取りと見積もりを無料で手に入れ比較したい
- 営業されるのが嫌、苦手
- 自宅でじっくり信頼できるハウスメーカーを選びたい
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ


