この記事にはプロモーション・広告が含まれています
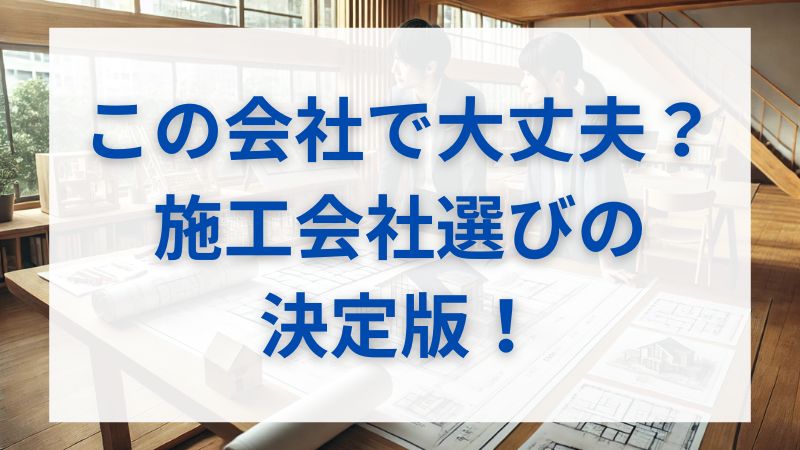
日本は世界有数の地震多発国として知られており、住宅の耐震性は命と財産を守るうえで極めて重要です。中でも「耐震等級3」は、住宅性能表示制度において最も高い耐震基準であり、消防署や警察署など防災拠点の建物と同等レベルの耐震性能を求められます。
この耐震等級3の住宅を実現するためには、単に性能の良い建材を使用するだけでは不十分です。信頼できる施工業者と、設計力に優れた建築士の選定が不可欠であり、その選択次第で住宅の安全性は大きく左右されます。
しかし、一般の施主にとっては「どの業者を信頼すべきか」「どのような基準で選べばよいのか」が分かりづらく、不安や疑問を抱えたまま進めてしまうケースも少なくありません。
関連記事:【地震に備える家づくり】耐震等級3の設計基準と施主が知っておくべき注意点
本記事では、耐震等級3の住宅を目指す方に向けて、施工業者や建築士の選び方、施工中に確認すべき品質チェックポイント、そして契約時の注意点まで、実践的な知識を体系的にご紹介します。記事を通して、地震に強い安心の住まいづくりを実現するための確かな判断材料を提供します。
54万人(2025年9月時点)以上が利用!信頼できるメーカーが見つかる
\ 複数社の比較で300万円以上の差 /
家を建てるなら相見積もりで
複数社比較をやらなきゃ損!
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。
- 簡単な質問に回答(約3分)
- 希望のハウスメーカーを選択(複数可)
- 無料で「間取り」「見積もり」「土地探し」が届く!
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ
耐震等級3に対応した施工業者選びの流れと見極めポイント

耐震等級3の住宅を実現するには、設計だけでなく「どの施工業者に依頼するか」が決定的なカギを握ります。信頼できる業者の選定は、単なる相性や価格だけでなく、専門性・対応力・実績のバランスで判断する必要があります。
施工過程には多くの判断ポイントがあるため、選定は一度きりの判断ではなく、段階ごとの確認が重要です。以下では、業者選びの基本的なステップから、比較・判断の具体的な方法までを時系列に整理し、初めての家づくりでも迷わず判断できるように解説します。
施工業者選びのステップとスケジュール感
業者選びは、資料請求から契約直前まで数カ月かかるのが一般的です。各段階で確認すべきポイントを時系列で押さえておくことが、後悔しない判断につながります。
| ステップ | 内容 | 目安時期 |
| 情報収集 | インターネット、SNS、住宅展示場などから候補をリストアップ | 着手から1カ月以内 |
| 相談・資料請求 | パンフレット・価格帯・工法・過去事例を入手 | 着手から1〜2週間 |
| 初回面談・見学 | 実際に担当者と話す、モデルハウス・完成見学会に参加 | 着手から1〜2カ月 |
| プラン提案・見積 | 間取り提案や見積もりを取得し、比較対象とする | 着手から2〜3カ月 |
| 最終候補の比較・意思決定 | 候補を絞り、性能や条件を精査 | 着手から3カ月前後 |
| 契約 | 提案と仕様に納得したら契約 | 3〜4カ月目以降 |
業者選定は「時間をかけて比較・確認する」ことが安全な家づくりの第一歩となります。
関連記事:【徹底比較】耐震等級3の家づくりで後悔しない依頼先の選び方|ハウスメーカー・工務店・設計事務所の違い
相談・資料請求段階で確認すべきこと
初期段階では、手当たり次第ではなく、「自分の希望に合うかどうか」を見極める選別力が求められます。
施工可能エリアかどうか
地域密着型の工務店はエリア制限があるため、最初に確認しておくべき基本情報です。
耐震等級3に対応可能かどうか
明確に「耐震等級3対応」をうたっているか確認。建築実績や認証取得経験も重要な指標になります。
対応のスピードと丁寧さ
資料請求や問い合わせに対する対応が早く、かつ誠実であるかは、今後の打ち合わせの質にも直結します。
過去の施工事例の質と数
写真や動画で事例を確認し、標準仕様と実際の施工の乖離がないかチェックします。
この時点で「情報を隠す姿勢」や「質問に曖昧な返答」がある業者は候補から外す勇気も必要です。
関連記事:【保存版】耐震等級3を確実に取る!設計審査の書類・手続き完全マニュアル
プラン提案から比較検討までの流れ
提案された間取りや構造、見積もり内容は、見た目や価格だけで判断せず、住まいの性能と将来性に焦点を当てて比較しましょう。
| 比較ポイント | チェック内容 |
| 耐震設計の根拠 | 構造計算の有無、壁量計算の提示、構造専門家の監修の有無など |
| 見積もりの明細 | 一式表示ではなく、詳細な内訳が提示されているか |
| 設備・素材の選択肢 | 標準仕様とオプションの線引きが明確か |
| メンテナンス性 | 長期修繕の視点から、将来の交換や補修が考慮されているか |
性能の根拠が「数字と書面」で説明されるかどうかが、信頼できる業者の大きな特徴です。
契約前にすべき最終確認ポイント
業者選びで最も大切なのが、この「契約前」の最終確認です。提案内容と現場の実態が一致しているか、将来的なトラブルを回避するために細かく詰めておきましょう。
設計図・構造図の内容確認
間取り図だけでなく、耐力壁の配置、金物の種類、構造計算書の提示有無など技術的な根拠を確認。
地盤調査と地盤改良の方針
着工前に行う地盤調査の有無と、それに応じた地盤改良計画が明確かどうかを確認します。
スケジュールと工程の明記
着工日・上棟日・完成日などの予定が具体的か、スケジュール変更時の対応ルールがあるか確認。
耐震等級3取得の証明書提出時期
申請時と完成後の評価取得時期、第三者機関の名称を含め、取得計画があるか確認します。
この段階での確認を怠ると、完成後に「想定と違う」リスクが高まり、修正も困難になります。
信頼できる工務店・ハウスメーカーの見極め方

業者を選ぶ際、表面的なブランド力や価格だけで判断してしまうと、後から「思っていた対応と違った」と後悔するケースは少なくありません。本当に信頼できる業者かどうかは、透明性・実績・提案力といった複数の視点から評価することが重要です。
以下では、チェックすべき3つの視点と、それぞれの見極め方について詳しく整理します。
透明性のある説明を行っているか
不明点に対して誠実に説明してくれるかどうかは、その業者の信頼度を判断する上での基本です。
価格の説明が明確か
「一式表示」ではなく、内訳ごとに見積もりが提示されているかを確認します。
工法や構造の説明に根拠があるか
耐震性能について「なんとなく強い」といった表現ではなく、壁量計算や構造図をもとにした説明があるかをチェックします。
打ち合わせ時の対応が誠実か
質問への対応が曖昧だったり、契約を急がせるような発言が多い場合は注意が必要です。
説明の透明性が高い業者ほど、完成後のトラブルが少ない傾向にあります。
過去の施工実績と顧客の声の確認
実績と顧客評価は、施工力と対応品質の確かな証拠になります。
| チェック項目 | 確認すべきポイント |
| 施工実績の提示 | 耐震等級3の実績があるか。件数や地域など具体的かどうか |
| 見学可能物件 | 完成住宅や構造見学会を公開しているか |
| OB顧客の声 | アンケート結果、レビュー、直接のインタビューが確認できるか |
| 施工事例の品質 | 写真・動画の公開があり、納まりの丁寧さが見えるか |
実績と顧客評価は、紙の提案資料よりもはるかに信頼性の高い判断材料です。
資金計画の提案力
予算の組み方が「現実的」であるか、「将来的に安心できる」かどうかも重要な選定基準です。
初期見積もりと最終価格の乖離リスクを説明しているか
後出しの追加費用が発生しやすい項目(地盤改良・外構工事など)について事前に説明している業者は信頼できます。
ライフプランを加味した資金計画か
単なる建築費の話ではなく、教育費・老後資金・固定資産税など、長期視点で話してくれるかどうかを見極めましょう。
住宅ローンの提案内容が適切か
金融機関との連携や金利プランの選定支援など、ファイナンシャル面のサポートがあると安心です。
信頼できる業者は「安さ」ではなく「予算との納得度」で勝負します。
複数業者の比較と優先順位のつけ方

複数の業者と打ち合わせを重ねると、どの会社も一長一短があり「最終的にどこを選ぶべきか」で迷うことは少なくありません。比較には客観的な基準と、自分にとっての優先順位の整理が必要です。判断の軸を明確にすることで、後悔のない決断が可能になります。
比較すべき主要な項目
業者を比較する際には、下記のように性能・信頼性・コストの観点で分けてチェックするのが効果的です。
| 比較項目 | 内容 | チェックポイント |
| 提案力 | 設計力や耐震構造の根拠 | 構造図や根拠あるプラン説明があるか |
| 実績 | 耐震等級3住宅の施工経験 | 施工件数・地域性・建物タイプの多様性 |
| 価格 | 初期見積と追加費用の明確さ | 内訳が詳細かつ変動リスクが説明されているか |
| 担当者の対応 | 説明のわかりやすさ、信頼感 | 不明点への回答が具体的か、無理な営業がないか |
| 評判 | 顧客満足度、口コミ、第三者評価 | 完成物件の紹介やOB訪問の可否 |
| 契約条件 | 保証制度、耐震性能の明記 | 契約書に耐震等級3の仕様記載があるか |
比較項目は「数字・書面・事例」で裏付けられているかが判断の分かれ目になります。
自分に合った業者の選び方
客観的な比較だけでなく、「自分たちの暮らしに合うかどうか」を見極める視点も重要です。家づくりは生活そのものであり、予算・将来設計・価値観が反映されるプロジェクトだからです。
自分たちのライフスタイルに合っているか
子育て世帯であれば家事動線や断熱性能に強い会社、高齢世代であればバリアフリー設計に実績がある会社が適しています。
柔軟な対応力があるか
標準仕様を押し付けるのではなく、要望に対してカスタマイズ可能かどうかでストレスの有無が変わります。
信頼関係が築けるか
技術面だけでなく、人間的な信頼感を持てる担当者かどうかも重要な判断材料になります。
業者選びの正解は1つではなく、「自分にとってベストなパートナーを見つけること」がゴールです。
打ち合わせで確認すべき具体的な質問
施工業者や設計士との打ち合わせでは、適切な質問を用意しておくことで、技術力や信頼性を具体的に見極めることができます。質問内容次第で「話しやすさ」だけでなく「専門性」も露呈するため、事前準備が重要です。
設計・構造に関する技術的な質問
設計段階での耐震性能は、図面上では見えにくいため、構造の根拠や判断基準を直接確認することが重要です。
耐震等級3に対応するために行っている設計の工夫はありますか?
耐力壁の配置、剛性バランスなどの専門的な設計意図を答えられるかがポイントです。
構造計算書や壁量計算書は確認できますか?
計算根拠を提示できる設計者は、技術的な信頼性が高い傾向にあります。
基礎や接合部に使う金物の仕様はどのようなものですか?
構造部材の選定理由を明確に説明できるかで、施工精度の高さが推測できます。
技術的な質問に対する回答の深さと明確さが、設計士の力量を判断する材料になります。
過去の施工事例・アフターサービスに関する質問
過去の実績やアフターサービスの考え方は、信頼性と長期的な安心感を測る重要な指標です。
これまでに手掛けた耐震等級3の施工例を見せてもらえますか?
実例を見せられるかどうかで、経験値や自信度合いが判断できます。
完成見学会や現場見学の機会はありますか?
施工の透明性やオープンな姿勢が確認できます。
引き渡し後の定期点検や保証制度について教えてください。
アフターサービスが体系化されているか、トラブル時の対応が明確かが重要です。
実績とアフターケアの質問には、業者の「姿勢」や「誠実さ」が表れやすくなります。
耐震等級3に関連する具体的な確認事項
耐震等級3の取得に関する対応力は、事前に確認しておかないと後でトラブルになることがあります。
耐震等級3の設計審査や評価機関の対応はお任せできますか?
評価申請の経験があるかどうかで、制度理解度が分かります。
耐震等級3の証明書はどのタイミングでもらえますか?
建築確認や竣工後に提出される書面の取り扱いについて明確な回答が必要です。
認定取得にかかる追加費用や申請スケジュールは?
想定外の費用や工期延長を避けるため、事前に確認しておくと安心です。
制度面に関する質問に対する正確な回答が、経験と誠実さの裏付けになります。
複数社の比較で300万円以上の差
家を建てるなら相見積もりで
複数社比較をやらなきゃ損!
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。
- 簡単な質問に回答(約3分)
- 希望のハウスメーカーを選択(複数可)
- 無料で「間取り」「見積もり」「土地探し」が届く!
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ
耐震等級3に強い設計士・建築士の特徴

耐震等級3の家づくりは、図面上の設計段階からすでに勝負が始まっています。どれだけ優れた工法や部材を用いても、構造計算や配置設計が不十分であれば、最大限の耐震性能は発揮されません。そのカギを握るのが、耐震設計に精通した設計士や建築士の存在です。
耐震設計に関する豊富な知識と経験
建築士の中にも、意匠設計を得意とする人と、構造設計に強い人がいます。耐震等級3を確実に実現したい場合には、構造設計に対する知識と実績がある専門家を選ぶ必要があります。
| 判断軸 | 確認ポイント |
| 過去の等級3設計経験 | 実際に耐震等級3を取得した案件数とその内容 |
| 専門資格の有無 | 一級建築士、構造設計一級建築士などの資格保持 |
| 提案内容の構造的根拠 | 耐震壁や柱の配置バランスに対する説明ができるか |
| トラブル対応経験 | 地盤や構造補強に関する柔軟な提案経験があるか |
特に「なぜこの配置なのか」「どこが耐力壁か」などを明快に答えられるかどうかで、設計の信頼性が判断できます。
最新の耐震技術や工法への精通
地震大国・日本では、耐震基準や工法が日々進化しています。その変化に追いついていない設計士では、現行基準に適合した家づくりが難しくなります。
最新の建築基準法改正への理解があるか
基準の改正ポイントや評価方法の変更を把握していないと、計画に不備が出る可能性があります。
制震・免震技術への知見があるか
特殊工法への理解や導入実績があれば、より柔軟な提案が期待できます。
耐震等級だけでなく、省エネ・長期優良住宅との連携も視野に入れているか
総合的な性能住宅としての設計力が求められます。
常に最新の法改正や技術トレンドをキャッチアップしている設計士ほど、信頼できるパートナーといえます。
業者の施工の質を判断するチェックポイント

設計がどれほど優れていても、現場での施工が不十分であれば、家の耐震性能は著しく低下します。完成した住宅を見ただけでは分かりにくい部分も多いため、施工の質を客観的に判断するための視点と行動が重要です。
完成した住宅の見学会への参加
現場の仕上がりを見ることは、施工力を肌で感じる最も効果的な方法です。
完成見学会で確認するべきポイント
クロスの仕上がりや隙間の有無、床の水平性などの「見える部分」の精度を確認できます。
構造見学会があるかどうか
建築中の現場で、柱・梁・耐力壁の施工状況が確認できる構造見学会に参加できるかも大きな評価ポイントです。
職人の作業環境と現場の整理状況
現場が清潔で整理整頓されているか、職人の挨拶や態度に丁寧さがあるかも、施工への姿勢を判断する材料になります。
施工現場の公開に積極的な会社ほど、技術と誠実さに自信を持っている傾向があります。
関連記事:【要確認】モデルハウスで“本物の耐震等級3”を見抜く5つの視点とは?
第三者機関の評価や認証の確認
完成後に耐震性が保証されるわけではありません。第三者による評価を通じて、設計・施工の信頼性を客観的に確認することが不可欠です。
| 評価項目 | 確認できる内容 | 主な評価機関 |
| 耐震等級の取得証明 | 等級3の認証が下りているか | 日本住宅性能表示制度(住宅性能評価機関) |
| 構造・劣化対策の等級 | 長期的な住宅性能 | 住宅性能評価書(設計・建設) |
| 瑕疵保険の加入状況 | 基礎や構造に対する保証内容 | JIO、日本住宅保証検査機構など |
第三者評価があるかどうかを必ず確認
契約前に「評価書の写し」や「認定取得予定日」など、書面で確認しておくと安心です。
設計評価と建設評価の両方を取得しているか
設計段階だけでなく、実際の施工が図面通りに行われたかを建設評価でチェックできます。
主観的な印象ではなく、書面と第三者の評価を根拠に判断する姿勢が、施工の質を見極めるうえで欠かせません。
複数社の比較で300万円以上の差
家を建てるなら相見積もりで
複数社比較をやらなきゃ損!
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。
- 簡単な質問に回答(約3分)
- 希望のハウスメーカーを選択(複数可)
- 無料で「間取り」「見積もり」「土地探し」が届く!
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ
耐震等級3の家づくりで注意すべき施工ポイント

耐震等級3の設計通りに建てられるかどうかは、現場での施工管理に大きく左右されます。正確な図面通りに工事が行われ、品質が保たれていることが、設計通りの耐震性能を実現する唯一の方法です。
関連記事:狭小地・不整形地でも諦めない!L字・三角・旗竿地でも実現できる耐震等級3の家
耐震等級3に適合した材料と工法の使用
材料や工法が設計図と異なっていると、耐震等級3は形式上取得できても、実質的な性能は確保されません。
| チェック項目 | 確認ポイント |
| 柱・梁のサイズと位置 | 図面通りに配置されているか現場で確認可能か |
| 耐力壁・筋交いの配置 | 耐震壁が図面と一致しているか |
| 金物の種類と設置位置 | 説明書通りの金物が正しい位置に使われているか |
| 使用木材・合板の仕様 | JAS認定など、規格品が使われているか |
- 設計通りに使用されているか、工程ごとに写真や現場立会いで確認することが重要です。
関連記事:耐震等級3で家族を守る!地震に強い家を作るための完全ガイド
関連記事:【徹底比較】在来工法とツーバイフォー、耐震等級3で本当に安心なのはどっち?
現場での施工管理と品質チェック
いくら優れた業者でも、現場での管理が行き届いていなければ、設計意図通りの施工は実現できません。
現場監督の配置と役割の明確化
担当監督が常駐するか、巡回型か、現場ごとの対応体制を確認しましょう。
第三者機関による中間検査
配筋検査、構造検査などを第三者が実施している場合、客観的なチェック体制が整っています。
工程ごとの報告と写真記録の提供
建築中の各工程で写真を撮り、施主にも共有する仕組みがあるかは、信頼度の指標になります。
雨水や湿気対策の管理
上棟前や断熱材施工時の天候管理、ブルーシートの使い方など細かな配慮も施工品質に直結します。
現場の管理が甘いと、小さな施工ミスが累積し、結果的に耐震性能を損なうリスクが高まります。
関連記事:耐震等級3を活かすには?地盤調査と基礎工事で家の強さは決まる
契約時に確認すべき重要事項

耐震等級3の住宅を建てる上で、契約書は「設計や施工の品質を保証する最後の砦」です。
見積書や口頭のやりとりだけでは後々トラブルに発展する可能性があるため、重要な項目は契約書に明文化し、保証制度や対応範囲についても細かく確認しておくことが極めて重要です。
関連記事:耐震等級3の坪単価は本当に高い?差額・効果・後悔しない選び方を徹底解説
契約書に耐震等級3の仕様を明記する
口約束や提案書だけでなく、契約書に正式な文言として「耐震等級3の住宅であること」が記載されているかどうかは、後のトラブル回避に直結します。
「耐震等級3」取得予定であることの記載
設計段階・建築確認申請時・完成時、どのタイミングで評価取得するのかを明記しておく必要があります。
性能表示制度の登録番号や評価機関の名称
どの第三者機関から認証を受けるのかを記載し、施主として確認可能な状態にしておきます。
仕様書と構造計算書の添付
図面だけでなく、具体的な構造設計資料も契約書に添付または保管文書として記載しましょう。
契約解除や設計変更時の条件整備
等級取得が困難になった場合の代替案や、違約条項の有無なども確認が必要です。
「契約書に明記されていない仕様は守られない」と認識し、記載の有無を徹底して確認しましょう。
関連記事:【2025年法改正】耐震等級3が事実上の義務に!建築基準法改正で家づくりはどう変わる?
保証内容とアフターサービスの確認
完成後に問題が発生した場合、どこまでが保証対象なのかを事前に知っておくことで、不安を最小限に抑えることができます。
| 確認項目 | 内容 | チェックポイント |
| 瑕疵保証の範囲 | 構造・雨漏りなどの基本性能保証 | 10年間の瑕疵担保責任があるか |
| 耐震性に関する保証 | 壁・基礎・接合部の性能劣化 | 対象部位・対応期間の明記 |
| アフターサービス制度 | 定期点検や無料修理対応 | 1年・2年・5年の点検スケジュールの明示 |
| 第三者保証加入状況 | JIO、ハウスプラスなど | 保険番号と内容が契約書に記載されているか |
書面に保証内容が記載されているかを必ず確認
口頭での説明だけに頼らず、保証規定のパンフレットや一覧表などを受け取りましょう。
アフター対応のフローや連絡方法の明示
トラブル時の対応ルートや担当窓口が不明確な場合は、あらかじめ質問しておくことが大切です。
完成後も安心して暮らすためには、「契約段階での保証とアフターサービスの明確化」が欠かせません。
関連記事:【保存版】住宅の引き渡し時に絶対見るべき!後悔しないためのチェックリスト
信頼できる施工会社を見極めて、後悔のない耐震住宅を実現しよう

耐震等級3の家づくりは、情報収集から契約、施工に至るまで、すべての段階で確かな判断が求められるプロジェクトです。設計士や業者を選ぶ際の見極め力、図面や構造計算の理解、現場管理や契約書の内容確認など、どれもが家の耐震性能を左右します。
「信頼できる情報」と「自分の目で確認する姿勢」が、安心・安全な住まいづくりの最大の武器」です。
以下に、耐震等級3の家を建てる際に特に重要となるチェックポイントをまとめます。
| 項目 | 重要ポイント |
| 業者選び | 提案力・施工実績・誠実な対応のバランス |
| 設計者の見極め | 構造設計への理解と最新技術への対応力 |
| 現場管理 | 材料の正確な使用と中間検査の有無 |
| 契約書の内容 | 耐震等級3の明記と保証制度の確認 |
| 第三者評価 | 設計・建設評価の取得状況の確認 |
ひとつひとつの判断を丁寧に重ねていくことで、後悔のない耐震住宅を実現できます。
関連記事:耐震等級3で後悔する人の共通点とは?必要な人・不要な人を徹底解説
憧れの大手メーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれる

住宅展示場や完成見学会にいくのは時間もかかるし大変…
そんなときに便利なのが「タウンライフ家づくり」です。
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
気になるメーカーや工務店を選び、希望の間取りや予算を入力するだけ。「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる!
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。

「タウンライフ家づくり」はこんな方におすすめ
- あなただけの間取りと見積もりを無料で手に入れ比較したい
- 営業されるのが嫌、苦手
- 自宅でじっくり信頼できるハウスメーカーを選びたい
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ


