この記事にはプロモーション・広告が含まれています
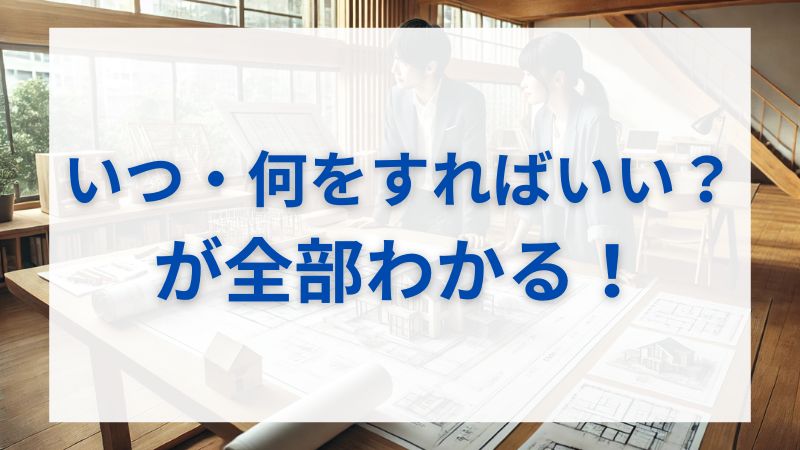
家づくりは多くの人にとって、一生に一度の大きなプロジェクトです。地震が多い日本では、「耐震性」は住宅選びにおいて極めて重要な要素とされています。
その中でも「耐震等級3」は、建築基準法の1.5倍の耐震性能を誇り、最も高い基準とされています。これは災害時に避難所となる消防署や警察署と同等の耐震性です。
しかし、そのような高性能住宅を建てるには、計画段階から綿密なスケジュール管理と工程の理解が必要です。
住宅建設には多くのステップがあり、準備不足やスケジュールの乱れは後悔につながるリスクをはらんでいます。初めて家を建てる施主にとっては、何から始めればいいのか、どの段階で何をするべきかが見えづらいものです。
本記事では、耐震等級3の住宅を建てるための工程やスケジュールをわかりやすく時系列で解説し、施主が迷わず安心して家づくりを進められるようにサポートします。
どの段階で何に注意すべきか、どんな行動が必要なのかを具体的に示しながら、理想の住まいづくりを成功に導くための実用的な知識をお届けします。
54万人(2025年9月時点)以上が利用!信頼できるメーカーが見つかる
\ 複数社の比較で300万円以上の差 /
家を建てるなら相見積もりで
複数社比較をやらなきゃ損!
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。
- 簡単な質問に回答(約3分)
- 希望のハウスメーカーを選択(複数可)
- 無料で「間取り」「見積もり」「土地探し」が届く!
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ
家づくり全体の流れとスケジュール感

耐震等級3の家を建てるには、計画から引き渡しまでの全体像を把握することが重要です。各工程で必要な期間や、施主が関与すべきポイントを理解することで、無理のない家づくりが実現できます。
関連記事:【地震に備える家づくり】耐震等級3の設計基準と施主が知っておくべき注意点
家づくりの全体的な流れ
家づくりは「準備・設計・施工・完成・入居」という一連の流れをたどります。以下に、全体のステップを一覧で整理します。
| ステップ | 内容の概要 |
| 情報収集・資金計画 | 住宅展示場見学、予算設定、ローン相談 |
| 土地選定 | 希望エリアの調査、地盤や周辺環境の確認 |
| 施工会社の選定 | 設計事務所または工務店・ハウスメーカーとの契約 |
| 設計・仕様決定 | 間取り設計、耐震構造の検討、建材・設備の選定 |
| 着工前準備 | 地盤調査、確認申請、施工スケジュールの確定 |
| 施工 | 基礎工事~上棟~内装仕上げまでの現場工程 |
| 完成・引き渡し | 検査完了後、施主立会いのもと引き渡し |
| 引っ越し・アフター対応 | 入居と同時にアフターサービス開始 |
この流れを意識することで、各フェーズで何をすべきかが明確になります。
関連記事:耐震等級3で家族を守る!地震に強い家を作るための完全ガイド
目安となるスケジュール感
家づくりには、想像以上に長い期間がかかることもあります。以下の表は、各段階ごとのおおよその期間を示したものです。
| 工程 | 期間の目安 |
| 情報収集・準備期間 | 約1〜3か月 |
| 土地探し・契約まで | 約1〜3か月 |
| 施工会社との契約・設計 | 約2〜4か月 |
| 着工準備・申請手続き | 約1〜2か月 |
| 工事期間(基礎〜竣工) | 約4〜6か月 |
| 引き渡し・引っ越し準備 | 約1か月 |
合計すると、家づくり全体で8か月〜15か月ほどかかることが一般的です。予定が詰まりすぎると、設計の検討や仕様の確認が十分にできず、後悔を招く原因となります。
家づくりでは、工程ごとのスケジュールに余裕を持たせることが、後悔を防ぐ最大のポイントです。
天候不良や資材不足、法的手続きの遅延など、外的要因によってスケジュールが変動することも想定しておく必要があります。
スムーズな家づくりを実現するには、スケジュール管理に加え、家族内での意思統一や柔軟な対応力も欠かせません。
関連記事:【2025年法改正】耐震等級3が事実上の義務に!建築基準法改正で家づくりはどう変わる?
関連記事:【保存版】耐震等級3を確実に取る!設計審査の書類・手続き完全マニュアル
耐震等級3の家づくりに向けた施工会社選定前の準備

理想の住まいづくりは、実は「施工会社と契約する前」からすでに始まっています。この段階での準備が、その後のスケジュール進行や家の性能に大きく影響するため、丁寧な情報整理と行動が不可欠です。
予算の設定と資金計画
住宅建築における資金計画は、家づくりのすべての前提となる重要なステップです。無理のない予算を設定し、後悔のない選択をするためには、住宅費用全体を明確に把握する必要があります。
| 項目 | 内容 |
| 土地代 | 希望エリアの地価や条件によって大きく異なる |
| 建物本体価格 | 坪単価×延べ床面積で計算。性能によって価格も変動 |
| 諸費用 | 設計料、申請費、登記費、火災保険などの各種費用 |
| 外構・家具・引っ越し | 意外に高額になるため、別予算で確保が必要 |
| 予備費 | トラブルや想定外の出費に備えて10%前後を見込む |
予算の中に「耐震等級3に必要な構造強化費」も含めておくことが、後の仕様変更リスクを防ぎます。
住宅ローンを利用する場合は、早期に金融機関と相談し、事前審査のスケジュールも確保しましょう。
関連記事:【保存版】耐震等級3の家はいくらかかる?総費用と賢い資金計画の立て方
関連記事:耐震等級3の坪単価は本当に高い?差額・効果・後悔しない選び方を徹底解説
土地の選定と調査
どんなに優れた建物を計画しても、土地が合わなければ計画通りの家は建てられません。土地選びでは、耐震性やライフスタイルに直結するポイントを確認する必要があります。
地盤の強さ
地盤が弱いと、地盤改良工事が必要となり、費用や工期に影響を及ぼします。
災害リスクの有無
洪水、液状化、地滑りなどのリスクがある地域は、住宅性能を高めても安心とは言えません。
周辺環境・インフラ
道路幅、通勤通学、日当たり、騒音など、生活の快適性も事前に確認しましょう。
不動産会社に依頼するだけでなく、ハザードマップや自治体の地盤情報も活用し、将来の安心感を得る判断材料とします。
関連記事:狭小地・不整形地でも諦めない!L字・三角・旗竿地でも実現できる耐震等級3の家
関連記事:耐震等級3を活かすには?地盤調査と基礎工事で家の強さは決まる
設計事務所や施工会社の選定
耐震等級3の実現には、高い設計力と施工力を持つパートナーが必要です。信頼できる事業者を選ぶためには、候補を比較し、対応力や実績を見極める目が求められます。
耐震等級3の実績があるか
構造計算や認定取得の経験がある会社でなければ、耐震等級3の確実な実現は困難です。
コミュニケーション力
質問に対して丁寧かつ具体的に回答してくれるかを確認しましょう。
設計力・施工力のバランス
デザイン重視か技術重視か、会社ごとの強みに注目し、理想に合う方向性を選びます。
資料請求だけでなく、実際に担当者と会って話すことで、信頼できるかどうかを肌で感じることも重要です。
関連記事:【徹底比較】耐震等級3の家づくりで後悔しない依頼先の選び方|ハウスメーカー・工務店・設計事務所の違い
関連記事:【徹底比較】在来工法とツーバイフォー、耐震等級3で本当に安心なのはどっち?
施工前のスケジュール調整と段取り
施工会社の選定が済んでも、すぐに工事が始まるわけではありません。着工前には複数の準備工程があり、それらを滞りなく進めるためには、施主側の段取り力も問われます。
| 項目 | 必要な準備・対応 |
| 設計確定 | 間取りや仕様、構造設計を確定させる |
| 確認申請 | 建築確認を自治体に提出し、承認を得る |
| 地盤調査 | 必須項目。設計や基礎仕様に大きく関わる |
| 工事スケジュール調整 | 気候や人員確保の都合で時期がずれる可能性あり |
| 契約締結 | 工事請負契約を正式に結び、着工準備完了 |
この段階で「余裕あるスケジュール」を組んでおくことで、後の工程の詰まりや焦りを避けることができます。
着工日だけでなく、設計確定の期限、地盤調査日の設定、各種打ち合わせのタイミングなども含めて、カレンダーに落とし込んで管理していくのがおすすめです。
複数社の比較で300万円以上の差
家を建てるなら相見積もりで
複数社比較をやらなきゃ損!
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。
- 簡単な質問に回答(約3分)
- 希望のハウスメーカーを選択(複数可)
- 無料で「間取り」「見積もり」「土地探し」が届く!
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ
施工工程とスケジュールのポイント

施工段階は家づくりの核心であり、耐震等級3を実現するための重要なフェーズです。各工程の意味とスケジュールを理解することで、施主自身がより納得できる家づくりを進めることができます。
耐震等級3を実現するための設計段階のポイント
耐震性能の要は「設計段階」で決まります。計算根拠のある設計がされているかどうかが、住宅の安全性を左右します。
構造計算の実施
耐震等級3を取得するには、許容応力度計算と呼ばれる構造計算が必要です。これは、建物にかかる力と部材の耐力を数値で確認する高度な検討方法です。
バランスのよい構造配置
壁の配置や耐震壁のバランスが取れていないと、地震時に偏った揺れが発生しやすくなります。
使用材料の強度確認
柱・梁に使用される木材や接合金物など、強度の確かな材料を選定する必要があります。
設計段階で構造的な整合性が取れていない場合、いくら現場で施工を丁寧にしても耐震性能は保証されません。
この段階から構造に強い設計者と連携することが、耐震等級3を確実に実現する鍵です。
地盤調査と基礎工事
建物の基礎を支える「地盤」は、構造以上に見落とされがちな重要ポイントです。地盤の状況に応じて、基礎仕様も変わります。
| 工程 | 内容と施主の確認ポイント |
| 地盤調査 | スウェーデン式サウンディング試験が一般的。地盤の硬さや支持力を把握する |
| 調査結果の説明 | 地盤改良が必要かどうか、どのような工法が選ばれるかを確認 |
| 基礎設計 | ベタ基礎や布基礎など、構造や地盤に応じて選定される |
| 配筋検査 | 鉄筋の太さ・本数・配置が設計通りになっているか第三者機関がチェック |
地盤調査とその対策は、後から変更できない「家づくりの土台」です。最初にしっかり確認する姿勢が重要です。
耐震等級3の性能を確保する構造強化の方法
地震に強い家にするには、構造部材の配置や接合方法にもこだわる必要があります。
耐力壁の配置
耐力壁は地震の揺れを受け止める構造要素で、建物全体のバランスに合わせて配置されます。
柱・梁・筋交いの施工
柱や梁の接合部には金物補強が行われ、筋交いで水平力に対応します。
床・屋根の水平剛性確保
剛床工法や火打ち梁などで、建物の変形を抑える構造とする必要があります。
これらの施工は、設計図面に基づき正確に実行されなければ意味がありません。中間検査や工事監理によって、確実な施工が担保されます。
構造強化は目に見えない部分だからこそ、確実な記録とチェック体制が不可欠です。
引き続き、各工程にかかる期間や工事監理のポイントについて解説します。
各工程の所要期間と目安
家づくりは一朝一夕に完成するものではなく、各工程ごとに一定の期間が必要です。以下に平均的な目安を整理しました。
| 工程 | 所要期間 | 備考 |
| 設計・仕様決定 | 約1〜3か月 | 細部の打ち合わせ次第で延びる傾向あり |
| 地盤調査・確認申請 | 約1か月 | 申請の承認待ちに時間がかかることも |
| 基礎工事 | 約2〜3週間 | 地盤改良がある場合は追加期間が必要 |
| 上棟(構造躯体の組立) | 約1週間 | 上棟式を実施する場合もあり |
| 内外装工事 | 約2〜3か月 | 天候や仕様変更で変動しやすい |
| 最終仕上げ・検査 | 約1〜2週間 | 完了検査、施主検査、手直し期間含む |
各工程の進行状況によっては、次の工程にずれ込むリスクがあるため、予備日を設けることが大切です。
季節によって施工ペースが変わる点にも注意が必要です。梅雨や真冬は、コンクリートの養生や外壁工事に影響が出ることがあります。
工事監理と施主の関わり方
耐震等級3を確実に実現するためには、専門家の「工事監理」と施主自身の関わり方が重要になります。現場に任せきりではなく、施主自身も主体的に情報を把握しておくことで、施工ミスの早期発見や品質向上につながります。
設計者による工事監理
設計と工事を別の機関が行う場合は、第三者としての監理者が必要です。図面通りに工事が進んでいるかを確認します。
中間検査・完了検査の立会い
指定確認検査機関による法的検査に加え、独自に中間立会いを求めることも可能です。
定期的な現場訪問
施主が週1〜2回の頻度で現場を訪れることで、不明点の早期相談や現場の状況確認ができます。
工事監理の質は、最終的な住まいの安心感と直結します。積極的な関与がトラブルを未然に防ぐ手段です。
現場に足を運ぶことで、実際の施工精度や進捗を目視で確認でき、完成後の満足度にもつながります。信頼関係を築くうえでも、現場とのコミュニケーションは非常に有効です。
スケジュール管理と進捗確認の実践方法

計画通りに耐震等級3の家を完成させるためには、スケジュール管理と進捗確認が非常に重要です。施主自身が主体的に動き、施工会社との連携を図ることで、遅延リスクを最小限に抑えることができます。
工期の調整と遅れへの対策
スケジュール通りに進めるためには、あらかじめトラブル発生時の対処法を考えておくことが有効です。
| 想定される遅延原因 | 具体例 | 対応策 |
| 天候の影響 | 長雨、台風、降雪 | 雨天に弱い工程を前後で調整する柔軟な組み換え |
| 資材不足 | 建材納品の遅れ | 注文時期を前倒しし、代替案の選定も検討 |
| 設計変更 | 仕様の見直しや追加要望 | 変更は最小限にし、都度工期への影響を確認 |
| 人員の確保 | 大工や専門業者の人手不足 | 繁忙期を避け、早期に工事日程を確定 |
スケジュールが一度狂うと、次工程全体に影響を与えるため、リスクの見積もりと対策は必須です。
契約前の段階で「予備日」を含んだスケジュール提示を施工会社に求めるのも有効です。
定期的な進捗確認と報告
工事の進行状況を定期的に把握することは、計画と実際のズレを早期に修正するために欠かせません。
報告の形式を決める
写真付きメール、週次の報告書、口頭での進捗報告など、情報の共有方法を事前に取り決めておきます。
確認すべき主な項目
工程ごとの完了日、検査予定日、工事中の変更点、使用資材の到着状況などが含まれます。
質問しやすい関係づくり
気になることを遠慮せずに確認できる関係を築くことが、安心感と品質確保に直結します。
報告は「受け取るだけ」でなく、内容を施主が理解し、次の判断材料にできるよう意識することが重要です。
進捗確認は義務ではなく「家づくりを成功させるための共同作業」として前向きに取り組みましょう。
施工会社との進捗確認のタイミング
進捗確認のタイミングを誤ると、問題の早期発見や対応が遅れ、工期に影響を及ぼす可能性があります。効果的なタイミングを押さえ、要所での確認を怠らないことが重要です。
| タイミング | チェックポイント | 施主の行動 |
| 着工前 | 地盤調査結果、設計図の最終確認 | 設計者・現場監督と内容を共有 |
| 基礎工事完了時 | 配筋状況、コンクリート打設の確認 | 写真記録を依頼し、第三者検査も視野に |
| 上棟後 | 構造の組立状況、金物の取り付け | 設計図と照らし合わせて確認 |
| 内装工事中 | 断熱材や設備機器の設置 | 変更点がないか口頭で確認 |
| 引き渡し直前 | 建具・設備・仕上がりのチェック | チェックリストをもとに立会い検査を実施 |
進捗確認は「節目ごと」に行うことで、効率的に問題を発見しやすくなります。
工事中の現場は日々変化します。都度の確認が難しい場合でも、写真報告を活用することで一定の情報共有が可能です。
施工中の突発的な問題とスケジュール調整
現場では想定外のトラブルが発生することもあります。事前の予測が難しいケースこそ、冷静かつ柔軟に対応できる体制づくりが求められます。
天候不順による工程遅延
外構や屋根工事など、天候に左右されやすい作業は優先順位を調整することで影響を最小限に抑えられます。
設備の納期遅延や欠品
キッチン・バスなどの人気設備は納期が不安定な場合もあるため、代替品の選定基準も用意しておくと安心です。
職人や業者の都合
人手不足や体調不良などが原因で、急な日程変更が発生することもあります。進捗確認の頻度を高め、事前察知を心がけましょう。
突発的な問題に直面したときは「原因」「対応策」「影響範囲」の3点を整理し、早めに施工会社と共有することがカギとなります。
慌てず、冷静に対処することでスケジュール遅延を最小限にとどめることが可能です。
施工の品質チェックとスケジュールの連携
品質の確保とスケジュールは密接に関係しています。工期を優先しすぎると、施工精度に影響が出る場合もあるため、バランスの取れた管理が必要です。
中間検査と記録の保存
各工程での写真記録や検査報告書は、後のトラブル防止に役立ちます。
外注業者の施工品質確認
下請け業者が複数関与する場合、それぞれの施工精度にも目を向ける必要があります。
仕上がり確認のタイミングを明確に
最終工程に入る前に、扉の建て付けや塗装のムラなど細部をチェックできる時間を設けておきましょう。
スケジュールの都合で検査や確認が省略されることがないよう、「施主としての検査時間」も計画に含めておくことが重要です。
品質と工期は両立可能です。そのためには事前準備と密な情報共有が欠かせません。
関連記事:耐震等級3を活かすには?地盤調査と基礎工事で家の強さは決まる
関連記事:【要確認】モデルハウスで“本物の耐震等級3”を見抜く5つの視点とは?
関連記事:耐震等級3で家族を守る!地震に強い家を作るための完全ガイド
複数社の比較で300万円以上の差
家を建てるなら相見積もりで
複数社比較をやらなきゃ損!
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。
- 簡単な質問に回答(約3分)
- 希望のハウスメーカーを選択(複数可)
- 無料で「間取り」「見積もり」「土地探し」が届く!
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ
引っ越し準備と引き渡し後のスケジュール管理

建物の完成が見えてくると、次に考えるべきは「引っ越し準備」と「入居後の段取り」です。ここを怠ると、せっかくの完成直後に慌ただしくなったり、トラブルの原因にもなりかねません。余裕を持って計画し、スムーズな住み替えを実現しましょう。
引っ越し前の最終チェックリスト
引き渡し前には、以下のチェックを確実に行うことが重要です。チェックリスト形式で管理すると漏れを防げます。
| チェック項目 | 内容 |
| 施主検査の実施 | 建具の建付け、壁紙の仕上がり、キズなどを細かく確認 |
| 設備の動作確認 | 給湯器、換気扇、照明、インターホンの動作確認 |
| 書類の受け取り | 保証書、取扱説明書、検査済証の確認 |
| 水道・電気・ガスの手続き | 各インフラの開栓連絡と立ち会い予約 |
| 鍵の受け渡し | 玄関・勝手口など、全ての鍵の受領と動作確認 |
引き渡し前の確認を怠ると、引っ越し後の修理や問い合わせが必要になり、生活の立ち上がりがスムーズにいかなくなります。
最終確認の際は、できれば家族全員で訪れ、複数人の目で細部をチェックすることをおすすめします。
関連記事:【保存版】住宅の引き渡し時に絶対見るべき!後悔しないためのチェックリスト
引っ越し業者の選定とスケジュール調整
引っ越し業者の手配は、繁忙期には希望日が取りにくくなるため、早めの行動が必要です。3月・9月は引っ越しが集中しやすいため注意しましょう。
比較検討は3社以上が理想
相見積もりを取ることで価格とサービス内容のバランスが把握しやすくなります。
現地見積もりを依頼する
正確な荷物量を確認できるため、後のトラブルが減ります。
荷造りスケジュールの逆算
荷造り開始日、粗大ごみの回収日、処分品のリストアップなどを早めに着手しましょう。
引っ越しの成功は「準備期間をどれだけ確保できるか」にかかっています。共働き世帯は、週末だけで荷造りを終えるのは困難です。
必要に応じて、梱包サービスの利用も検討することで負担を軽減できます。
竣工から引っ越しまでのスケジュール感
建物の完成から実際の入居までには、いくつかの手続きを経る必要があります。段取りを把握しておくことで、慌てずスムーズに移行できます。
| 時期 | 主なタスク | 補足内容 |
| 完成検査 | 建築士・行政による検査 | 合格後に検査済証が交付される |
| 施主検査 | 仕上がりやキズの確認 | 不具合は修正依頼を出す |
| 引き渡し日 | 鍵の受領・書類の確認 | この日から所有者としての責任が発生 |
| 引っ越し準備 | 荷造り・業者手配 | できれば1週間以上前から開始 |
| 引っ越し当日 | 搬入・設置・電化製品の確認 | ライフライン開通もこのタイミング |
引っ越しは「建物完成=即入居」ではないため、最低でも1〜2週間の余裕を見て計画することが大切です。
施主検査で不具合が見つかった場合、修繕期間が必要になることも想定しておきましょう。
引っ越し日程の前倒しや後倒しを避ける方法
引っ越し日程が急に変わると、業者やライフラインの再調整が必要となり、大きな負担になります。以下の工夫で、スケジュールのズレを最小限に抑えられます。
完成予定の2〜3週間後を引っ越し日に設定する
不具合の修正や書類手続きの遅れをカバーできます。
工事進捗をこまめに確認し、日程の目安を更新する
予定通りに進んでいない場合は、早めに再調整を行います。
引っ越し業者には「予備日」を伝える
最悪の場合に備えて、2候補程度の予備日を持っておくと安心です。
引っ越し日がずれることで、新居と旧居の家賃が重複したり、学校や職場の通勤に支障が出るケースもあるため、余裕を持った計画が不可欠です。
仮住まいが必要になる場合には、事前に候補を調べておくと慌てずに対応できます。
引っ越し後のアフターケアスケジュール
新居での生活が始まった後も、建物の状態確認や不具合対応などのアフターケアが必要です。長く安心して暮らすためには、入居後のスケジュールも意識しておきましょう。
引っ越し後1週間以内
住宅設備や電気機器の動作確認。不具合があればすぐに連絡。
1か月点検(任意)
建具の建付けやクロスの浮きなど、細かい不具合をチェック。
半年〜1年点検(施工会社主導)
基本的な保証対応がある時期なので、見落としがないようにします。
| 時期 | 主なチェック内容 |
| 1週間以内 | 設備・水漏れ・換気・窓の開閉 |
| 1か月後 | 内装の剥がれ、ドアの建付け |
| 6か月〜1年後 | 床鳴り、給湯・配管系統の不具合 |
アフターケアは「対応してくれるかどうか」だけでなく、「記録を残しておくこと」もポイントです。写真付きでメモを残すことで、説明時の誤解を防げます。
保証書や問い合わせ先の管理も含めて、入居後の安心を支える体制を整えておきましょう。
関連記事:耐震等級3の家でも危ない?地震に負けない設備選びと設置のポイント
耐震等級3の家づくりを成功させるためのスケジュール

耐震等級3の住宅を実現するためには、設計・施工・引っ越しまでの全工程において、段取りとタイミングを適切に管理することが鍵となります。各ステップには明確な目的と役割があり、それぞれが連動して初めて理想の住まいが完成します。
関連記事:家族の命を守る防災住宅──地震に「強い家」で暮らそう
以下に、全体のスケジュールと施主が取るべき行動を一覧で整理します。
| フェーズ | 主な内容 | 施主の行動 |
| 準備段階 | 資金計画、土地探し、施工会社選定 | 情報収集、予算設定、信頼できるパートナー選び |
| 設計段階 | 間取り・仕様決定、構造設計 | 家族の希望を整理し、耐震性能の理解と確認 |
| 着工前 | 地盤調査、確認申請、契約 | 工程スケジュールを確認し、余裕を持った日程管理 |
| 施工段階 | 基礎工事〜上棟〜内装工事 | 現場チェック、進捗報告の受領と理解、不具合指摘 |
| 完成・引き渡し | 最終検査、設備確認 | チェックリストをもとに不備の確認と修正依頼 |
| 引っ越し準備 | 荷造り、業者選定 | 日程調整と余裕を持った作業スケジュール確保 |
| アフターケア | 点検対応、不具合連絡 | 記録と連絡体制の整備、保証内容の再確認 |
スケジュールを可視化し、計画的に行動することで「慌ただしさ」や「想定外のトラブル」を回避できます。
耐震等級3のように高性能な住宅は、設計や構造への配慮が重要になるため、早期の準備と進捗確認の姿勢が欠かせません。
後悔しない家づくりを実現するには、「何を」「いつまでに」「どう動くか」を常に意識し、主体的にスケジュールを管理することが求められます。
関連記事:耐震等級3で後悔する人の共通点とは?必要な人・不要な人を徹底解説
理想の住まいは、段取りと確認の積み重ねによって築かれるものです。しっかりとしたスケジュール管理で、安心と納得の家づくりを成功に導きましょう。
憧れの大手メーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれる

住宅展示場や完成見学会にいくのは時間もかかるし大変…
そんなときに便利なのが「タウンライフ家づくり」です。
3分で完了!希望条件を入力するだけ
全国1,200社(大手36社含む)以上の優良ハウスメーカーと提携、運営歴13年(2025年時点)、累計利用者54万人!
気になるメーカーや工務店を選び、希望の間取りや予算を入力するだけ。「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を複数社から無料でもらえる!
大手メーカー、地域密着型の工務店など、厳選された1,170社以上の優良企業と提携

「タウンライフ家づくり」は54万人が利用する安心のサービスです
たった3分で申し込み完了。手数料も営業もなし!希望条件を入力するだけ。

「タウンライフ家づくり」はこんな方におすすめ
- あなただけの間取りと見積もりを無料で手に入れ比較したい
- 営業されるのが嫌、苦手
- 自宅でじっくり信頼できるハウスメーカーを選びたい
\ 300万円の差額実績あり /
【PR】タウンライフ


